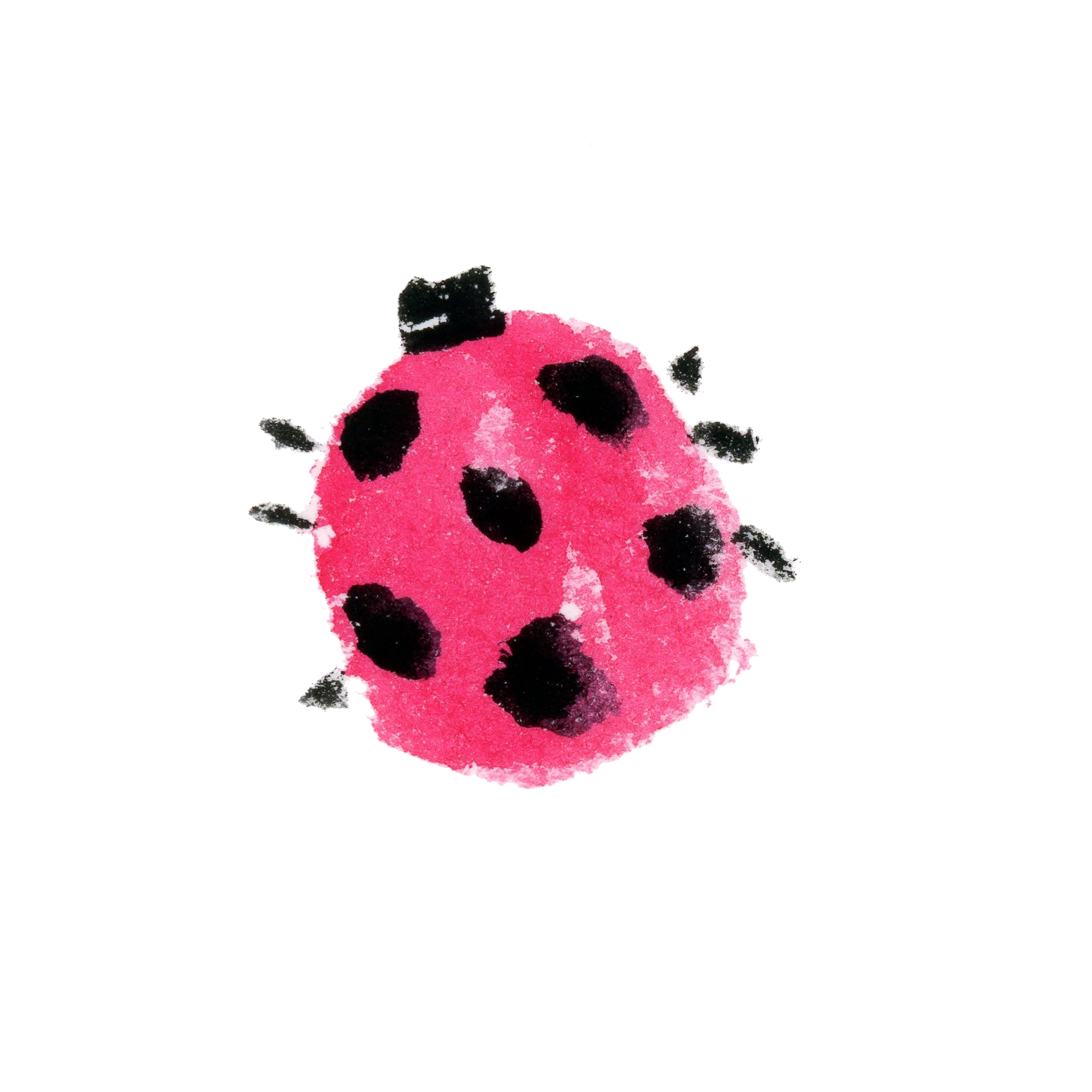
旅情
俺もこいつも随分と年を食った。
自分より幾分か若い女は、出会った頃はまだ小娘然としたあどけなさの残る女だった。いつまでもその時の感覚でいたが、こうしてまじまじと見つめると柔らかい肌や刻まれた皺にささやかな歴史を感じる。
「なに?」
不躾な視線に不快そうに潜めた眉にも、すっかり消えない皺を見つけて少しにやけた。指でなぞると「やめてよ」と身を捩る。
「老けたよね!?」
「昔よりマシになった」
「昔はいつでもこういうシチュエーションになれる準備してたのに……」
ちゃぷ、と湯から両手を引き上げて、水面が揺れる。連れ合うように湯気が揺らいだ。まとめ上げた髪が少し湿っていくらかうなじに張り付いている様は健やかに艶めかしい。他に人の居ない部屋つきの露天風呂だからと逆にタオルを巻いている。白いパイル地からバター色の肌が覗いて、少しにごりのある湯の中で幻みたいに漂っている。
この人間も、いつしかそういうものが似合うようになっていたのだ。
「自分がいつでも男盛りだからって」
わざとやっかむような視線を作ってこちらを睨めつけたあと、勝ち気な瞳が少し曇る。
こちらは痩せた。持ち前の身長こそそう変わらないが、食べる量が減り、体重も筋肉量も全盛期よりごっそりと減った。当然目の前のこいつよりもより深い皺があちこちに刻まれて、腹には未だ病理と闘うためのポートが埋まっている。水分と栄養は点滴でも追いつかず慢性的に不足していて、昔の無茶が祟ったのか関節もあちこち痛む。少し歩くのにも杖が必須で、すぐに座り込みたくなる。指先の精密操作には翳りがあった。
明らかに衰えているのだ。
「往年の映画スターみたいな身体しちゃって」
「どいつかによるな」
「うーん、メル・ギブソン?」
「いまの姿を知らねェ」
多分褒めたんだろうなと思うが。
湯の中で揺れる葉を手のひらで掬っては逃す遊びに興じている女から目をそらして、空を見上げる。冷たい空気のむこうで月が雲にかくれている。暗い夜だ。だが静かではない。風が強く、木々がざわめいている。
悪くないなと思った。風情があるのは嫌いじゃない。
「TETSUさんはさ」
木の音に紛れるように声がする。「将来どうなりたい?」。視線を向けずともちゃんと聞こえていることなどわかっているのだろう。返事を待つように少しだけの沈黙が湯気の間を揺蕩う。
「オレに将来があるかよ」
「私いまだに『大きくなったらパン屋さんになりたい』とか考えてるよ」
「はやく現実に追いつけ」
「あとはねぇ、遺産相続を譲介にすべきかどうか本気で悩んでる」
「お前にはまだ早ぇだろ」
「いつなにがあるかわかんないからさぁ。TETSUさんは養子縁組しないの? そのほうが話が早いよね」
「いまさらあいつの苗字が変わるとキャリアに支障が出る」
「あ、考えたことはあったんだ」
「…………」
不愉快であることを隠さずに眉をひそめると「ごめんごめん」と至極軽い言葉が返ってくる。こいつのこういう軽さは、好きではないが流石に慣れた。
「私なんかにも、ささやかでも遺すものがあるなぁ、と思うと、たくさんあるTETSUさんは大変だね」
「俺にはもうなにも残っちゃいねぇよ」
手足と脳と、身体すべてを使って手にしてきた有象無象の報酬は、その大部分を整理した。持て余すような土地や建物、金品は金に形を変えて、寄付やら何やらにしたし、和久井譲介が手にできるようにきれいな形にしておいた。数多の研究も然るべき場所に片付け、多くはあの村の診療所に収蔵された。触法するような有象無象を紛れ込ませるには、あの村は都合が良すぎるくらいだ。神代一人ですら過去を掘られたら前科がつくところが特に良い。あの診療所が法的にクリーンになったのはここ最近の話でしかない。
歴史は堆積する。過去を覆い隠す。降り積もった雪みたいにやさしく溶けることはない。暴かれるときは周囲まるごとショベルカーで掘り返すような力技だ。その時はあの村の秘密も道連れだと思うと愉快な気がした。
俺はもうメスを持てない。
久しぶりに会いに行って開口一番そう言った時、ナマエは笑った。笑おうとして破顔して、結局最後は泣いた。
「泣くなよ、なにも死ぬんじゃねぇんだ」
はぐらかすために放った言葉はほとんど棒読みで、俺も嘘が下手になったもんだった。メスが握れなければ医者は廃業だ。ドクターTETSUは死ぬ。そうなれば真田徹郎も長生きできまい。生業を捨てた時の自分が想像できない。生きる限り続く業。生きるための業。それなしでの呼吸の仕方なんか忘れてしまった。
「譲介には言ったの?」
「馬鹿言うな。あいつの状況を考えろ」
アメリカで外国人が医師免許を取得するのは困難だ。そのカリキュラムを邪魔する訳にはいかない。あいつが来ようが来るまいがどのみち俺は長くは持つまい。あいつの人生は俺が死んでからのほうがずっと長い。
「じゃあK先生は? KEI先生は? 一也くんとか、ほかにも、えっと……」
「神代一人には、俺の研究を託した。他に俺が会うべき相手は居ない」
懇意にしている施設には挨拶を終えた。諸々の手続きはまだ途中だが、生前整理をするのであればこいつも無関係ではない。明確に他人に紹介できる間柄ではないし、一緒に暮らしたような期間も数えるほどしか無いが、人生最後の連れ合いのようなものがいるのであればこいつだろう。籍を入れてしまえばいくらかの手続きが楽になるのはわかっていたが、今更そんなこと言いだす気にもなれない。今になってそうするのであれば、もっとはやくその判断をすべきだったと思ってしまいそうだった。やりたいことだけやって生きてきたつもりだが案外とまだ後悔できることがあるらしい。
なにかしてほしいことがあるか尋ねると、ややあって彼女は「旅行に行こう」と言った。
「あんまり長湯しちゃだめだよ」
遅かったら見に来るからね。黙りこくってじっと湯に浸かる俺にそう言って、薄赤く火照らせた肌でナマエが風呂から出ていく。
ナマエの家に数日泊まっていくつかの残務を処理している時、ふいに「山と海どっちがいい?」と聞かれてとうとう俺はこいつに殺されるんだろうかと思いながら「海だな」と答えた。山に埋めるにはアンタじゃ力不足だろうと思ったが、どうやら旅行の行き先の選択肢だったらしい。
そうしてネット予約サービスを経由してリザーブされた旅館はN県の避暑地。ペット可の旅館。部屋と風呂と食事についての案内文を読み上げて、ナマエはちろりとこちらを見た。聞き慣れた県名に一抹の不穏を感じたが、場所自体は以前なにかの折に行きたがっていたところだ。オレの意向がまったく無視されているのはそう悪い気分ではない。行きたいところに行くべきだ。異を唱えないことを諾と解釈して、予約ボタンが押される。十数年越しのささやかな願いくらい結願してあげてもバチは当たるまい。この機会を逃せば次はないだろうし。
ドライブがてら愛車で行こうぜと申し出れば面食らった顔で「免許返納してないの?」と大いに高齢者扱いされこっちのほうこそ虚を突かれる。外科治療などの繊細な精密作業は心許なく晩節を汚すくらいならとリタイアを決めたが、運転はまだ現役だ、と、思う。
思えているうちに返納したほうがいいのかと多少不安になった。
「まだ大丈夫ならしなくていいよ。廃業決め込んだあとに趣味がなかったら老いるでしょ」
「老い……」
「TETSUさんは白馬の王子様ならぬハマーのオジサマだからねぇ」
そうしてはじまった旅行は拍子抜けするほど普通で、道中に急患も出ることなく平穏無事なものだった。天気も景色も良かったし、腑抜けた顔で猫と歩いてはすぐに疲れてベンチに座り込むのに、湖畔はちょうどよかった。そのうえ黙りこくっても相手は勝手に喋っているので気が楽だった。
宿帳に記入しているとこいつは勝手に「真田ナマエ」とペンを走らせ、悪趣味だなと少し睨むと「どうせ誰にもわかんないじゃん」としれっと流される。こうしていい歳の男女二人が同部屋で過ごすことに言い訳がいるのは煩わしい。確かに悪目立ちは避けたい。ただでさえ自分の容貌は人目を引くのだ。既婚のふりをしていると話を通しやすいことは多々有り、こいつとのその手のごっこ遊びは何度か経験があったが、活字でこうして見せつけられるとよくないラインを超えたような気がしてめまいがする。もっと危うい線引きをいくらでも反復横とびしてきたものなのだが。
何を隠そうこいつとの関係性で誤解されるもの1位が愛人、2位が夫婦、3位が不倫だ。ナマエのほうが俺の隣にいても違和感が薄くなるくらいに成熟したので、援助交際とは言われなくなって久しい。
部屋に戻ると、奴はかけていたドライヤーを止めて「なにー? もっと拭きなよ」とニヤニヤ嬉しそうだ。かなり大きめな音で、テレビはバラエティ番組を流している。騒がしいのをものともせず、キャットハウスの中で猫が眠っていた。ナマエはいそいそと俺を座らせてタオルでわしわしと水気を拭う。されるがままにしてていると、熱めの風をかけられる。指が黒い髪を撫でて、形を整えようと動く。地肌をかき混ぜて襟足に指を絡める。無抵抗を決めて目を閉じたままでいると、ぶわと顔の下から強い風が当たる。
ぱちりと目を開けると、相手はいつの前にか前に回っている。
「……なんだよ」
「いや前髪の根本をね」
仕上げとばかりに下から前髪をかきあげて、視界が開ける。相手は髪の毛ばかり見ているのでこちらから見上げても目が合わない。しばらく風と指で前髪を弄んてから満足したのか、視線がちらりとこちらに降りてくる。ほんの少しの沈黙、それを留めるように顎をひっつかんで、少し首を伸ばして唇に触れる。ゆっくりと唇を離す。呆けて開きっぱなしの下唇を擽るように食む。慌てたように手のひらがパシパシ肩を叩いた。
「違ったか?」
「そ、ゆ、わけではないけど……」
顔を赤くして目をそらす、予想外の初心は反応は久しぶりだからだろうか。もっと深いスキンシップもいくらでもしてきたはずなのに。
元々性欲が強い方ではない。病気と歳でもうほとんど枯れている。治す目的と壊す目的以外で人に触れたいと思うことなど無かった。この女に何年も何年もかけてそれ以外の触り方を教え込まされるまでは。
「じゃあいいだろォ」
眼の前に膝立ちしている女の足腰を、解いたあぐらで引き寄せる。前述の通り性欲はカラカラにフリーズドライされているので夕食前からしっぽり行きたいわけではない。治療と破壊以外で好きにしていい身体に触れたいだけだ。そのコンセンサスはとっくの昔に取れている。もたれ掛かって差し出すように晒されるうなじに触れると、 襟足はまだ湿っていた。
「ちゃんと乾かせ」
俺にそうする前によ。ドライヤーのスイッチを入れて、首筋に張り付く髪の毛を辿って肌から離す。
強い風の音、そのせいかぐっと身体を近づけたナマエが耳元で強く声を上げる。少しうるさいくらいに。
「本当にもうお医者さん辞めるの? 手術するだけが医者の仕事じゃない、んだよね」
「……うるせぇな、お前にゃ関係ない話だ」
「私になくても譲介にはある」
顔は見えないままだが予想できる。仕方のない人だなぁ、という眉をハの字に寄せて少し笑ったいつもの顔だろう。
「あなたの大事な養い子との約束を反故にさせるわけにもいかないし」
ごめんね、と。小さくつぶやき、ぬるい体温が離れる。
「譲介っ!!」
突然叫んだのはその養い子の名前だった。バタン!と騒がしい音とともにぐるりと視界が反転し、畳に身体が叩きつけられる。強い力でぐいとうつ伏せに組み伏せられて、抵抗しようとした両腕はなにかに掴まれて動けない。
「クソっ!」
俺はもうこの力には抵抗できない。病と加齢が「こいつら」に勝てるわけがなかった。悪態をつく俺に譲介と一也は少し怯んだが、しかし力はしっかりと加えられたままだった。見上げた先に神代一人が佇んでいて、ナマエは俺の顔をしゃがんで覗き込んだ。
「てめぇ、謀ったな!」
「……当たり前でしょ、私がみすみすTETSUさんを死なせると思う?」
あと譲介に頼まれてたからさ、ごめんね。と笑っている顔に申し訳無さなんて1ミリもない。
「俺より譲介の言うこと聞くのかよ」
「だってTETSUの自己判断って大体間違いじゃない」
ばっさりと切り捨てられて絶句する。大体間違いってとんでもないこと言いやがって。
「それに、二度と間違えないって決めてる」
十数年越しにリベンジできる機会があるとは思わなかったけどね、と。そういうわりに少し笑って眉尻を下げて、そうだこれが本物の「しょうがない人だね」って顔だ。
「クッ……俺も落ちたもんだな。お前ら程度の殺気に気づかねぇなんてよ」
「殺気ではないからだ」
俺の体重を床に押さえつける一也が言う。また少しあいつに似た気がする。そうだあいつも、あの男も、治療が必要ならば女であろうとふん縛って手術台に載せる男だった。強く瞳を眇めた顔は、今にもミランダ警告でも発しそうだ。
「おいおい、こんな老いぼれどうすんだ。どうしようもねぇぞ」
力では一切勝てなくなっていることを愕然としつつ、ショックを隠すように軽口を叩く。「まずは検査と問診、それからアセスメント作成と」神代一人が相変わらず面白みもなく堅苦しく答える。「引っ越しだ」と最後にズレた言葉を付け加えて。
「引っ越し?」
不意を突かれて聞き返す。ぐいと袖がまくられて、どうにか首を回すと譲介が俺の浴衣を捲っていた。手には注射器、舌打ちをする。俺の身体情報なんかとっくに共有され済みってことが。これだから医師じゃない素人は恐ろしい。良し悪しなんて知ったこっちゃないのだ。目的のためなら手段など選ばない。ナマエは本当に少しの罪悪感もない顔で、さもこれが正しいことのように言った。
「プロはもっと違うものを使うんでしょ?」
ほんのささやかなちくりとした感触がゴムで締め付けられた腕に侵入する。
「うまくなったもんだね」
注射から薬が効くまでは少しの時間がある。苛立ち紛れに悪態をつくと、譲介は苦虫を噛み潰したような、顔をしたあと、ふっと笑った。眉を寄せたまま。しょうがないな、というように。そんな所ばかりナマエに似るな。
「親のラブシーン見せられるのってこういう気分なのかもな」
「家を買ったの」
と言っても、空き家活用の関係で結構安くすんだんだよ。と。
目が覚めたら村の診療所だった。定期更新されている新型の機材で同意も何もなく身体中調べられた俺を最初に出迎えたのは、爽やかな果実の香りだった。横でりんごを剥いていたナマエが目を覚ました俺に「おはよ」と笑いかける。そのまま、きれいに切ったりんごをぱくりと食べた。オレのじゃないのかよ。
「手入れは居るけど、TETSUさん車の運転できるくらいには元気なんでしょ」
「……譲介を巻き込みやがったな」
「K先生に託してとんぼ返りしてったよ。しばらくは大丈夫みたいだし」
次はクリスマスあたりにでも『帰ってくる』よ。果汁で濡れた手を布巾で拭う。
「詳しい数値はよくわかんないけどね。譲介がアメリカ戻るってことならまぁしばらくは大丈夫なんでしょ」
「…………」
「ってことで新居は、かつてのライバルの息子と関係者つき、たまに帰省してくる可愛いアラサー男も。あとはまぁ、ねこちゃんと、甲斐甲斐しい内縁の妻も添えて」
どう? 悪くないでしょ。そう言う声は少し震えて硬質で、ここまでしてなおこの女は不安なのだろう。
「気に食わねぇな」
だからそんな言葉にびくと震えて、動揺した瞳がこちらに向けられる。情けない顔。
「そこまですんなら入籍くれェしてみろ」
「……私とTETSUさんの間に証拠はないからさ」
未来では私達の関係を証明するものってなにもないね。何故か嬉しそうに瞳を細めて女はそう言った。
「お前は本当にイイ女だな」
もっと抱いとけばよかったぜ。なんて言えば、サイテー!と小突かれた。一生この情けない顔見て過ごすなら、まぁ、悪くない。