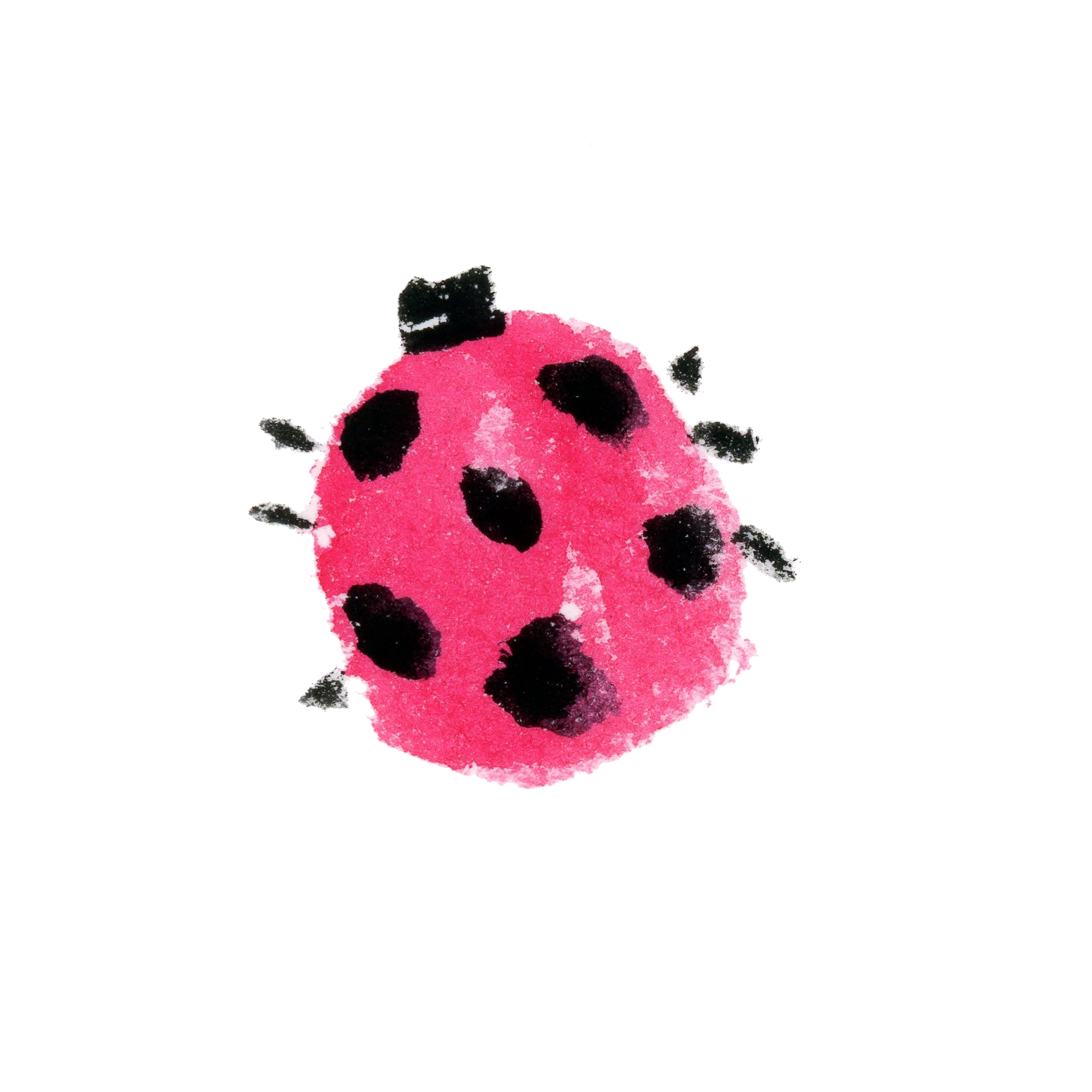
とってもよくお似合いで
サイン会というものを何度かやった。
初開催は、二冊目を出版するときだった。退職したとは言えほぼOLメンタルで素人同然、どころか出勤して強制的に人と接するような機会が減ったことで誰かと長時間話すこともなくなり、マイナスからのスタートといった具合であった。小規模な催しだからと奮起してしどろもどろでなんとかこなしたものだ。過去の私はいつも頑張ってて偉い。
年数と回数を重ねて、それなりに場数と経験を積み、いまではあまり緊張もせずに人前に立てるようになった。同業の中では外部への露出は多いほうだ。中堅、と言われる立場なのだろう。いまの業務形態は向いている。天職だと思う。
年齢もキャリアも重ねると、それなりのものを期待されるようになる。場慣れした様子で堂々と振る舞い、進行に添ったトークをそこそこやって、次に自分に必要なもの、求められているものはなんだろか。
「格、ですかね」
「か、カク……」
付き合いの長い編集者は、さらりと「格式です」と言った。
「作家先生っぽい格、先生あまりありませんからね」
「そういうのって勝手に仕上がってこないものかなぁ」
「そういう人もいますけど、先生はそうじゃないと思います」
「そうですかね……そうかもね……」
「親しみやすさも大事ですがね。見た目から入ったらどうです? 着物とか」
「文豪っぽい! ……文豪っぽすぎない?」
「すぎるくらいがちょうどいいですよ、こういうの」
そんなものかなぁと首をかしげる。とはいえ彼女はデビュー時からお世話になっている辣腕編集者である。彼女の言うことにゃ一理どころか百理あるだろう。千里の道も一歩から。形から入るのも悪くない。
買うほどじゃないよな、そして着付けとかできないなと、自宅でパソコンを開く。レンタルできて、着付けもできるところ……。成人式の時はKEI先生にお世話になった。「借りてくれないと、父があなた用に仕立ててしまうわ。私はそれもいいと思うけれど」という殺し文句で、しぶる私に半ば強引に自分のを貸してくれたから、自分で手配するのははじめてだ。今回も先生に頼ってしまうもの手だけど、自分から言い出すのは図々しい気がする。言えば先生は快く協力してくれるだろうけど。
うんうん唸っていると、ズンと隣に重りが乗ってソファが揺れる。殆ど肩に顎を乗せているような距離で、男は「仕事か?」と問いかけた。
「うん、今度のサイン会、着物をお勧めされてて」
「ふぅん」
チコチコとスクロールしている私にTETSUは気のない返事をする。
「でもよくわかんないね。やっぱりKEI先生に頼もうかな」
「一枚くらい自分のが無ぇのか。訪問着とか」
「無いよ。なに? 種類すらわかんない」
「目の前の機械で調べろ。着付けは?」
「できない。レンタルと着付け全部込みでできるとこ、どっか知り合いとか居たりする?」
私の肩に鋭い顎で負荷をかけてくるこの男は、そういえばその手の伝手が結構あるはずだ。私に教えていい部類かどうかは彼が勝手に判断してくれるだろう。TETSUは「そうさなぁ」と少し考えるそぶりをした。
「……ああ、一個あるな。着付けは俺ができる」
「えっ⁉ TETSUさん着付けとかできるの⁉ ……なんかやらしー……」
「やらしいのはお前だろ。おふくろに教わっただけだ」
なるほど、年代的にはそういう世代か。一昔前は着物を普段着にしてる人も決して珍しくなかった。私より幾分年かさの男はその時代の気配を色濃く残している。
畳紙から現れた色彩に、感動よりも困惑が勝った。美しかった。深い色合いで染められた鮮やかな花々、品格とやらに色があったらこんな感じだろう。下前には小さく落款が捺されている。
「え? これほんとに私が借りていいやつ?」
私の髪を簡単にまとめあげて、露になった肩に色留袖をかけて、TETSUは「ふうん。70点くれぇだな。まぁ、10年もすりゃ似合うだろ」と鼻を鳴らした。
「遠慮すんじゃねぇよ。どうせもう持ち主はいねぇんだ」
「そ、それ怖い話? 曰くがある?」
「あるかもな。なんせこれを仕立てた女は、夫も子供も犯罪者だ」
「反社組織系?」
「組織じゃねぇがな」
珍しい上目遣いで、膝を曲げて襟を整えている男は私を見た。そして目をそらす。くるりと後ろを向かされて、従順にそれに従う。
「そういや昔おふくろが」
聞いたことない声音だった。驚いて首を回して振り向こうとしたけど「動くな」という一言だけで身体が固まる。
「兄貴に言ってたな、嫁になるやつにやるってよ」
うちにゃ女兄弟がいなかったからな、とすっとぼけたみたいな声。この人は年々演技が下手になるね。
「お兄さんいたんだね」
「もう死んだがな」
あの真田医院の柱には、2つの名前が刻まれていた。タケシ。テツロウ。それぞれが誰の名前かなんて、うっすらわかるけれども気づかないふりをしている。果たして過去になにがあったかなんて、調べようとすれば簡単にわかるのだろうけれど、過ぎたことを気にしても意味などないのは彼も私もよく知っている。だからお互い過去のことなんて上澄みを掬うくらいしか口にしない。
墓も建物も片づけたのに、お母さんの形見をどんな気持ちでどこに置いていたのかなんて、聞いても仕方ない。
「思ったより悪くないな」
苦しいギブギブ、と私を呻かせながら帯を締めて、サナダテツロウ(仮)は目を細めた。鏡の中には、加賀友禅に身を包んだ女性が立っている。正直言って割と似合っていた。彼の言う通り、あと10年もすればまるで私のために誂えのかってほどしっくり来るだろう。
「……やっぱり、そんな大事なもの借りられないよ」
「貸すんじゃねぇ、やるんだよ」
「な、尚更!」
「お前が受け取らなきゃ今度こそ捨てるしかねぇな」
殆ど脅しみたいなことを平気で吐き捨てて、長い指が器用に髪の毛を整えなおす。なんで私の周囲はみんな好意に脅しを混ぜるのか。
「そんなの……」
「……これはお前に似合うよ」
鏡越しの視線が私のそれと絡む。似合う、ともう一度念押しされては、もう何も言えない。
「これを着る時は、TETSUさんが着付けてね」
不履行になると理解しながら付け足した「ずっと」という言葉に、かつての良き息子である悪人は唇の端を持ち上げた。