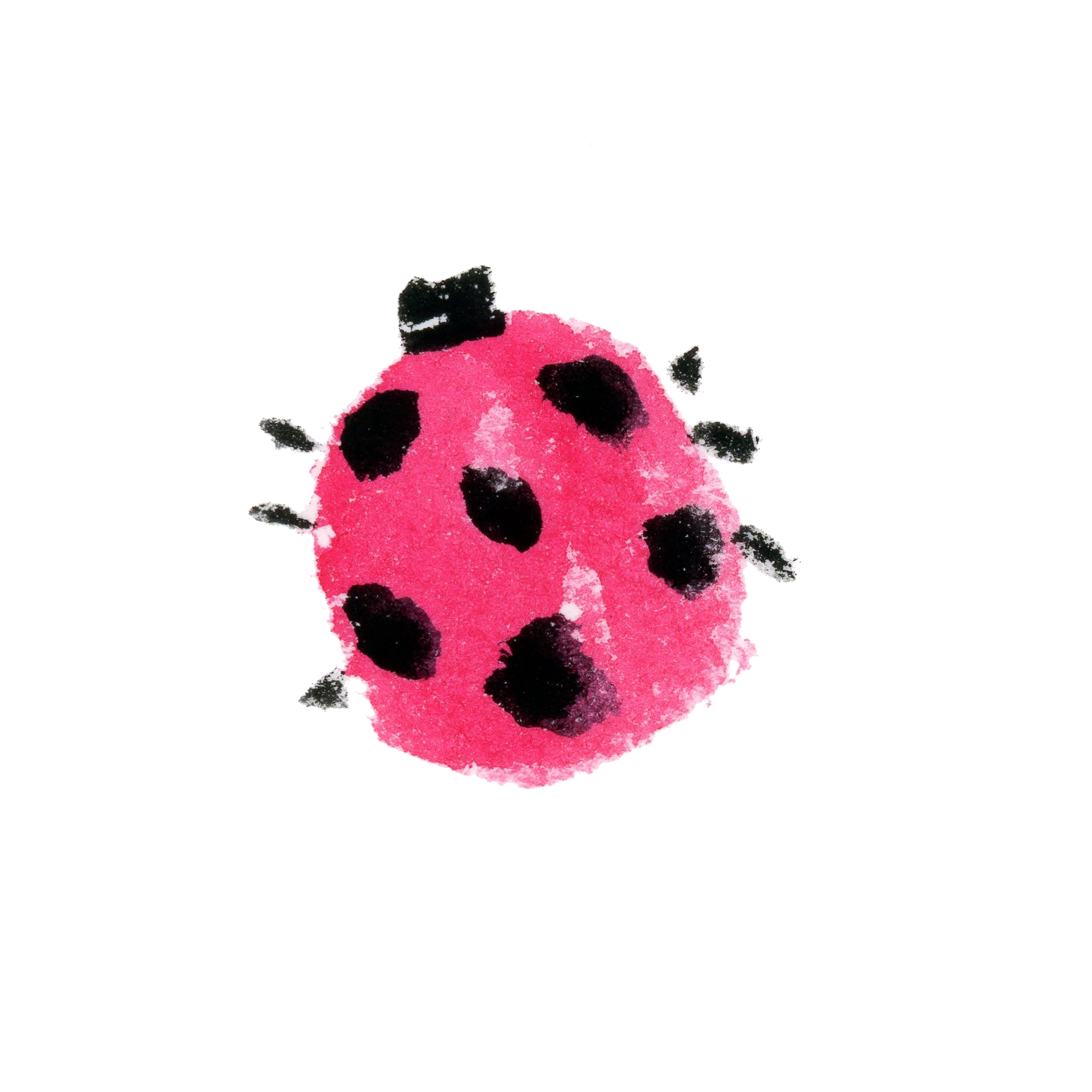
4-3
コトンと小さな音がした。雨音混じりでもそれがわかるのは、家のなかとそとのはざま、ちょうど玄関から聞こえたから。郵便受けになにか入った音だ。こんな夜中に。
ちょうどレム睡眠のさなかだったのか、鼓膜の震えはそのまま脳を覚醒させた。ぱちとまぶたが開く。
郵便受けには、ふたつ。随分前から手放していた懐かしい合鍵と、ぽたりぽたりと雨粒の落ちた跡がある封筒だった。少し厚く、小物が入っているような膨らみもある。 それを開封する前に、ドアを開ける。
通りにまで出ると、街灯の隙間には男が居た。杖だけ持って傘は刺さず、ぬるい雨の中を背中を丸めて歩く男。
「ドクターTETSUっ!?」
記憶にあるよりも足取りが重くて、一瞬良く似た別人にも思えた。そんなわけないのに。あれ、この人めちゃくちゃ弱ってない? あの廃病院のとき以上に。私が知ってる時の彼なら、私が扉を開けるまでに去ることなんてわけなかったはずだ。
けれど男は、濡れたアスファルトをほとんど引きずるようにして足を動かしていた。
「なんでずぶ濡れ……車は……」
「……エンジン音が五月蝿くて近所迷惑だってお前が言ったんだろ」
振り返らない。振り返るのも億劫なのか、顔も見たくないのか。両方かな。
ぱしゃぱしゃと雨を跳ね上げながら小走りで追いつくのは簡単だった。もし会えたらと何度も考えていたいくつもの選択肢、現実はそのどれとも違った。
「来なよ……雨だよ」
声をかけても立ち止まらない。ゆっくりとした歩みを、追従するしか出来ない。傘を持ってくればよかった。
「コーヒーくらい出すからさ」
引き止められるすべてのバリエーションを使ったけど、そもそもバリエが少ない!
そう、この人と全然人の話聞かないんだよな。だからこんなことになってんだけど。譲介のことも私のことも、こっちが思うよりもずっと熟慮してるのはわかってる。ああもうでかくていかつくて毎度奇跡みたいなドラテクで狭いパーキングに押し込まれてるハマーH2にたどり着いちゃうよ。パーキングの入口でTETSUの前に回ると、男はやっと止まった。私ももう随分濡れてしまったけど、この人も病人のくせに濡れ鼠だ。風邪引くよ肺炎になるよ、と思ったけどそんなことももうどうでもいいんだね。じゃあなにがどうでもよくないの? 譲介とKか。
「行ってほしくない……」
雨の中男女が揉めてるの月九じゃんって思って脳の何処かが冷笑した。おまけに涙まで出てきた。ベタな恋愛ドラマの世界観にTETSUの居場所って無くない? お人形遊びに乱入してくる怪獣ソフビみたいだね。
「ね、お願い…。このままTETSUさんとお別れなんて嫌だよ……」
私の安さに呆れたのか流石にいたたまれないのか、TETSUは立ち竦んだ。どうしていいかわからなかったんだろう。医学の症例には詳しくて、薬学にも心理学にも詳しいけど、自分にそれを向けられたら困り果ててしまうのがこの人の弱点だった。
「……見るたび泣いてんじゃねぇか、お前」
「TETSUさんのせいじゃん……」
それ以外だと割とニコニコ呑気に生きてられるんだよ私は。TETSUさんに出会いさえしなかったらね。そんな人生ほんと最低。
足取りは重く遅く、身体がきついのか、もしくはほんとにうちに来たくないのかもしれない。たっぷり水を吸った男は、前髪の先からぽたぽたと水滴を垂らしたまま玄関に立ち尽くしている。いくらぬるい雨だとしても冷えそうだ。
「風邪引くよ」
タオルを押し付けてコートに触れる。水気で重くて冷たいそれをひっぺがしたかったけど、それより先に男の手が延びて私の手首を掴んだ。
唇が触れるまでの間に少しだけ間があったけど、彼も私もその間に身じろぎひとつしなかったから、冷たい唇同士が触れるのになんの邪魔も入らなかった。
「っ……」
この男の口づけはいつも冷えきっている。寂しいのを隠したくて触れてくるのを、彼自身も気づいてないからかも。
ちゅ、ちゅ、と角度を変えて吸い付かれて、大きな手のひらが無遠慮に、でも柔らかく身体に触れる。人に触れるときにいつもほんの少しの労りを持つのは、稼業で染み付いた気遣いだろう。
こんなに冷え切っているのに手だけは温かい。それが服の裾から腰を撫でたので、慌てて肩を叩いて離れる。
「はっ……だめ……、だから……」
背中を丸めた姿は、拒絶されたことで落ち込んでるようにも見えた。私がそういうふうに見たかっただけかもしれない。この人背が高いせいかもともとちょっと猫背だしな。寂しそうな背中をしてるなっていつも思ってた。……それも私がそう見たかっただけか。
「そんなつもりで脱がせたかったわけじゃない……」
この人は私のことどういうふうに見えてるのだろう。いつもちょっとがっついていると思われてるのは、見せかけじゃなくて事実だから、こういうときすぐに即物的な解釈をされるのは仕方ないか。この人別にセックス好きじゃなさそうなのに。私のこともきっと好きってわけじゃなくて、たぶん同情か懇情なのに。
「風邪ひくから、はやく、お風呂……」
すぐ傍のユニットバスに押し込める。我が家ながらTETSUには少し窮屈すぎる激狭のお風呂だ。浴室内を少しでも早く温めたくてシャワーからお湯を出してやって、その間にお茶でも入れようと背を向けると、ぬっと伸びてきた腕が私を浴室へ引き戻す。何度も言うけど本当に狭いお風呂で、二人で居るとほとんど身動きが取れない。
「テ、んっ!?」
壁に押し付けられて、背中をもっと丸めたTETSUが噛み付くみたいに唇を合わせる。熱いシャワーが二人の上に降り注いで、暴力的なまでに熱を与える。
「は、ふ……っ……」
「……、……」
どうしたんだろう、どうしたいんだろうこの人は。ずっと黙ったまま、なに考えてるのかは相変わらずわからない。なんでこんなになるまで寂しいのに、譲介を手放したんだろうね。これだけお互い離れがたく思っているのに。あんなに譲介に懐かれて好かれて求められて、まだそれをわかっていないなんて。
やはり病状は思わしくないのだろう。寄りかかる体重はどろりと重い。慣れた加齢臭混じりの体臭に混じる匂いは、あぁこれが死臭というやつか。
今回もあの廃墟の夜と同じように、自罰感情で私に触れているのだろうか。
なにひとつ気持ちがわからなくても、触れ合えば熱と匂いと重みだけは伝わる。それだけでも、そんなものだけでも欲しがる私はやはりTETSUの思う通りの浅ましい人間だ。亡くなってしまったKにもまだ子供である譲介にもできない、本物のズルってやつだった。
雰囲気を壊すような話ではあるが、こんな病状でこんな精神状態の人が勃つわけもなく。こちらとしてもそんな人からこれ以上欲張るわけもなく。一通り触れ合ったあとは湯船にお湯をドバドバ張りながら残りの服を引っ剥がした。アームカバーだけは「いい」と普通に拒否られる。温もって少し元気になったみたいだった。寒いと必要以上に落ち込むよね。
「100数えるまで出ちゃ駄目だから」
それなりにこちらもびしょ濡れになったため、濡れて窮屈な服を脱ぎながらそう告げる。これ一度まとめて洗うしか無いかな。TETSUのコートって手洗いした方がいいかな。
着替えて濡れた髪を乾かして、夕食をあたため直しながらお茶を煎れる。
100数えたかどうかは知らないけどそれなりにほかほかになった闇医者が、バスタオル一枚で局部を隠した情けない姿のままのそのそと風呂場から出てきたので、しまいこんでいた男物の下着と3Lのスウェットを渡す。黙って着ていた。
マグカップも髭剃りもみんなまだうちにあるのだから我ながら未練がましい。
「意外だな」
と告げられたのは、ものを大切にする精神のことではなかった。「もっとキレるのかと思ってたぜ」とスウェット姿のしょぼくれたオジサンは呟く。あっためなおした味噌汁でHPが少し回復したみたいだ。
「私もそう思って……でも多分会うと頭に血が上っちゃうから、あらかじめ原稿用紙に書いてた……」
色々言いたいこと言いたかったことをつめこんだら超短編くらいの長さにはなってしまった。究極の私小説だ。譲介の時と違って送る場所がわからなくていつまでも手元に残っていた。折りたたんだ原稿用紙を取り出すとTETSUから心底呆れた目を向けられる。小切手1枚で縁を切ろうとした男とどっちがマシなんだろうね。
「でも全部もういいよ、いやよくはないけど……あとで読んでてね……いややっぱ読まないで……」
複雑な感情が波のように寄せては返す。「TETSUさんに任せる……」と三つ折りにした原稿用紙をテーブルに置いた。その上に合鍵を乗せる。
私の手元には、TETSUが用意した封筒だけが残る。
「これはいらねぇ」
「…………」
合鍵が、私の方へ戻される。あからさまに傷ついた顔をしてしまったのだろう。TETSUは「お前が悪いんじゃねぇ」と意外なことに私を慮った。
「……譲介を手放した」
「……うん」
「ドクターKなら、あいつを育て直せるはずだ」
「無責任なの。わかってるよね」
「あいつが受験に失敗したのは、仕方ねぇ。不運なだけだ。だがいま俺が倒れたら、あいつは未成熟な浪人生のまま俺の後始末をするだけの人生になる」
「…………そんなに悪いんだね」
「悪いな。見りゃわかんだろ」
そうだね。見るだけでわかる。触れたからもっと分かる。それくらいに彼はいま病状が悪い。痩せて頬は痩けて、あんなにつやつやだった肌も年相応にハリがない。瞳はどろりと黄色く濁って、かつてはちょうどよくゆったりしていたスウェットも不格好に余っている。それでも生来の体質なのか大柄で肉厚なことには変わりなく、もっと元気な頃から何度も裸を見てきた私のような人間じゃなければ、病人とは気づかないかもしれない。いや無理かな、肌がかなり土気色になってるし。
「……もっと時間がありゃよかったんだがな」
クク、と自嘲気味に笑う。自分の末路に、残された蝋燭の長さに気づいてから、彼はずっと時間に追われている。
「……諦めたわけじゃあねェ。ただ、明日をも知れねぇ身でこのままあいつを手元に置くほうがずっと無責任だ」
クソ、こんな話するつもりじゃあなかったんだよ。と男は気まずそうに頭を掻いた。だったら最初っから引き取るのに無理があったんだよ、なんてことはとても言えない。あの時確かに譲介にはTETSUが必要で、そうでなければ生きられなかったのだから。それくらいはわかる。
「でも、置き去りにするなんてひどい」
「譲介はとっとと俺に愛想を尽かすべきなんだよ、お前みたいにな」
「っ……」
傷ついて被害者ぶるのはお門違いだ。そりゃあんなキレ方して姿を消したらTETSUがそう思うのも仕方ない。
「ごめんなさい……」
しおらしく素直に頭を下げる。しゅんとしながら謝る様は我ながら子供の喧嘩みたいだ。
「合わせる顔がなくて……一番無責任なのは私だよね」
「……別に、お前が謝ることじゃねえ」
私の殊勝な態度を前にして「しおらしくすんなよ調子狂うなァ」とTETSUは悪態をつく。いままでならそれに私が軽く怒る素振りをして話がまとまるけど、今回は子供も巻き込んでしまったのだ。簡単に終わらせていい話ではない。
「俺はしばらく消えることとする。片付けるもんも山程あるしな」
「その間うちにいてもいいんだよ」
「馬鹿言うんじゃないよ。お前、俺がいるってことを譲介に隠し通せるのかよ」
「それは……」
譲介の手が届く範囲にTETSUが居ては意味がない。TETSUがそばにいる限り譲介はTETSUに寄り添いたがるだろう。せっかくK先生のもとで再起しようと頑張っているところにそんな事態、洒落にならない。
私は譲介がまともな人間関係を築くためにK先生が任命してくれた練習台だ。傷つけてもやりなおしをできる、医療従事者じゃない一番近い他人。急に距離を取るのも変だし、それこそ昔の男(……なのか?)にかまけて今大切にすべき子供から離れるのは不誠実で無責任だ。
「でも、これは持っててほしい、です……」
しつこいのはわかってるけど、二人の関係性にあるものは究極これだけだった。この男は私の部屋の合鍵を持っているのだという、ほんの一抹の希望だ。おかげで全然引っ越せないんだけど。
「……ならそいつはちゃんと受け取るんだな」
懇願された男は、私の手前に置きっぱなしの封筒を指差す。何が入っているのかはまだしらない。よくある茶色い角形2号。
「これ、なんなの?」
「いいから、まずは約束しろ。絶対に受けとれ」
「……わかった」
手の内に封筒を取る。男がテーブルの上の合金を握った。最初からこれが目的だったのかもしれない。こうして部屋に上がってしまった以上は。対面してしまったからには。
「…………」
開封すると、まずは通帳が目に飛び込んできた。私名義だ。印鑑もある。一体どうやって作ったのかなんて聞くだけ野暮だ。
「な、ん、なの!?」
結局キレかけた声を出してしまった。しおらしタイム終了である。TETSUは私と居ると調子が狂うらしいが、私だってTETSUといると常に情緒と常識とテンションがめちゃくちゃになる。恋は人を狂わせるとかそういうナイーブなやつじゃなくて。
「私こういうのイヤっていったよね!?」
印字された馬鹿みたいな数字を見て素っ頓狂な声を上げる私に、TETSUはやっぱりなって顔して笑った。
「それは報酬だ。先払いのな」
良く見ろ、と、通帳の他にファイリングされた書類がいくつか入っている。取り出すとそれにはいくつかの連絡先やなんらかの情報が記されていた。一番うしろには公正証書の正本。甲の部分には知らないはずだけどまあ大方予想はついていたな、という名前が、乙の部分にはわたしの名前が記されている。それは、真田徹郎が死んだあとの諸々の手続きの一部を私に委託するものであった。予想通り真田徹郎って名前だったんだ。こんな漢字なのか。そんな程度の関係性である私の名前がここに並んで記されているのはおかしい。
「どうやってこれ……」
こんなこと事後承諾でしていいわけないしできるわけないのに。でもそんなの問うだけ無駄である。それよりも「なぜ」のほうが大事だった。
「どうしてこんな……」
「それも聞くな」
男はちゃりんと、手の中で大げさに金属音を鳴らした。
「俺が死んだら……まぁ、死んだってわかった時は、そこに連絡しろ。いくつかの面倒はかけるだろうが、大方の話はついてる」
「し、死なないでよ……」
「死ぬんだよ、いつかは」
この人があの日寂しさで自滅しかけてた私のところに来たのは、そしてあの夜譲介を見つけたのは、そもそもが自分の人生を仕舞うための一環だった。紆余曲折あって本人としても思ったより時間がかかっただろうが。合間で子供を拾ったりしてたらそりゃあ寄り道は多いだろう。長い長い終活だ。
「元々こうするつもりだったさ。まぁ、いまはあいつが居るからな。悪ぃが足のつかねぇもんの殆どは譲介にやるからな」
「あなたのものだから、それは、好きにすればいいんだけどさ……」
まさかこの人の名前と私の名前が並んでる文書なんて手に入ると思わなかったのでひどく動揺しているのだ。一体何を考えているのか。
なにを考えて、考えないでいてくれたのだろう。
「私が朝これだけを見た時どんな気持ちになるか、少しは考えてよ……」
怒ってやろうと思ったけど無理だったのは、涙混じりの自分の声が情けなかったこととか、顔をそらして前髪で顔を隠して口元だけ笑った男に無性に寂しくなったこととか、そういうのが全部混じり合ってどうしようもなくなったからだ。どういう気持ちになるべきかわからなかった。模範解答がほしい。こんな時ってどういう気持ちでいればいいのかなKEI先生。
なにひとつ解決はしていない。この男は重い病気で、子供は傷ついたままで、私は愚かで無様で不誠実だ。それなのにどうしてこの人はいつも、強張った手で拙い優しさを繕ってくれるのだろうか。私が1番欲しいものは多分くれないのに、こうしてどこかのなにかの小さな場所を明け渡してくれるのか。この人の欲しいものをなにひとつ渡せないままの私に。
「…………医者じゃなくなっても生きてくれる……?」
「俺が足も手も使い物にならなくなってなんでもねぇただの男になったら、その時はこの身体くらいくれてやってもいい」
「……ふざけないで、私は草臥れた男の回収先じゃない」
「ククク……そうさな」
「四の五の言わずに譲介のために生きてよ」
分厚くて熱くてかさついた指がヘビみたいに静かに伸びて、頬に触れる。親指が唇にとんと柔らかく乗って、男はこれ以上わたしがなにかいらないことを言わないように誤魔化した。
以前よりも誤魔化し方が下手になってたけど。