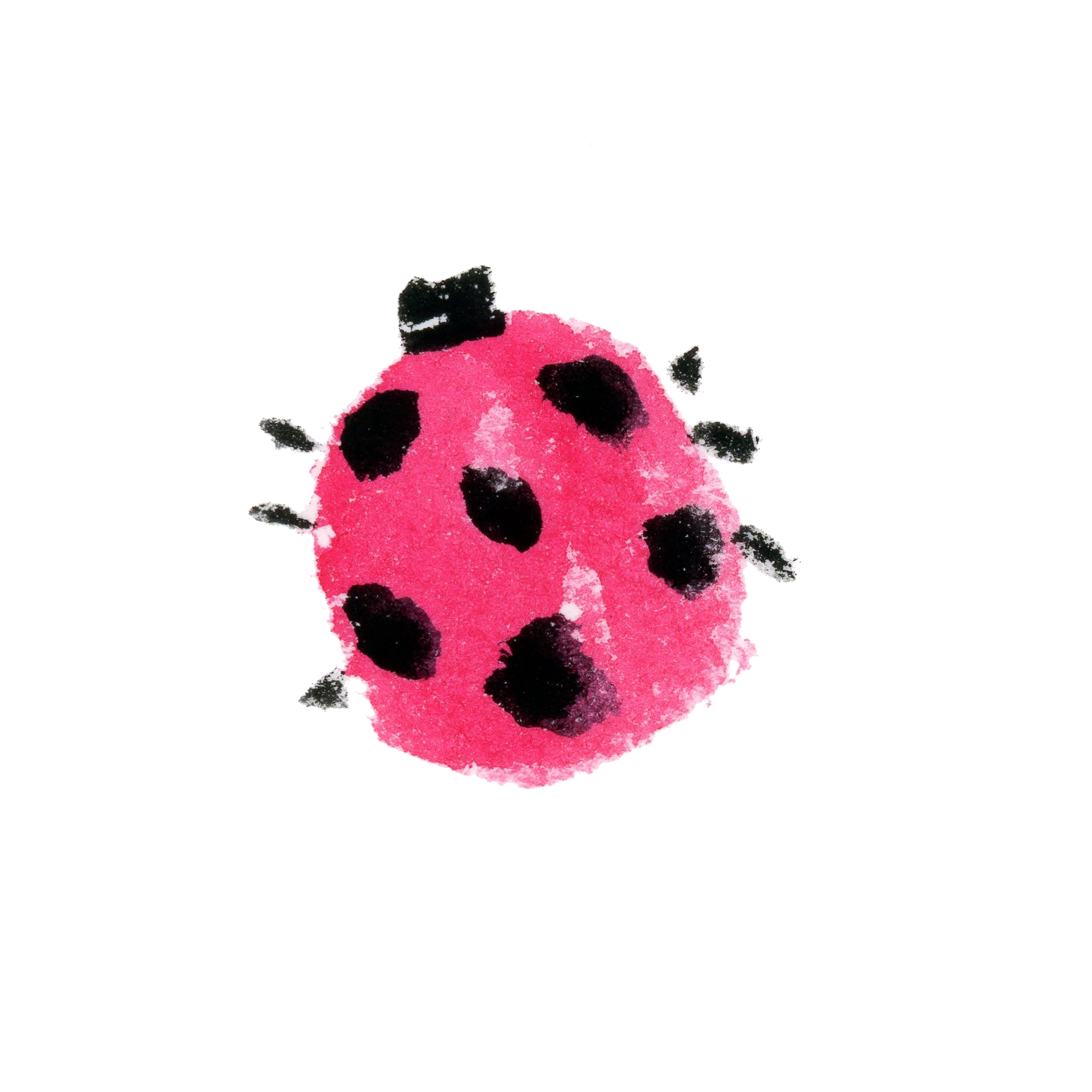
4-1
オチとしては今回も対話が足りなかったなって思う。結構頑張ったんだけど、コミュニケーションって満ち足りることはないんだね。
まさか転校と同時に引っ越すとは。
「い、言ってよ!」
普通にそれくらいは報連相してくれてよくないかな。私の勢いに対し、都内から一つ隣県に引っ越した男はしれっとしたものだ。
「言ったらどうなったんだよ」
「引っ越しとか手伝ったかな」
「業者に頼んだからいらん」
闇の引越し業者に依頼したのかな。
突然「迎えに行く」と言われて普段と同じ流れでやって来たハマーに乗せられて、そのまま高速に乗ったもんだから本当にびっくりした。今回のマンションには手術室はなかった。引き続き都内のマンションのほうも使うらしい。
隣県となると遠いってほどじゃないけど今まで程頻繁には遊びに行けない。それよりもN県に近づいたことが少し気になったけど、本当に小さな違和感だったし、そのまま仕事が忙しくなってきたので問いただすタイミングを失ってしまった。なぜかTETSUと距離があるほど私の仕事はうまくいくのだ。
高2にもなると譲介も一人暮らし+α(むしろ+Tか)の家事の回し方をかなりわかってきてたし「あんた最近忙しいからこっち構ってる場合じゃないだろ」とプチ説教までしてくる始末だ。「肌荒れしてますよビタミン足りてないんじゃないですか」とレモンティーを出された。新しいツンデレだ。
「でも、TETSUさんの助手と学校の勉強と家のこととって、大変じゃないの?」
「別に。僕は自分の世話くらいできる」
あんたは出来ないだろ、とTETSUからなにか聞いたらしい少年は生意気を言った。ぐうの音も出ない。
「ちゃんと寝るんだよ、ごはん食べるんだよ」
「あんたが言うなよ」
本気の心配だったけどいまいち伝わっていない。むしろ自己管理も出来ないと言いたいのかと突っかかってきそうな気迫だ。やっぱり疲れて見える。余裕がない。
帰り際、玄関横の水槽を見て首を傾げる。
「あれ?」
メダカの水槽は、去年地域の秋祭りで掬ってきたのを都内のアパートに持ち込んでいたものだ。闇の引越し業者がちゃんと連れてきてくれたらしい。でも、もっと居なかったっけ。環境が変わったから弱っちゃったのだろうか。

そうして1年はあっという間に過ぎたのだが、この年譲介に会えたことは殆どなかった。1年まるまるあったのに、年度途中から出会ったはずの去年に比べると格段に少ない。TETSUが言うには元気らしいし、たまに会うときも―――元気、なのかな。あれは。元々いっぱいいっぱいに張り詰めたガラスの糸みたいな子だったけど。TETSUの影響で露悪的な振る舞いが目立ちだしたから分かりづらい。反抗期ってだけならいいんだけど。
「また引越しするの!?」
「そうだ」
「そんなコロコロ……譲介にも一応友だちとかいるんじゃないの?」
春からは高校3年生。大事な受験シーズンだ。そんな折に住まいも学校もがらりと変えるなんて、よほどの事態だろう。闇医者はともかく譲介はそこそこいい学校に通う普通の高校生だ。連れ回す理由がない。
こうなるからお前にゃ事前に言わねぇんだよ、とTETSUは悪態をついた。最近使い出した杖を片手にしているので、私は両手にマグカップを持って、勝手知ったるとはとても言えないマンションのダイニングテーブルに置く。
「あいつに一番必要なものは何だと思う?」
「心のよりどころ? 安全基地?」
「……野望と、その実現だ」
いい線言ってると思ったけど言外に却下された。野望って、何。およそ日常生活では聞かない言葉だった。世界征服以外に野望としてふさわしい目標なんてあるのだろうか。譲介に必要なのはTETSUだ。TETSUからの承認だ。この人が医者になることを求めたらそりゃ譲介はその高みに向かうだろう。この人も、他人に分け与えられるのはそれしかない。二人が一緒にいる以上医療の道に進むのは必然だ。解答は正しいけど計算式が違う。その大いなる誤算に二人は気づかない。
こういう時のTETSUは「こいつに言ったところでなァ」みたいなむかつく態度を一切隠さないし私の話に耳も貸さない。私だけ蚊帳の外にいるのは十分わかってるのに、更に突き放すように。
「あいつの原動力は生い立ちへの復讐だ。物心ついたときから親に捨てられ、施設にも恵まれず福祉にも冷遇された。社会からは力による支配のみを与えられ―――」
ぐ、と持っている杖が軋んだ。怒りではない、悲しみでもない、純粋なエネルギーの駆動を身体の中で持て余すように、TETSUは歯をむき出しにして顔を歪める。笑顔は獣の威嚇だ。
「力に潰されねぇためには、自分が力で潰す側になる。それだけだ」
「でも、いまのままでも……それか、東京に戻ったっていいはずなのに」
「N県には一也がいる」
「……やっぱりそこなんだね」
自分でも怖いくらいに冷たくて低くて、理不尽な怒りに満ちた声が出て、なんだか驚いてしまった。眼の前のTETSUも少し瞠目したようだった。
TETSUの過去に何があったかは知らないし知ったこっちゃない。廃病院で燻ってたときにうっすら聞いたけれど、そんなこと関係ない。譲介はTETSUじゃない。TETSUは譲介じゃない。そこに私の居場所はなくても、この事実は変わらない。
TETSUの心の奥にKが巣食って、救ってることは知っている。楽しくて幸せな時間を与えて、そのままどこかに消えてしまった男だ。世界中のすべてが、TETSUが、彼を愛しても、私はちっとも好きじゃない。嫉妬と呼ばれても良い。身の程なんて知らなくて良い。Kは亡くなって、TETSUは生きてる。そして私と譲介を掬い上げた。Kを心に座らせたままのTETSUが。TETSUなのだ。紛れもなく。
「……一也は、K一族はあいつのコンプレックスを強烈に刺激する。カンフル剤だ」
「TETSUさんはいつもそればっかり……」
「これは決定だ。ヤサも用意してある」
「でもそれってあなたの……あなたがKに関わっていたいだけじゃない」
これはまずいぞ、全然止まらない。脳の冷静な部分が必死にブレーキをかけるけど。いやだー、ヒスりたくないよぉー。と思うけど生得ってのは変えられない。三つ子の魂百まで。KEI先生に必死に叩き直してもらっても腐った性根は奥で膿んでる。優しい人になりたかった。KEI先生みたいにK先生みたいに、TETSUみたいにさ。
「私を気にかけるのもKEI先生がいるから……!?」
あなたのドクターKはもういないのに!
はふ、と息を呑んで、その言葉が声に出ていたことに気づいた。こんなこと言う気はなかった。ただ悲しませるためだけに言葉を放ってしまった。言葉は武器だ。ペンは剣より強く、メスより不潔。TETSUが何を言われたくないかなんてよくわかってる。
ほら眼の前の男が傷ついた顔してる。
「…………んなこたァ、俺が一番良く知ってんだよ」
杖を持っていない方の手が伸びてきて、びくりと身体を震わせる。TETSUと出会ってから結構痛い目を見てきて、こういうときすっかり身構えるようになってしまった。いつか力の気配を見せつけてきた手のひらが、意外なほどに優しく髪を撫でる。それを振り払った時に彼がどんな顔をしていたかは見なかった。次に自分が何を言おうとしていたのかもわからない。
その時、玄関の鍵が回る音がした。譲介が帰ってきたのだ。うう、と開きかけていた唇を閉じる。言い争っているところは見せたくなくて。
TETSUも少し息をついて座る。話はこれでおしまいだった。
ダイニングに来た譲介が、平素には戻しきらなかった私の表情を見て少し困惑する。大人の顔色をよく見ている子だ。剣呑な雰囲気を察知するのは難しくない。
「お、おかえり……」
「……ただいま帰りました」
「早いな」
「終業式だったので」
手を洗った譲介が成績表をテーブルにおく。すっかり感情を律したTETSUは何食わぬ顔をでそれを私に差し出す。彼のほうは中身なんて予想がついているんだろう。 私はまだひどく動揺していて、受け取る手が震えていた。開いた上質紙には立派な数字が書かれている。
「……すごい、譲介。本当にすごいね」
もっとちゃんと褒めたいのに
結局私も目の前の子供のこと全然見れてないし全然大切にできてない。TETSUを責める資格はない。力を与えただけTETSUのほうがずっと立派だ。譲介にとって私はTETSUとの間を邪魔する厄介な客人のままで、この部屋に私の居場所はない。
「あの、大丈夫ですか?」
「……ごめん」
用事思い出したから帰るね。なんていう100点満点の嘘をどもりながら言って、逃げるようにマンションを飛び出す。譲介が驚いた声を上げるのを背中で聞いた。
あの子に友達なんてちっとも居ないことを知ってる。TETSUがまるでKの一族みたいに、彼に「医療」を仕込んでるのも知ってる。譲介が私を疎んでいることも知っている。
いつしかあの子がポケットにナイフを隠し持つようになったことも、私は知っている。ぜんぶ知っていて逃げたんだから、一番身勝手で無責任なのは誰かってのは嫌になるくらい明白だよね。

「KEI先生ェ……」
やっぱりあの闇医者、もう一度刺しておくべきだったな。とボロボロ泣いてる私の可愛い大切な子を見て思った。憤怒の気配を察知して、慌てた彼女が否定する。
「ちがうんです、私が悪くて……」
「なにかあったのね」
一度落ち着きなさいな、とスツールに座らせる。紅茶を淹れて渡してやると、少し表情が和らいだ。「ごめんなさい、こんな時間に」と無作法の謝罪から始まる辺り、すっかり社会人らしさが板についたものだ。あの尖りきってた子供は本当に丸くなって、こちらへの信頼もよく表してくれるようになった。
「こういうとき、他に言える相手……先生しかいなくて……」
「無理に話さなくてもいいわよ」
「先生に叱られに来ました……」
そこまで自分は厳しく叱ってただろうか。過ぎ去った日々を思い出す。……叱ってたわね。あんまり物事が上手く行き過ぎると不安になって自滅するのがナマエの癖で、定期的に叱られたがるのだ。
「TETSUさんはずっと優しかったのに……私ひどいことを……」
あの男が他人に優しくする様を想像できない。見た目ほど悪い人間ではないのは知っている。自分が更生したのだって彼の一助があったからだ。とはいえ、だからこそ一層思うのだ。兄という医師の生き様に触れてなお闇の世界で生き続ける男のことを理解してはいけないと。
少しだけ足を踏み入れたからこそ、生々しく想像のつく世界。彼はそちら側の命を救い続けると決めたのだ。そうであるならば、自分は彼を理解してはいけない。テリトリーは守るべきだ。お互いと、なにより彼の患者のために。
そしてこの子があの男に懸想する理由も理解するわけにはいかない。好き不好きは理屈ではないことくらいわかっているつもりだけれど。
あなたの話をするたび、思う。兄であれば、あなたを本人が願うような姿に鍛えることができたのではないのかと。真っ直ぐでひたむきで、幸せになるための資格を持っているような人間に。……彼女がそんな幻想を捨てきれないままでいるという事実が、私にこの子は手に負えなかったのだという現実を表している。幸せになる資格など誰も持っていない。そんなものこの世界にないのだから。
人は誰しも愛される価値がある。
たとえあなたがそれに気付けなくても、幸福の価値など考えずに済むほど穏やかに過ごして欲しい。そればかり祈っている。
似たような痛みを持っているからこそわかる。心の傷はまだ生々しいままいつまでも血を流して膿んでいるのだ。愛されることを諦めても、愛したいとまだ求めている。そうして到底ふさわしくないような、あなたを大事にしない相手とばかり近づいて、自分に愛は勿体ない、手に届かない存在なのだと確認する。自傷行為みたいな関係性ばかり。
だからあの男なのね。
触れ合うことのない個人と個人の間に、感情の火種を見つけてしまったのか。お互いが微かに触れるときにしか存在しない、静電気が火花を散らすような、その瞬間だけの光を。ふたりの他の誰にも気づかれない熱と痛みを。
手が離れあとにだけ、自分の手のひらを見つめてやっと気づくようなそれを。
「母屋の部屋を貸してあげるから、今日のところは寝なさい」
促すとナマエはこくこく頷いて、慣れた足取りで母屋へと向かった。今度こそ医院の戸締まりをして自分もそちらへ向かう。ソファに座ってしょぼくれるナマエを風呂に押し込んでほかほかにしてから、畳に布団を敷いて寝かしつける。
「先生、ごめんね……」
「こういうとき何ていうかは教えたでしょ」
「……ありがと、せんせ」
まったくいくつになっても世話の焼ける子なんだから。
深夜、V8エンジンのけたたましい駆動音が近くにしばらく停まっていたけど、誰も訪ねてこなかったのだから客ではなかったのだろう。
逃避傾向のある者同士が上手くやっていくのはどれほど困難なのだろうか。
灯ってしまった熱を、二人がそれをなんとラベル付けしたのかはわからない。どちらかはそれを同情と呼ぶし、どちらかはそれを憐れみというかもしれない。
ふたりで一緒に考えたら、いつかそれの正体に気づけるのかも。
「本当に、手のかかる子ほど可愛いとはよく言ったものね」

「あれ! ナマエちゃん来てたんだ!」
「おはよう一巳ちゃん……」
「一巳ちゃんって……僕もう中学生なんだよ。恥ずかしいよ……」
「ナマエちゃんももういい感じの歳だから、ちゃん呼びは恥ずかしいかなぁ……」
腫れぼったい目でよぼよぼと起き出すと、リビングでは顔見知りの子供が朝から元気よく笑顔を振りまいている。
「夜中にしょぼくれて泣きついてくるような子は“ちゃん“付けで十分よ」
相変わらず泣き虫なんだから。と、KEI先生がトーストをセットしながら言う。KEI先生のとこっていつもドラマに出てくる幸せな家庭みたいだ。美人でしっかりもののお母さん、元気で明るく健やかな息子。おっちょこちょいだけど頼りになるお父さん(単身赴任中)。いかにもなホームドラマ。
「うう……コーヒー、私淹れます……」
いたたまれなくなってできることを探す。コーヒーを淹れるのはいっぱい練習したので上手くなったのだ。「お手並み拝見かしら」と先生が茶化す。
「僕朝練あるから! またね、ナマエちゃん! いってきまーす!」
「いってらっしゃい、一巳ちゃん……」
「いってらっしゃい、車に気をつけるのよ!」
元気な子供が出ていくと、嵐が去ったみたいに静かだ。
開け放した窓辺でレースのカーテンが波のように揺らいでいる。日差しが降り注いで、庭の緑がキラキラと輝いて眩しくて。
同じ国に生まれててどうしてこんなに違うんだろうな。
譲介の鬱屈は、身をもって理解している。こうして過ごしていると昨日までのことなんか嘘なんじゃないかと思ってしまう。私は譲介にも、TETSUにも出会わずに、自営業にもならず会社の部署を移動して静かに働いて、たまにKEI先生と会って、こうして泊まったりなんかして。
良い人生だと思う。ゾッとするほど素敵だ。
ぼーっと白い布を弄ぶ風のゆらぎを見ていると、ここにも居るべきじゃないなと痛切に感じる。でもあのマンションも私が居ていい場所じゃない。TETSUのことをわざと傷つけて、謝って許してもらえるほど都合よい人生は生きてきてない。頑張った子供にきちんと向き合いもしないで、次にどんな顔して会うべきかもわからない。もう関われば関わるだけ傷つけるんだろう。
大丈夫、譲介にはTETSUがいる。私のことは元々必要としてない。TETSUにも―――、譲介と、Kがいる。いじける気持ちはあるけど、意外と落ち込んではいない。前にどん底だった時と比べたら大抵のことは復帰可能だ。空中ジャンプ上Bでまだ間に合う。そもそも私に落ち込む資格はない。
もそもそと、たっぷりのバターが染みたサクサクのトーストを口に運ぶ。先生が用意してくれたそれは、こういうときに食べるにはちょっと美味しすぎる。
「ほんとに後先考えないわよね、あなた」
それに男の趣味も悪いし、感情のコントロールも下手なまま。そう言ってKEI先生が笑ってコーヒーに口をつけ「……美味しい」と至極意外そうな顔をした。そうでしょうとも。
「人って成長しないんですね……と愕然とします」
こっちは自嘲気味に笑う。人生を笑い飛ばすのは慣れて上手くなったけど、成長はしてない。私とTETSUはやり直してもまただめだった。今度は完全に私の自滅。話し合いが足りない。どうしてもTETSUの前だとなんの言葉も尽くせない。これが人を好きになるってことなら、私に恋は向いてない。
「……してるわよ、成長は。ちゃんと助けを求められるようになったでしょう」
「……でも、私いまTETSUさんと譲介を見捨ててる」
TETSUはいいよ、大人だし。
でも譲介はまだ子供だ。自活する手段を持たず、悪い大人に憧れる良い子。私達が思うよりずっと素直だったせいで、TETSUの言うことを真に受けすぎた子供だ。あんなに屈折した素直な子供、私だったら持て余すな。でもTETSUも時折イノセントさを覗かせる男だから、もしかしたらうまくいくのかも知れない。いってくれたらいいな。
「だからなんなのよ」
先生がピシャリと言った。切り捨てるように。
「心配なんでしょう、二人が」
「それは……まぁ……でももう心配する権利ないと言うか……」
「黙らっしゃい!」
「だ、黙らっしゃいって……」
そう言えばこの人そもそも日本医学会重鎮の娘だったっけ。普通にお嬢様育ちなので、時々めちゃくちゃにお嬢様をやる瞬間がある。私はこれほどまでに飴と鞭を、薬と毒を兼ね備えた人を他に知らない。伝記書こうかな。いや書けないエピソードが多すぎるか。大統領の話ってほんと?
「心配なの? どうなの!」
「し、心配で!!」
「でもいまは戻れないのね!?」
「は、ハイ!!」
完璧に教育の成果だ。特別大きかったり厳しかったりするわけじゃないのに、張りのある声は重厚なクラシックみたいに私の背筋をぴんとさせる。
「……だったらウジウジ悩む前にできることがあるでしょう」
殊更優しく甘美な響きで、先生は微笑む。そこで言葉を切る意味を知っている。先生は止めない。ドクターストップをかけない。見届けてくれる気なのだ。ここはまだ引き際じゃない。
「生活を立て直しなさいな。何かあったときにあなたまでそれじゃ支えられないわよ」
なにもしなくても上手くいったらそれで万々歳じゃないの。二人で祝杯を上げましょう。そう先生が言うと、私がぐじぐじメソメソ悩んでいたことがひどくシンプルなことに感じる。
「もしもあなたの支えが必要な瞬間があったら、今度こそあの男のケツを蹴っ飛ばして泣きながら縋らせなさい」
「いやそもそもTETSUさん悪くないと言うか……」
「バカね。どうあれ、ああいう男は屈服させるに限るのよ」
黙らっしゃいとケツの語彙が両立してるのがKEI先生の魅力である。もうメロメロだ。もしかしてK一族の恋愛術ってかなり力技なのだろうか。
「そして、もう二度と私の大事な女の子が、居場所がないなんて泣かないでいいようにして頂戴」
細くて白い指が頬に触れる。
念入りに繰り返す手洗いと消毒で少し荒れた指先。丁寧に切りそろえられた桃色の爪。横っ腹にゴツゴツとなにかのタコができている。
私が世界で一番憧れている、誰かの心と命のために働く人の手だった。
生きる資格も愛される資格も求めるだけ無駄なのだと。ポケットの中に持っているのだからと。
この人は人を救うことを生業にした。
もしかしたら、多分、きっと、TETSUも。
どうもKの一族と話すと急に人生イケる気がするな。問題はまだ解決してないけど。眼の前のことがんばるぞ! という小学生みたいな目標がでーんと提示されるのだ。単純さは美徳だってKEI先生だけは言ってくれる。
当然ながら仕事を頑張った。ぶっ倒れたらなにかあったときに譲介のこと支えられないので、健康に留意して頑張った。久しぶりに人間ドックいったし。ちゃんと食べて、寝て、適度に運動してお酒は控えてお医者さんの言うことをしっかり聞いたのだ。
どうやら私は私生活運は悪いが仕事では苦労しない星のもとに生まれたらしい。やればやるだけ仕事の評価が上がるのはありがたいことだと思う。
社会生活を送っていたら、何度か誰かといい雰囲気になって食事に誘われたり、飲みに誘われたりもする。でもあんまり上手く行かない。答えは簡単、TETSUじゃないからだ。あの闇医師、私の心にとんでもない後遺症を残したらしい。
二人のことを考えながら目まぐるしく季節は巡る。いつだかK先生に「次は後悔しないように」と言い含められたけど、やっぱりそんなこと私には無理だった。いつも後悔だらけだ。KEI先生に背中を押されても、本当にこの道でいいのか怖くてたまらない。「最悪」を考えて不安がるのはここ最近の趣味みたいなもので、だからそう、KEI先生から電話が来て、本当に不安が的中した時に私は驚かなかった。
「レジオネラ肺炎……?」
『そう、まだニュースにはなっていないけど、一也くんが言うから確かだわ。付属病院に入院が決まったらしいの』
帝都大の入学試験の日だった。ゼミ内でレジオネラ菌の集団感染が起き、試験当日に発症したという。レジオネラって、銭湯とかに行くと「うちには居ませんよ」の証明が掲示してあるあれか。
当日はまだ面会謝絶で、私同様噂を耳にした記者や野次馬が敷地の外を彷徨いていた。入試の最中の出来事だ。情報は感染同様あっという間に拡がったのだろう。
翌日になるとメディアはターゲットをゼミへと移したらしい。かなり減ったマスコミを横目に附属病院に入り、面会の受付を済ませる。
同じような風景が続く廊下を進んで目的のフロアに着くと、手すりに挟まった大きな花束が目に飛び込んできた。無機質な建物のなかでそこだけ異質な鮮やかさだったのだ。
花が指し示すように上に掲げられたプレートを見ると、そこが目的の病室だったことに気づく。
誰が誰へか知らないけれど、渡せなかったみたいだ。
私もまた、花を携えている。悩みに悩んで買ったプリザーブドフラワーだ。これを渡すために来たのだ。
見も知らぬ渡せなかった人の気持ちがよくわかる。なんて言葉をかけたら良いかわからない。あの人の期待に答えることは譲介の全てだった。一浪したくらいであの人は見捨てたりしないだろうけど、譲介自身が自分に絶望する理由には充分すぎるほとだ。起きてしまったことは仕方ないし、私がしてしまったことも取り返しはつかない。今できることをするしか無い。
意を決してドアを開ける。
「…………あれ?」
譲介が居るはずのベッドはもぬけの殻だった。カーテンで仕切られたそこはたしかにこの大部屋における和久井さんの寝台のはずだけれど。
隣に横たわっていた男性が掠れた声で「和久井くんのご家族の方ですか?」と私を見る。彼もまたレジオネラ肺炎の罹患者だろうか。ぐったりと横たわっていて、症状が重そう。
こういうときに何度も使ってきた便利な嘘は、気にかけてくれた親切な彼にも簡単に口にできた。
「え、ええ。おばです」
「和久井くん症状軽いから、ちょっと前に散歩に……」
「そ、そう……」
大部屋、息がつまりますもんね。少ししたら戻ると思いますよ、と言う口ぶりは親しげで、もしかしたら譲介の友達かもしれなかった。
「また日を改めます。……お大事になさってくださいね」
花を置いて踵を返す。残念な気持ちと共に、少しだけホッとしている自分に軽く失望した。会ったところでなにもできないし怒らせるだけなのはわかっている。それでも顔くらい見に来るのが最善だと思ったけど、よく考えたら私の自己満足だもんね。 やっぱりこれでよかったのかもしれない。
病室から出ようとノブに手をかけたたところで、先に扉が開いた。
「あっ」
「っ…………あんた……」
「…………譲介……」
一瞬驚きで固まった白い顔が、みるみるうちに赤くなっていく。怒りだ。そりゃそう。憤怒で絶句する彼と、二の句が告げなくなった私、どちらも大部屋には相応しくないので慌てて廊下に出てドアを閉める。譲介はぐっと感情を抑えて「ここじゃ目立つ」と歩き出した。
「何しに来たんだよ」
「……は、肺炎って聞いて……」
「大した症状じゃない」
酸素マスクも外れた、とは言うけれど、元々白かった肌はいっそ青白いし、ガラガラと引きずるそれは点滴のパックだ。
「僕はもうすぐ退院する。……島村さんは、まだかかりそうだけど」
「そう……」
人気のないベンチに座って、譲介はうつむく。そしてもう一度聞いた。こちらを見ないまま、低く。
「どの面下げて…」
「……心配になって……」
心配なのも顔を見たかったのも謝りたかったのも本心だけど、どの理由を取れば彼は納得するのかな。
「あんたにできることなんか何もないだろ」
「それは……」
そうだね。さすが、よくわかってる。私の心を的確に抉る真実を譲介はいつも知っていた。
「あんたはいつも勝手だ」
「うん……」
「大人気ないし、保護者失格だろ」
「そうだね……」
「……可哀想な僕じゃないと見向きもしないのか?」
「えっ……?」
徹頭徹尾私が悪い、反論の余地なく。と思っていたところに予想外のボールが来て驚いて顔を上げる。
「あの日だってそうじゃないか……僕は、ちゃんと1位を取ったのに」
声が震えているのは怒り抑えているからと、彼なりに気持ちのセーブができるようになったのだと、そう思っていたけれど。
「……アンタは僕に背を向けた」
「譲介……」
彼の表情はうつむいて見えない。けれど震えるほど強く握りしめた拳にぽたりと水滴が落ちた。
泣いていた。
私のせいだ。

なんで泣いているのか自分でもわからなかった。
いやそんなのは嘘だ。僕はこの人には何の感情をぶつけてもいいと思っている。そうして離れて行った人なのに、いまだにそうしてしまう。怒りも不甲斐なさも腹いせも全部ぶつけてしまう。
この人が僕を捨てたのは僕のせいだろう。
ドクターTETSUは何も言わなかったけど、きっとそうだと確信がある。
「僕はなんの期待にも答えられなかった……」
「ごめん……」
「僕を捨てたんだ。都合の良いときだけ現れて善人面するなよ……」
「ちがうよ、譲介。あれは私が悪くて……」
「言い訳なんか聞きたくない!」
母親は僕を捨てた。この人も捨てた。あの人だけが僕を捨てない。見捨てない。刺し殺そうとしようがこのひとを傷つけようが見知らぬ母子を引き離そうとしようが手術で足を引っ張ろうが、ドクターTETSUだけはこの3年間こんな僕を捨てなかった。
今更この人が現れて、なんだっていうんだ。
滑り込みでゼミを斡旋してくれたのはドクターTETSUだ。そこまで目をかけてくれた人の期待に答えられなかった。僕をどん底から掬い上げてここまで手を尽くしてくれた恩人にすら、今の僕は当たり散らしてしまいそうで怖かった。1年の浪人期間、はたして一也とどれほど差が開くのか。今でさえ遅れを取っている。追いつく見込みすらなくなるかもしれない。背中すら見えない周回遅れになったら、もう僕は、なんのためにここまでやってきたんだ? なによりあの人が、なんのために僕を拾ったんだ? 僕は何になればいい? どんなふうに生きればいい?
この先自分がどうなってしまうかわからなくて、ただ不安だった。
「もう二度と僕の前に現れるな……」
僕はまたこの人を傷つけるし、この人も多分また僕をムカムカさせるだけだ。この人に会って話すと、イラつく。むしゃくしゃする。嫌になる。
こんなちっぽけな人の優しさに甘えそうな自分が嫌になる。
「……譲介は、私に会うと傷つくよね」
そうだよ。と言いたくなくて、うつむいたまま無視をする。
少しだけなにかを言いたげな、言葉を選ぶような気配がして、それでも彼女は立ち上がる。「でもね」と、座った僕の頭に強張った声がする。揺れて、震えている声だった。
「……なにかあって、周囲のまともな大人の誰にも頼れないときは、しぶしぶでいいからかけてね」
うつむく僕の眼の前に、白い紙が差し出される。名刺だ。いつかのときも貰ったが、あの頃は呼ばなくても無駄にしょっちゅう会えたから、多分どこかに捨ててしまった。その時とは違う紙に、格調高い印字をしている新しい名刺。
しばらく無視したけれど、一向に引っ込めることはなく、しかたなく僕はそれは受け取る。指の圧で、紙片がたわむ。
持ち主がいなくなってからもしばらく、その紙を見つめていた。
目の赤みが引いた頃に病室に戻ると、島村さんが「おかえり」とベッドの上から出迎えてくれた。
テーブルに色とりどりの花が置いてある。プリザーブドフラワーって言ったっけ、花のミイラに色を付けたものだ。
「おばさんが置いていったよ」
「おばさん……あぁ」
説明に困る時は叔母で通していたっけな。「おばさんキレイだね。なんか、薄幸美人って感じで」と島村さんは笑う。
「見た目だけですよ」
ベッドに横になると、明るい色の花は嫌でも視界の端にちらつく。ごろりと反対側を向くと無機質な病院の色に囲まれて漸く落ち着いた。
もともと枯れているようなものなので、数日の入院中放ったらかしでも花は鮮やかなままだった。すぐに捨てても良かったけど、島村さんに変に思われたくなくてできなかった。生花であればしおれかけたら処分できたのに。花瓶もないのだし。と思ったところで、だからプリザーブドフラワーだったのかと気付いた。
退院日、島村さんに挨拶をして病室を出る。
ドクターTETSUは受付の前でなにやら手続きをしていた。なんて声をかけたら良いかわからず立ち尽くす僕に気づいて「なんだその花」と言った。彼もまた、最初になにを言うべきかわからなかったのだろう。
「ナースセンターには挨拶したか?」
「え、いや……」
「してこい。スタッフへの敬意は欠かすな」
こういう細やかな部分も含めて、僕には学ぶべきところがまだいくらでもある。僕の恩人。僕だけの大人。あの人が居なくたって、彼がいればそれでいい。
お世話になったスタッフたちに挨拶をして、正面玄関へ迎えに来ていたハマーに乗り込む。
「……あの人が来ましたよ」
そう言うと、運転席の男は片眉を上げた。
「誰だ?」
「えっ……」
ドクターTETSUは知らないのか、あのひとが僕を見舞いに来たことを。
彼女が僕を捨てた日、あの日は大変だった。お望み通りの成績を取ったのにドクターTETSUは「ご苦労だった」と言ったきりひどく重く黙り込んでいて、こういうとき賑やかしになる人がその原因らしく、逃げるように走り去ってしまったから。引き止める声にも振り返らずに、僕を捨てた。
でもこの人たちのことだから、僕の知らないところで会っているんだろうと思っていた。ナマエは僕にだけ特別会いにこないのだと。とうとう僕を嫌いになったのだろうと。それは失望するとともに安心でもあった。嫌われそうな行動をしていた人に嫌われる予定調和は、安心する。そうだよ、僕が人に好かれるわけ無い。
信じられないことにあれで彼女は売れっ子作家だったので、新刊が出たり、本屋でその筆名を見るたびに「僕を放って元気にやっているんだな」とくさくさした気持ちになったものだ。面倒なガキは放っておいて、好きな男の尻だけ追いかけて気楽なものだと軽蔑した。
ナマエは元々、ドクターTETSUの知人としてやってきた人だ。
僕とドクターTETSUの生活に急に割り込んでくる、部屋に飛び込んできた虫とか、校庭に現れた犬とか、そういうのに似ていた。どうしていいかわからない。なにも悪さをしないならどうでもいいし、でも居ると気になって落ち着かない。危害を加えたいわけじゃないけどどこか遠くに去ってほしい気持ちもある。穏当に追い払ってしまいたい。
あの人のことを嫌いだったわけじゃないのだ。ただ、ドクターTETSUが彼女を構うのが気に食わなかっただけだ。嫉妬とはいまだに認めたくはないけど。
だけど、でも、もしかしてこの人たち、あれ以来会っていないのか……?
ドクターTETSUはなにか察したのか、それ以上聞いては来なかった。
あの人の知らない、N県中心部にあるマンションの駐車場にハマーH2が滑り込む。
エレベーターで27階に上り、玄関ドアを開く。
男は手摺りに体重をかけて玄関に座り込む。ゆっくりとブーツを脱ぎ、スリッパをはいてたっぷり時間をかけて立ち上がる。僕以外の視線が無いとき、ここ数ヶ月はいつもそうだった。
廊下を擦るように歩くこの足取りを、彼女は知らないのかもしれない。
ドクターTETSUの病弱は、刻々と悪くなる。
この人が病気だと知ったのは、本格的に医療を教わり始めるその時だった。最初の実地課題が彼のルートを取ることだったから。
そうして学んでいくほどに、この男の体の状態が明白になって僕の眼前に晒される。自分の力不足もうんざりするほど理解できる。決して良い状態ではない、それどころか。
結局この人はまともに試験を受けることすら出来なかった僕を一度も叱らなかった。もう期待されていないのかもしれない。
ドクターTETSUに残された時間はあとどれくらいなのだろう。
このマンションで、ベッドに横たわる彼のそばにいる自分を想像してみる。簡単に思い描けてしまって、それも少し良いかもしれないと思った。