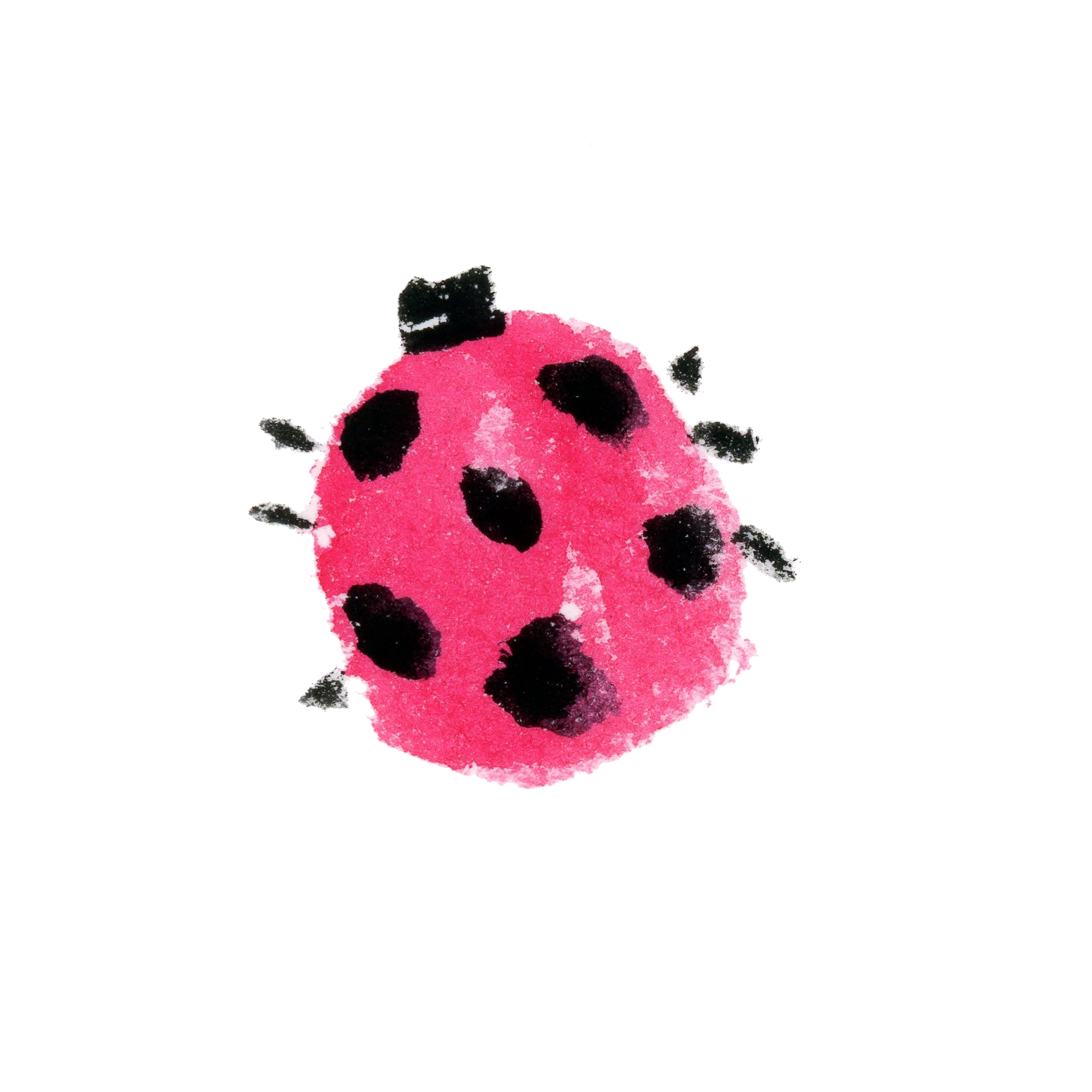
3-2
僕を引き取った男は「本物」だった。僕や、つるんでる不良たちみたいな生半可なものじゃない、本当に闇に生きる男だ。ドクターTETSUは闇医者。そして僕に人を操る術を教えてくれるという「お優しい」人らしい。
ぶち込まれたのは異様にセキュリティのしっかりとした都内の高層マンション。エントランスにはコンシェルジュがいるし、カードキーがないとエレベーターも動かない。
だからそんな部屋の前でインターフォンを押して「突然ごめんね、ドクターTETSUの関係者なんだけど」とカードキー片手に愛想笑いをする女性を見て「あぁ、そういうことか」と思った。
施設を転々とするうちに色んな子と出会った。僕みたいに物心付く前からもう施設に居た子、ある程度大きくなってから、事故や事件やそれ以外の理由で突然に親や保護者を喪った子、それから、不適切な親保護者から行政の介入で引き離された子、他にも様々な理由で近しい人間からの庇護を無くした子が集まるのが児童養護施設。施設毎に質も方向性も様々で、入所している子供も様々だった。家出した結果「そっちの世界」の手駒として生きることを選んだり余儀なくされたりした子供もいた。そういう子は大抵児相や警察なんかが保護して更生先を振り分けられ、大人たちに指導されて暮らす場を決められる。もう二度とそんなことをしたくないと言う子もいれば、こんなとこ早く出て元の世界に戻りたいと言う子もいる。前者の子は自分の過去を隠したがるが、後者の子は武勇伝みたいにひけらかしたりもする。どちらも防衛本能だ。
そんな中で聞いたことがある。アパートの一室に住まわされて「客」を取らされるやり方を。
だからか。最初にあの男に引き取られ、こんな都心の派手なマンションの最上階に自分の部屋を作られた時、正直に言えば怖かったのだ。ちゃんとした生活ができそうに居心地よくされたキッチンやお風呂。自分のためだけに用意された新品の学習机。デスクライト、辞書と携帯電話。そしてベッド。子供じみた青い布団。
いかにも里親然とした家庭っぽい場所ならば油断もできたかもしれないが(僕にだってそういう場所で試しに暮らしたこともある。うまく行かなかったけど。)、とても家庭人には見えない怪しい風体の大男と、その人ともいまいちちくはぐとした、でも新しい子供のために確かに用意されている新品のインテリア。
だからこの男は僕になにか「期待」しているのかもしれなくて、僕には差し出せるものなんて身体一つしか無い。いつか入浴中の脱衣室のドアが、トイレのドアが、夜中の「僕の部屋」のドアが開かれるのではないかと。そんな不安に襲われることもあった。結果としては杞憂で、そもそもあの男は居ない日のほうが多い。居たとしても、夜中に帰り明け方に出かけるような有様だ。まるで拾ったばかりの野良猫を怯えさせないようにしているみたいだ。
でも現れた女性を見て、違和感が線で繋がったような気分だ。そういうことか。
「急に来てごめん、近くに寄ったから……」
そんな事言いつつ勝手知ったるふうに洗面所で手を洗っている女性に背後から近づく。鏡越しに僕に気付いて女が振り返る。別に、女へ色目を使うのははじめてじゃない。年上の成人女性相手は初めてだけど。洗面台に手をついて大人の女の人の体に触れようとする。もう少しうぶっぽいかんじのほうがよかったのかも、と逡巡した一瞬の隙に、普通に平手打ちが飛んてきた。
「っ」
「あっ、ご、ごめんつい!」
反射だったらしい。呆然としていると慌てて洗面台でタオルを濡らして頬に当ててくる。
「ごめんね、いろいろあって防衛本能強めで……あ、母性的なのがいる感じ⁉ 私そういうのなくて……」
別にママが恋しくて触れようとしたわけじゃない。ママもパパもいたことない。父母の記憶なんて無いから恋しくなることもない。ただ「女性の顧客」なのかと思ったのだ。売春なんてしたことないけど、騙されて連れてこられた無知なガキとして笑われ搾取されるよりは、知ったかぶって主導権を握ったほうがいいと思ったのだ。顧客ではないらしい女は「母性って母さんの腹に置いて来ててさ」とわけのわからない言い訳をしていた。
「別に母親も母性キャラじゃなかったから多分腹の中で対消滅したんだろうね」
なんかごめんねとりあえずハグする? と冗談めかして腕を広げてきたのでゾッとした。母性なんて欲しくないし、母性の紛い物なんてもっと最悪だ。クソだ。そもそも本当は他人の身体なんて触れたくない。
「触るなっ!」
「っ」
今度は僕のほうが彼女の腕を振り払った。バシンと結構強い音がして血の気が引く。まずい、ドクターTETSUの関係者に対してこんなこと。
ドクターTETSUと僕は当然不均衡な関係で、あの人と彼女の関係は不明だけど、彼女の口先一つで僕のいまの部屋なんて簡単になくなるかもしれないのに。「あ」と口をついてでた声は自分でも嫌気が差すくらい間抜けで弱々しかった。
「ごめん、悪いジョークだったね」
翻って彼女は困ったように笑って身体を離した。お互いの間合いから出るように、洗面所からも一歩離れて。
「あなたの許可なく触んないから、あなたも許可なく人に触れちゃだめです」
「…………はい」
「それから、今日は突然押しかけて本当にごめん。次からはちゃんとエントランスからアポ取るから」
「……ドクターTETSUはあまり居ませんよ」
「TETSUさんじゃない、あなたにだよ」
都合が良くなかったら全然普通に断ってね。という人に、都合も、全然も、普通にも、うまくできる気がしなくて、でもそんなことおくびにも出さずに頷いた。
「……TETSUさんはあなたになにか求めた?」
少し眇めた瞳がこちらを見る。皮膚が表情筋に引張られて皺が浮かぶ。眉間の間に薄く現れる数本の皺、細められた目の下に浮かぶ薄い皺。眦に刻まれて瞳の柔和さを際立たせる皺。
「……通っている高校で学年1位になれと」
「そう」
それだけ言って「なにかあったら連絡してね」とドーナッツと名刺を置いて女は去っていった。
日が暮れてから「帰って」きたドクターTETSUは、ミスドの箱を見て「誰か来たのか」と言った。誰かとは言っているが、予想のついていそうな顔だ。こちらもしたり顔で返す。
「ええ、あなたの恋人が」
「俺に恋人は居らん」
「え」
じゃあ誰だったんだあの人。もしかしてこれ怖い話だったのか。
「……悪いやつじゃあねぇよ。俺に連絡がつかねぇときはあいつにかけろ」
「ご友人、なんですか?」
「そう見えるか」
見えないな、と思った。恋人のほうがまだそれらしい。

彼が退院してから、TETSUのヤサに行くのは避けていた。身元引受人の周囲を他人がうろちょろしていたら、少年が不安がるだろうと思ったのだ。いまはTETSUと彼とで信頼関係を深めたり、新しい環境に慣れたり、そういう時間が必要だと。
だというのに私の気も知らず身元引受人さんは「会いに行け」と言った。
「来週から一月くらい留守にする」
「来週もなにも、そもそもなんでいまうちにいるの……」
時間は夜。しかも深夜だ。保護者が子供を置いて女の家に来てる場合ではないはずである。
「高校生だぞ。放っておいても死なんだろ」
「高校生だけど、未成年だよ。慣れるまではついてあげなよ」
「お前こそ、もっと世話を焼くもんだと思ってたがな」
「いや私は……」
単純に、彼と対面しても何を言えばいいのかわからないのだ。「はじめまして! 私はあなたの保護者の……」友人? 知人? 未成年に伝えていい適当な関係性が思いつかない。
「ともかく、しばらく仕事で空ける。ちょくちょく様子を見に行ってやれ」
そんな事をいうので、邂逅を済ませておこうと仕方無しに翌日ドーナッツ片手にマンションを尋ねることとなった。そしてファーストインプレッションは見事に失敗した。敗因はドアを開けた瞬間、少年の顔に明らかに殴られたあとがあったからだ。TETSUによるものでないのだけはわかる。そういう人じゃないからね。でも子供がえぐめの傷をこさえている事実で完全に動揺してあとはもう上手く取り繕え無いままコミュニケーションは滑り倒した。
「ねぇあの子大丈夫なの?」
「大丈夫だったら引き取ってねぇよ」
「そもそもあの傷なに……」
「不良チームを抜けた制裁だそうだ」
遠出の前日、家に寄ったTETSUは困惑する私を前に何故か自慢げにそう言った。
「いまは俺が課した目標のためにえらく熱心に勉強してやがる。大した執念だぜ」
この男、ちょっと子育てが面白くなってきてるな……。
譲介少年のほうにはTETSUから話を通してくれたらしい。彼が出稼ぎに行った数日後、再度手土産片手に訪ねると「顔見知りの女がちょくちょく様子を見に来るけど害はねぇから放っておけ」と告げられたと譲介は言った。
譲介は、捨て猫みたいにあらゆる全てを警戒している。私が訪ねると「勉強します」と言って部屋に引きこもる。家の中全てで気を張っていて、どこもかしこも異様なまでに整理整頓をしている。家政婦さんがスーパー家政婦なのかと思ったけど「私が居るときもほとんど部屋から出てきませんし、どこも潔癖なくらい使用感がなくて……」と少し気味悪がっていた。
譲介にとって、ここはまだ家じゃないのだ。
そもそも家というものがわからなかったり、捉え方が私とは全く違ったりするのだろう。TETSUが彼をわかりやすいかたちで暖かく愛情深く受け入れたとも思えないし、おおかたいつもの闇医者ムーブで「人を支配する方法を教えてやるぜクックック」みたいな感じで迫ったのだろう。だから私が来ることも、見守りと言うよりは監視に思えるのかも。それなら警戒されて当然か。初手で叩いてしまったのもまずい。富山以降ああいう不穏な場面ですぐに手が動くようになってしまったのだ。子供といえど、高校生男子相手だと私の力では普通に押し負けてしまう。私が身を守るのに必死なように、あの子供だって自分の安全を守るために必死だ。自分を強く優位に見せるようにあんな行動をした彼のことを責められまい。あの時少年は、怯えていたのだ。世間一般のありとあらゆる人類に「無害」と舐められまくる私相手にすら。
これこんな繊細な時期に出稼ぎに行ってるTETSUが悪いよ、TETSUが。命に関わる仕事だし、仕方ないのはわかるけどね!
譲介の経歴や雰囲気を見るにつけ、そんな有り余るほどの警戒心はある意味正解な立ち回りなんだろうと思う。親切や好意を素直に受け止めるにはそれなりの体験が必要だ。譲介からしたら優しさすら攻撃と同義だ。
まぁそんなことは関係なく、思春期の少年がうざがるほどのお節介は大人の義務なのでやるけども。だってほら、TETSUの時もそうだったし。拒否されそうだからと最初から手を出さないのは、拒絶と一緒だ。
「買い物に行こう」
と言うと譲介は心底嫌そうな顔をした。愛想よくされないだけまだ救いがあるのかもしれない。
「夕飯何食べたい?」
「……三田さんのご飯があるでしょう」
「話は通してあるよ。今日は調理実習」
家政婦の三田さんは週イチで来ておよそ1週間分を作り置いていく。たまに覗かせてもらうけど、やはりプロはすごいなという手際だ。そんな三田さんの努力を無駄にするわけには行かないので、事前に今週は5日分でお願いしますと伝えていたのだ。
「生活のお勉強、そういうの施設でもあったでしょ?」
「まぁ、少しは……」
「で、何食べたい? 譲介はなにがすきなの?」
「……………別に、なんでも」
「とりあえずカレーかな」
初回だしね。ビギナーはカレーと相場が決まっている。
「豚派? 鶏派? 牛派?」
「……べつに、なんでも」
カレーならわりと何でも、という意味だと知ったのは結構あとになってのことだった。
ドクターTETSUが仕事で家を空ける間、お知り合いとやらは5日に一度ペースで来た。基本的に長居はせず、僕もあまり話すことはない。ほとんど部屋にいるようにしている。ドクターTが言うように、たまに要らない世話を焼く以外は害はなかった。TVを見たりダイニングで何やらパソコンを広げていたり、時たま部屋にお茶を差し入れてきたり、適当に構われるのはそんなに嫌じゃない。気まぐれに二人分コーヒーを淹れて見たら「才能あるよ!」と大袈裟に褒められて体よくコーヒー係にされた。
ただ、彼女が居る時にそのドクターTが帰ってきた日、明確に「嫌だ」と思った。ちょうど要らない世話のひとつ、おやつの時間とやらであった。テーブルには箱に入ったシュークリームが居て、僕はコーヒーを淹れていた。ガチャリと玄関が空いて、重い足取りがどすどすと廊下を歩く。すりガラスの入ったダイニングの扉にぬっと大きな影が差してそこからひと月ぶりに見る姿が現れる。
「あれ、戻るの今日だっけ。おかえり〜」
「……お、おかえりなさい」
「…………ああ」
コーヒーを淹れる僕を見て少し驚いたようだった。
嫌だったのは別にこの人が帰ってきたからじゃない。ただ、この人たちは僕よりも付き合いの長い知り合いだ。この人と僕が二人で過ごすのはいい。彼女と僕で過ごすのも、百歩譲ってまぁ良い。ただ、この人たち二人と過ごすのは嫌だった。狭い空間に居て、その他大勢と僕ならかまわない。二人と一人になるのは、無性にイライラして不愉快だ。
ドクターTETSUは洗面所に行かずシンクで手を洗う。ナマエは「譲介、どっちがいい?」と普通のとチョコのシュークリームを掲げた。
「別に、どっちでもいいです」
「TETSUさんは?」
「どっちでもいい」
男二人の曖昧な返答に苦笑して、テーブルの対面にシュークリームが置かれる。僕は両手に持っていた白いマグカップをそれぞれに置いた。シュークリームはふたつ、マグカップはふたつ、人間は3人だ。なにか言われる前に「僕」と声を上げる。それに被せるようにナマエが「私」と言った。僕が「僕勉強があるので」と自室に引きこもる前に。
「もう行くね」
「え、あの」
引き止める前にさっさとカバンを持って「またね」と去っていく。TETSUが止めないので僕も喉から制止の声を出せずにオロオロした。二人と一人になりたくなかったけど、ドクターTETSUと二人きりになったところで僕がこの男と向かい合わせてシュークリームを食べる姿なんて想像つかない。本当に余計なおせっかいをする人だった。
立ち尽くす僕を前にして、ドクターTETSUは静かに椅子を引いて座る。視線だけで座るように促されて、おずおずと僕は向かい合わせに座った。僕の席には期間限定濃厚ショコラパイシューがある。ドクターの前に置かれた特製クリームパイシューは僕のそれより少し肩身が狭そうだ。大きな手が掴むと、それはやたらと小さく見える。
彼は器用な手付きで黙々とシュークリームを食べた。この人も甘いもの食べるんだな。僕がかぶりつくと反対側から少しクリームが出て手が汚れた。向かいの男が箱ティッシュを寄越す。
「……ざす」
小さくつぶやいた返事が聞こえたのかどうなのか、ドクターTETSUはコーヒーに口をつけた。マグカップの持ち方が変だった。

「転校?」
壁にかけてある新しい制服を見て、ナマエは目を丸くした。私立の進学校のものであるそれは先日届いたばかりだ。2年への進級に合わせた春からの編入に向け、試験を受けたり手続きをしたりと着々と準備をしていたが、この人知らないままだったのか。
「編入手続きでドクターTETSUがスーツ着てたけど、見ものでしたよ」
「なにそれ!? 写真ないの?」
「あるわけないだろ」
そんな気安い関係ではない。少なくともこの人を相手にするときみたいに雑に扱う勇気僕にはない。
ここに引き取られて数ヶ月経って、ナマエともドクターTETSUともそれなりに関係性が固定されてきた。彼が患者をマンションに引き入れるようになったのでこの女が来る頻度は減ったが、その分彼女の来る日が明確になり、こちらも心の準備ができるというものだ。僕のほうがナマエに遠慮しなくなった以上に、ナマエも僕をかなり適当に扱う。「嫌だ」と言えば素直に引き下がるので顔色を窺う必要がないのは楽だった。
ナマエがあの人と一緒にいることはあまりない。あの人が居る日も、ナマエは夕食を食べたらさっさと帰っていく。彼も引き止めないし、口数もそんなに多くない。ナマエも僕とばかり話している。最初の頃は万が一泊まっていったらと思うとかなり緊張した。ドクターTETSUの部屋にあるベッドは世間一般よりも大きくて長いサイズで、病室兼客間にしてる部屋ならともかく、彼の部屋にナマエが入っていったら僕はとても気まずい思いをしただろう。実際には、少なくとも僕の居る時に二人の距離が近すぎるということはなかった。むしろ遠かった。ナマエが「社会勉強」と称して3人で出かけることも何度があったが、いつもドクターTETSUは金だけ置いてしれっとどこかに消えるし。
「実は猫アレルギーなのかもね」
「絶対違うだろ」
猫カフェで猫と戯れながらナマエが言う。先程までやたらと猫に纏わりつかれて黙りこくっていた男は、財布から抜き出した数枚の札をナマエに押し付けるとふらふらと何処かに行ってしまった。ナマエと僕が猫カフェに来たのははじめてではない。二人きりで来たこともある。意図は明確にあって、小動物を虐殺した過去のある僕に、小さい生き物との接し方を叩き込むためだろう。遠足の幼稚園児に混じってふれあい動物園でうさぎを触らされたこともある。ハリネズミを触らされたときは「トゲトゲして震えてて譲介みたーい」と言われてこの女いつか本気でどつこうと思った。
猫は筋肉がしなやかで素早くて人間なんか簡単にあしらって、媚びないし、嫌いじゃないと感じる。
「猫の毛がつくと困るんじゃないか。服黒いし、急患とかもあるし」
「あの服換えがいっぱいあるんだよね。譲介今度何枚あるか確認しといてよ」
「嫌だ」
何度も言うがこの人程気安い関係じゃないのだ。僕とこの人ほど。この人と彼ほど。
この人が僕を連れ回すのだって、ドクターTETSUと裏で同意は取っているのだろう。取っているのかな。多分取ってると思うけどあの人としては場所のチョイスは納得していないのかもしれない。事前に提案してたら猫カフェなんて彼は絶対来なかったはずだ。珍しいものが見れた。
ドクターTETSUは口が悪くて厳しい。それに文句はない。与えられるハードルはいつも今の僕よりも少し高く、食らいつくのは骨が折れる。勉強、社会常識、マナーと立ち回り、僕の人生ゲームは取り落としてきたものばかりで、いまからそれを拾い直すのにはかなりの苦労が必要だった。近頃は医学の面も伝授され出して、より緊張感が増している。それでもドクターKの話をするときだけは彼は至極楽しそうで多弁で、ドクターKとやらはよほどドクターTETSUが執着している相手なのだろう。それはナマエよりも、よほど。
傷ついた顔をするだろうなと思い、ついナマエにその話をすると、案の定ナマエは顔だけ笑って瞳は全然笑って無くて、してやったりと溜飲が下がった。ナマエもよくこんな嫌な子供を相手にするものだ。ナマエが僕を嫌っても、僕は「やっぱりな」としか思わないだろう。

「試されてんなぁ」
「TETSUさんが受けるべき儀礼じゃん」
「アイツは俺に反抗しねぇよ」
できねぇよ、と男は言う。
譲介と解散してうちに帰れば当然のようにこの男が待ち構えていた。我が物顔でコーヒー飲んでる。譲介もこんな男に生命線を握られて可哀想に。
少年の剥き出しの反骨精神はTETSUっては好ましい。もっと向けてくれても構わないと言う。だが現状の不均衡な関係性ではそれは難しいだろう。もっと譲介が自立したあとじゃないと。
「だがそれも、難しいだろうな」
と言うTETSUの判断は残酷で正しい。それくらい彼の中の穴は大きい。本人もそれはわかってて、時折焦りが垣間見える。私にですらそうなのだからTETSUにはもっと明確に見えているのだろう。
一方で、彼の心を置いてカリキュラムはどんどん進んでいく。知識の面は飲み込みが早い。正解が決まっていることは迷わないのだろう。対物であればそれで良いかもしれないが、対人職である医者を目指すのであればそれはいつか大きな壁となるはずだ。身体と知識の成長に、心が全然追いついていない。むしろどんどん離れていく。このままじゃ彼は取り返しの付かない失敗をする。TETSUと同じように。私と同じように。私にとってのKEI先生みたいに良いメンターがいてくれたらいいのに。TETSUにとっての……誰だろう。……ドクターKかな。
やっぱり私達じゃだめなのかもしれない。保護者として不適格だ。そんなこと思ってるなんてまさか譲介に知られる訳にはいかない。保護者の後悔は養育過程の否定だ。いまの譲介からしたらはしごを外されるようなものだ。
譲介がTETSUのもとに来る前日、教育上よくないからベタベタするのやめようと提案するとTETSUは「ベタベタしてねぇだろ」とのたまった。ベッドの上でひっつきながら。大嘘過ぎるだろと噴き出したし、彼も無理があるなと気づいて流石に笑っていた。
以来この男とはスキンシップを取ってない。マンションでも、我が家でも。いままでで一番健全な距離感だ。メンタルも良い。仕事もはかどる。TETSUと私の関係ってここがゴールなのかもね。それも悪くない。
「でもKEI先生はどう思います?」
「そうねぇまずは……」
久しぶりの西城医院、診察室でKEI先生は考える素振りをする。左下に視線を向けて最初に突っ込むべき部分を選び、それからこちらを真っ直ぐ見る。
「あの闇医者をもう一度刺すべきか考えてるわ」
「もう一度!?」
すでに一回刺してるのなんでだろう。私まだ皆さんの過去について知らないことが多いみたいだ。
「なんで? 痴情のもつれ?」
「勘弁してちょうだい」
男を見る目はあるのよ、私は。と女子トークモードだ。私に男を見る目がないみたいに言うのやめてほしい。確かにKEI先生の男を見る目の確かさは磯永先生を見ていればよくわかるけど。いい人だよね。
「いまの環境じゃ子供のためにはならないでしょうね。……とは言えその状態の子供を今までの環境に置いたままでいたとしても好転したとは思えないわ」
「それはそうかもしれませんが……。でもなんというか、私……私達にできることって多分もう……」
「でも今ドクターTETSUから引き離すのも、危ういわね」
行政も学校も福祉も手に負えない未成年をどうするべきなのかは社会全体の永遠の課題だ。個々のケースに合わせた対応をしていくしかないだろう。譲介にはドクターTETSUが合っている、と思う。けど他にもマッチングできるなにかがこの世界にはあるはずだ。今までの譲介にはあの男が最適だった。今後は別の最善手もあるのかもしれない。子供が成長したら、取り巻く周囲も変化すべきだ。
譲介はもう昔の譲介じゃない。勉学、心理学、医学、乾いたスポンジのように全てを吸収する。TETSUの持つ暴力性や繊細さや危うさも。それはある種の武器だ。譲介はより強く戦う術を手に入れた。
使い方を間違えたら取り返しがつかない。
「保護者っぽい顔しちゃって。……子供の成長ってはやいのね」
「ほんとうに、時間が全然たりませんよ」
そっちじゃないわよ。とKEI先生は笑った。もうとっくの昔に成人してしまっているはずの付き合いの長い子供を、「しょうがない子ねぇ」なんて瞳で見ながら。