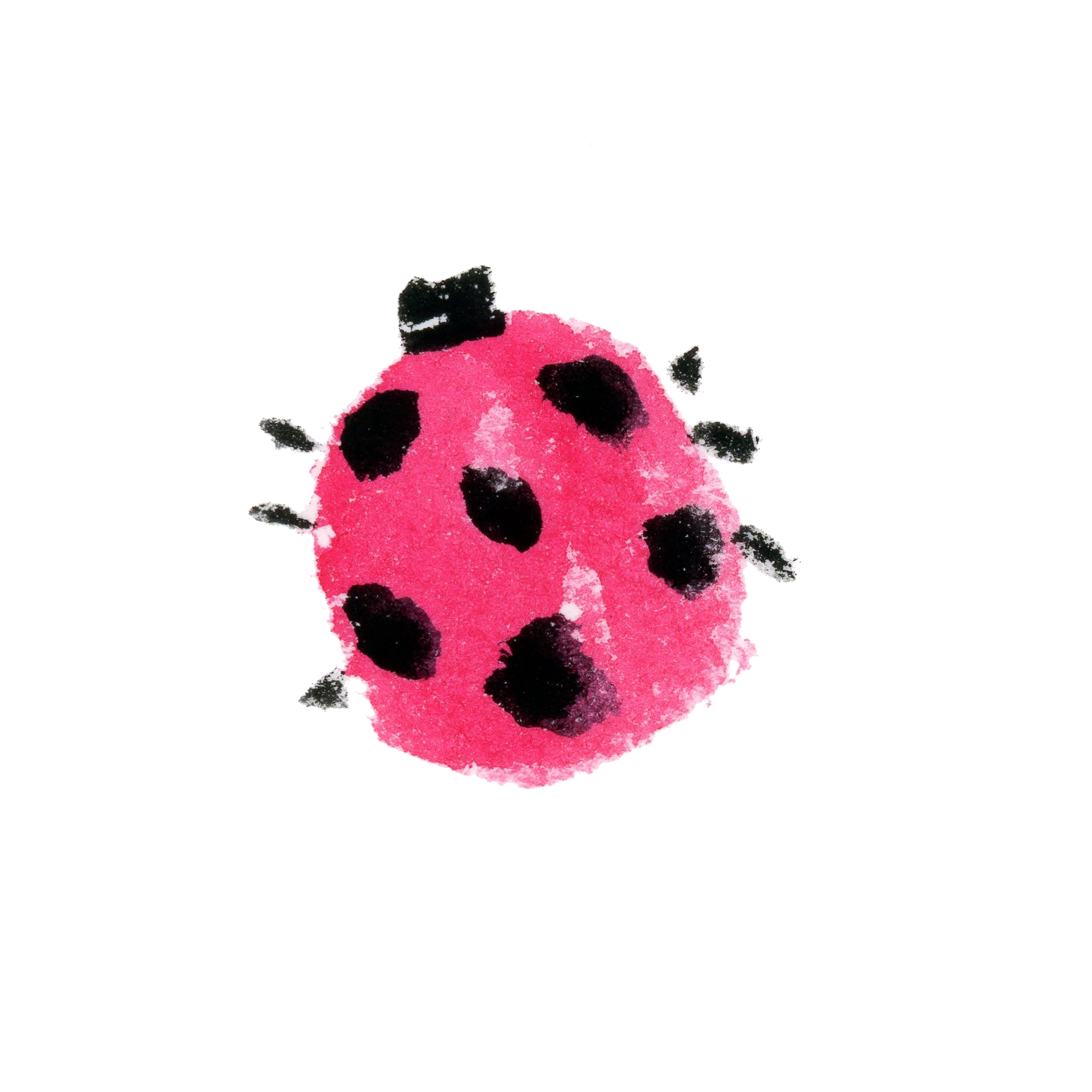
閑話2
(高1秋頃)
「……なんでアンタが居るんだよ」
「いや一応連絡はしたというか……」
現代っ子らしく譲介は送ったメッセには何気に即レスしてくれるのだが、今回はそれがなかった。五月雨式でごめんと思いながら続けて送ったものにも反応がない。そのまま一晩。TETSUは例によって遠征中であった。保護者不在時に、未成年と連絡がつかない。保護者の不在で羽目を外してるだけなら構わないが、一応様子くらい見とくか、と思いながらなじみのマンションへ行くと、普通に居た少年は開口一番そう言った。
「顔だけ見に来たからすぐ帰る……つもりだったけど、なんか、もしかして体調悪い?」
「あんたには関係ないだろ……」
家の中なのにマスクをしているので端正な顔立ちの半分しか見えないが、目が据わっていて顔色も悪い。「そうだよ早く帰れ」と少年は言った。言おうとした。けど無理だったらしい。「っう……」と呻いて口元を抑えた。
……さっきから感じる饐えた匂いはこれだったかぁ。
学校でノロウイルスの集団感染が流行している、という今朝のニュースを思い出しながら、私は自分のカーディガンが青少年の吐しゃ物を受け止める様を見ていた。

「ごめんね、体調悪いのに急に来たから……」
「…………」
より顔面を蒼白にした少年に「大丈夫だから、いいからベッドに行ってて」と言いつけて、シャワーと洗濯と清掃・消毒を済ませてしまうと、最後に残った仕事は少年の心のケアであった。私もTETSUに嘔吐物を見られてるよ大丈夫だよ。と思ったけど、譲介もTETSU相手ならもう少しダメージが少なかったかもしれない。保護者だし同性だし、医者だし。
消毒された洗濯物はドラム式洗濯機でゴウンゴウン回されている最中である。洗濯機の中で放置されていた乾燥済みのスウェットを拝借させてもらったので、いま色違いでおそろいのスウェットを着ている。着替えのひとつも置いておけばよかった。
「ドアのとこスポドリ置いとくからね。用事あったらメールして」
と、ドア越しに声をかけると、しばらくして携帯電話に電子お手紙が届く。「すみません、寝てたので連絡気づかなかったです」と殊勝な態度だ。文章からわかるほどに落ち込んでる。「大丈夫だよ、買い物行ってくるからいるものあったら教えて」と返信すると「ない」とそんなわけはない返答があった。冷蔵庫の中に水とお茶とセロリしかない。モデル並みの生活感のなさ。なんであるの、セロリ。あと米とカレールーは買い置きがいっぱいある。譲介が生活に慣れてきたので最近はあまり家事代行を入れていないのが裏目に出ている。こういう時ってどうするのが適切だったかな。たすけて脳内のKEI先生。「カレーは消化に悪いからゼリーかおかゆにしなさい。脱水に注意するのよ」と教えてくれた。ありがとう脳内のKEI先生。

気分不快で最悪の目覚めだった。いつの間にか枕元にスポーツドリンクとパウチのゼリーと薬がある。換気のためか窓が少し空いていて、夜の空気が気持ちよかった。
リビングの窓も空いているのか、風に乗って声が聞こえる。耳慣れた女性のものだ。ゆったりとしたしゃべり方、普段よりも少し低い。
「―――……うん、そう、いつ帰れそう?」
その一言で電話の相手はすぐに分かった。僕の話をしているのもわかる。
「あ、でも伝染ると……え? いや私はもう手遅れだね。ミイラ取りがミイラだね」
体調の悪さ故記憶の彼方に吹き飛ばされていた自分の失態を思い出し、頭を抱える。よりにもよってこいつにこんな姿。最悪だ。相手が親切で様子を見に来ただけなのもなんだか嫌な気分になったし、こんなことであの女が怒らないとわかっている自分も、だからこそ「こんなこと」と言えてしまう甘えた自分も嫌だった。あいつと居ると時々、あんなのでも大人なのだと気付かされて、それが自分の未熟さを見せつけられるようでイライラする。
「うん、大丈夫、そう。うん。塩素系漂白剤で消毒はしたけど……。」
「え? 薬箱? うん、あー……いや、んー。わかった」
「……じゃあ早く帰ってきてあげてね」
余計なお世話だ。
僕抜きで僕の話をしている大人たちを意識から消すように、毛布をかぶって目を閉じた。