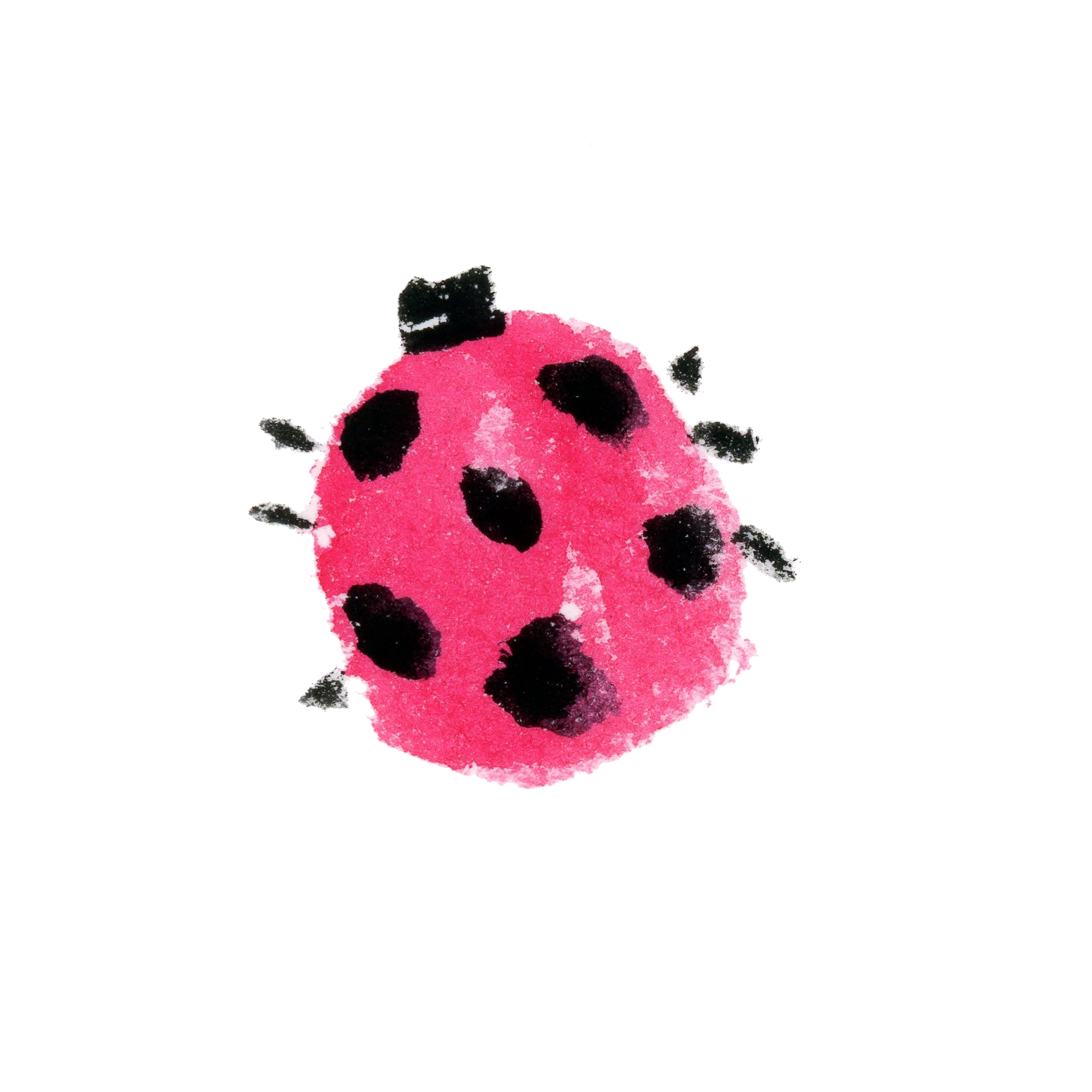
閑話2
(高2春)
「TETSUさん車出してよ! 私お酒飲むから!」
「平等な取引みたいに言うな。お前が飲みたいだけだろ」
邂逅一番ナマエがそう言ったのをドクターTETSUが軽くあしらう。「譲介もお花見したいよね、春だもんね」なんて言われて、一瞬考える。この場合どちらが正解なのか。ドクターTETSUは素直じゃない。口に出したことと本心は別にある。それくらいはわかる。その分岐ののちにどれを選ぶべきかまではわからなかった。ともかく、そういう思い付きみたいな一言で一行は郊外の公園まで行く羽目となった。休日の日中は、同じように桜を見に来たらしい人たちであふれかえっている。家族づれや会社の行事、大学生の集まりなんかの有象無象の隙間を縫うように屋台の香ばしい匂いが漂っている。振り向くとナマエはもうビールの入ったプラスチックのコップを持っていた。たいていいつも機嫌がいい人だけど、今日は鼻歌でも歌いそうなほどだ。
「家にありたき木は、松・桜。ってね」
「徒然草でしたっけ?」
「現役世代は話が早いね。庭があったらなに植えたい? わたし枇杷。あとミント」
「破滅願望でもあんのか」
「なんでですか?」
「枇杷を庭木にすると縁起が悪いって言われてるんだよ、家に病人が出るって」
「ミントは繁殖力が強すぎる。シソやドクダミ、セイタカアワダチソウなんかもな」
「真っ赤なバラと白いパンジーとか植えたい」
「子犬も飼うのか?」
「そうだね横には―――……」
多分僕にはわからない、世代か何か共通した文化圏の話をしていたみたいだけど、ナマエはふとそこで押し黙った。やっぱり機嫌よさそうに笑いながら。
「やめよっか、この話」
「お前が始めたんだろ」とドクターTETSUは呆れた顔をした。

(高2秋)
つけっぱなしにしていたテレビから不穏な音が聞こえて、不意に目を覚ます。ニュース速報の音だった。大型の台風は強い勢力を保ったまま北上し、本州で猛威を振るっている。
携帯電話の災害情報が不安を掻き立てるような警戒音を鳴らして、私の住む地域が避難区域に入ったことを告げた。
「そんな事言われても……」
変な時間に眠った罰なのだろうか。とっくの昔に外は暗く風は吹きすさび、横殴りの雨が窓を叩いていた。
避難? いまから?
重い腰を上げて、ひとまず窓の外を見る。まぁ、できなくはないか……。むしろ今のタイミングを逃すと、完全に身動きが取れなくなりそうであった。一応用意してある非常持出袋をクローゼットの奥から引っ張り出す。
強風の音に紛れて、やかましいが耳慣れたエンジン音が家の前に止まる。
「TETSUさん……?」
顔を上げると、チャイムがのんきに「ピンポーン」と鳴る。同時にどこか相反するような激しさでガチャガチャと、玄関扉がたわんだ。
「オイ、生きてんのかっ?」
物騒な言葉とともに、合い鍵で解錠されたドアが勢いよく役割を終えて、風と共に雨粒が家の中に入り込む。
嵐を背にした男は、ぽかんと呆ける私の顔を見て舌打ちをした。
「―――チッ……無事なのかよ」
「な、なに?」
なんか知らんが無事でごめんね。強い風の抵抗を受けながら男が玄関ドアを閉めて、湿った巨体が我が家に上がりこむ。
風と水気で髪もコートもよれよれと乱れていた。タオルを渡してやろうと脱衣所に行こうとすると「いいから、出る準備してこい」と制止される。
「え?」
「……おめェ、携帯見てねぇな」
声音には少し憤りが滲んでいた。
慌てて手に馴染む電子機器を見ると、1時間ほど前から着信4件と1通のショートメールが届いていた。同じ番号。たまに変わるので登録はしていないが、登録していない事自体が「彼」からの電話なのだと私に理解させてくる、見知らぬ数字の羅列。
ショートメールは着信よりも時間が新しく20分前のもので「そっちに行く」と潔い一文を表示していた。
「……えーっと……寝てた……」
「そのようだな、その様子だと」
心配して来てくれんだね。
我が家は安い、古い、そしてハザードマップが真っ赤であることが売りの年季の入った愛すべき賃貸アパートである。しかも一階だし。まだ遭遇したことはないが、いつだかには冠水したこともあるらしい。
「ごめんね……」
「いいからはやく支度しな」
「う、うん」
荷物の準備をしている間、闇医者はガスの元栓を締めたり戸締まりを確認して雨戸を締めたりしていた。停電の可能性も考えて、すべての準備を整えてからブレーカーを落とす。復旧火災と冷蔵庫の中身、天秤にかけたら天高く掲げられたのは後者だ。一晩くらいなら大丈夫だろう。
「ね、わざわざ来てくれたの?」
「こっちで仕事だったからな、ついでだ」
外に出ると強風に煽られて誰かのタオルみたいなものが吹き飛んでいくのが見えた。電線とかにひっかからないといいけど。
私の荷物をひょいと持ち上げた男は、風圧で重たそうな車のドアを開く。的が大きくてコートがバサバサはためいて、人のことより自分のことを気にかけてほしいものだが、いつまでも立ちすくんでいても埒が明かないので助手席に乗り込む。
「ごめんね」
私を迎えに来なかったら、多分高速道路には乗り果せていただろうに。ついさっき高速が封鎖されてしまったせいで、下道をとろとろドライブする羽目になってしまった。彼の向かう先は、高校2年生が住む隣県のマンションだ。
「譲介、大丈夫かなぁ」
タワマンって揺れるらしい。去年住んでいた都心のタワマンよりは、今彼らが住んでいるところは少し低いが、とは言え高層階には違いない。
「今日は休校だから家に居る。それに、あいつはちゃんと連絡がついた。どっかの誰かと違ってな」
「眠かったんだよ……なんか頭痛かったし……」
「相変わらず気圧の変化に弱ぇな」
「なんで気圧が変わると体調崩すの?」
「自律神経が乱れるからだな」
「出たよ自律神経……なんなんだよお前は。私を律しやがって……」
「べつに敵じゃねぇよ。素直に律されてろ」
「自分の身体が引き起こしたことで体調崩すの、生きる下手だなぁって感じ」
「癌の俺に言うかね普通」
「えっ、癌ってそうなの⁉」
「外的要因もあるが、基本は細胞の変異だからな」
「……いつか二人で『生きるの下手くそ選手権』してどっちが強いか決めようね」
「馬鹿野郎、俺を変な大会で優勝させるな」
「勝つ気だよこの人……」
病気云々ではなく、お互い精神性において生きベタなのである。
そんな話ばかりしてたら、下道ゆっくり安全走行でも意外とはやく目的地に辿り着いちゃった。隣県のほうが風が強かった。私達は台風へ向かって時速50キロ弱で走行していたらしい。
「おかりなさい。……お風呂湧いてますよ」
「だってさ」
「お前が入れ」
「いやTETSUさん先でしょ、TETSUさんちだし」
「あんたを連れて来るって聞いたから沸かしておいたんですよ」
「えっ、譲介偉ーい。でかした」
問答しててもしょうがない、この二人は頑固なので、先にお風呂をいただくとする。このマンションには数えるほどしか来てないし、お風呂を借りるのなんてはじめてなので少し戸惑った。
どうせ泊まるしなとついでに部屋着に着替えてしまい、ちょっと迷った末思春期の他人がいるしマナーだよなとちゃんとブラは付けた。TETSUしかいなかったらしない気遣いだった。
タワマンは普通にめちゃくちゃ揺れて愉快だった。いつかポッキリ折れるかもしれない。
「停電したらどうなるの?」
「ここ自家発電ありますよ」
「すごいね、世界でゾンビパンデミックが起きたらここに立て籠もろう」
「そうなったら医療品が不足して……」
そこで少年と二人押し黙った。医薬品が不足したら確実に死に瀕する男は、いま私の残り湯に浸かっている。
病はゾンビよりもよほど現実的だし、一番恐ろしいのはそれがホラーではないってことだ。
「…………ホラー映画で何が一番好き?」
「なんで僕がホラー映画好きな前提なんだよ。……施設じゃ小さい子が怖がるからあんまり見たことないですね」
「そっか、ちなみにここにスクリーム三部作のDVDがあるんだけど」
「なんでだよ」
「なんでだろうねぇ」
胡乱な会話の気配を察知したわけではないだろうが、お風呂で温まった部屋着姿の家主がリビングにやってくる。前髪もきっちり乾いている。テーブルに置かれたホラー映画のディスクケースを見て「飯時はやめろ」と真っ当なことを言った。譲介が適当なバラエティをつける。画面には台風情報が映っている。
夕飯はカレーだった。譲介は育ち盛りなのでおかわりしていたし、TETSUは私と同じくらいの量しか食べなかった。そして譲介は良い子なので、片付けようと立ち上がる私からお盆を奪い取って自主的にキッチンへ向かっていく。保護者に似ている。
「……ヤングケアラー」
「そこまでさせてねぇよ。家庭の『お手伝い』の範囲だろ」
「ねー譲介、映画見る時ポテチとアイスどっちが良い?」
キッチンに声を張り上げると、水音に紛れて「どっちでもいい」と少年の声が聞こえた。なるほど、両方だな。
「TETSUさんもオールする?」
「勝手にしてろ」
今日は金曜、明日は土曜。土曜授業も、すでに休校が決まっている。夜ふかししない方が不健康だ。
結局麗しきロートルはコーヒーをちびちび舐めながらスクリーム2の序盤くらいまでは付き合ってくれた。「まぁまぁ面白いな」と素直な感想まで述べていた。
「見たことなかったの?」
「学生時代はよく映画館に入り浸ってたもんだがな」
「あぁ、ずっと居れたもんね」
「そうなんですか?」
「昔の映画館って一度入ったら同じのずっと見れたんだよ。入れ替え制なかったから」
ふうん、とソファの上で膝を抱えた少年は鼻を鳴らす。
太陽を盗んだ男を繰り返し覚えるほど見たという数十年前の在りし日の少年が自室に引っ込んだあと、スクリーム2を見終えた現代の少年は3をセットしながら、ぽつりとつぶやいた。
「あの人、あんたと居るとよく喋るな」
「TETSUさんはいつもあんな感じじゃない?」
「僕の前じゃもっとこう……いや、喋るけど」
「かっこつけてるんだね」
「僕に良いかっこしてなんになるんだ」
「可愛い譲介くんが憧れてくれる」
可愛い可愛い良い子で悪い子の譲介くんは肩をすくめた。
「あんたに聞いた僕が馬鹿だったよ」
「そうかもねぇ」
TETSUさんはもともとええかっこしいで昔気質だ。行動だけで示したがるし大事なことは絶対言わない。そりゃ譲介からしたら不安しか無いだろう。
心配しなくても、私としているのはどうでもいいしなくても良いような話だ。
譲介とはどうでも良くない話ばかりしているから、会話の質が違うように感じるんだろう。あとKの話か。Kの話はTETSUの鉄板トークだからいつでも嬉しそうにしてくれる。
Kとはどんな話をしたんだろうなぁ。
いつの間にか眠ってしまっていたらしい。ふと目覚めると、電気は常夜灯になっていてテレビ画面は消えていた。
生き物の気配に目をやると、ソファの上では私の横で、子供があどけない顔をして眠っている。すぅすぅと、寝息は小さくて愛らしい。寝ている時は本当に天使みたいだ。驚くほど可愛くて、退屈なほどにピュアそうだ。見た目だけは。
明日絶対身体痛くなるけど、まぁいいかと思って再び目を閉じる。
風に煽られて高層階の部屋は少し揺れている。外ではまだ嵐が逆巻いていて、雨は窓を叩く。
誰かがそばにやってきて、のんきに眠る女子供に毛布を被せた。