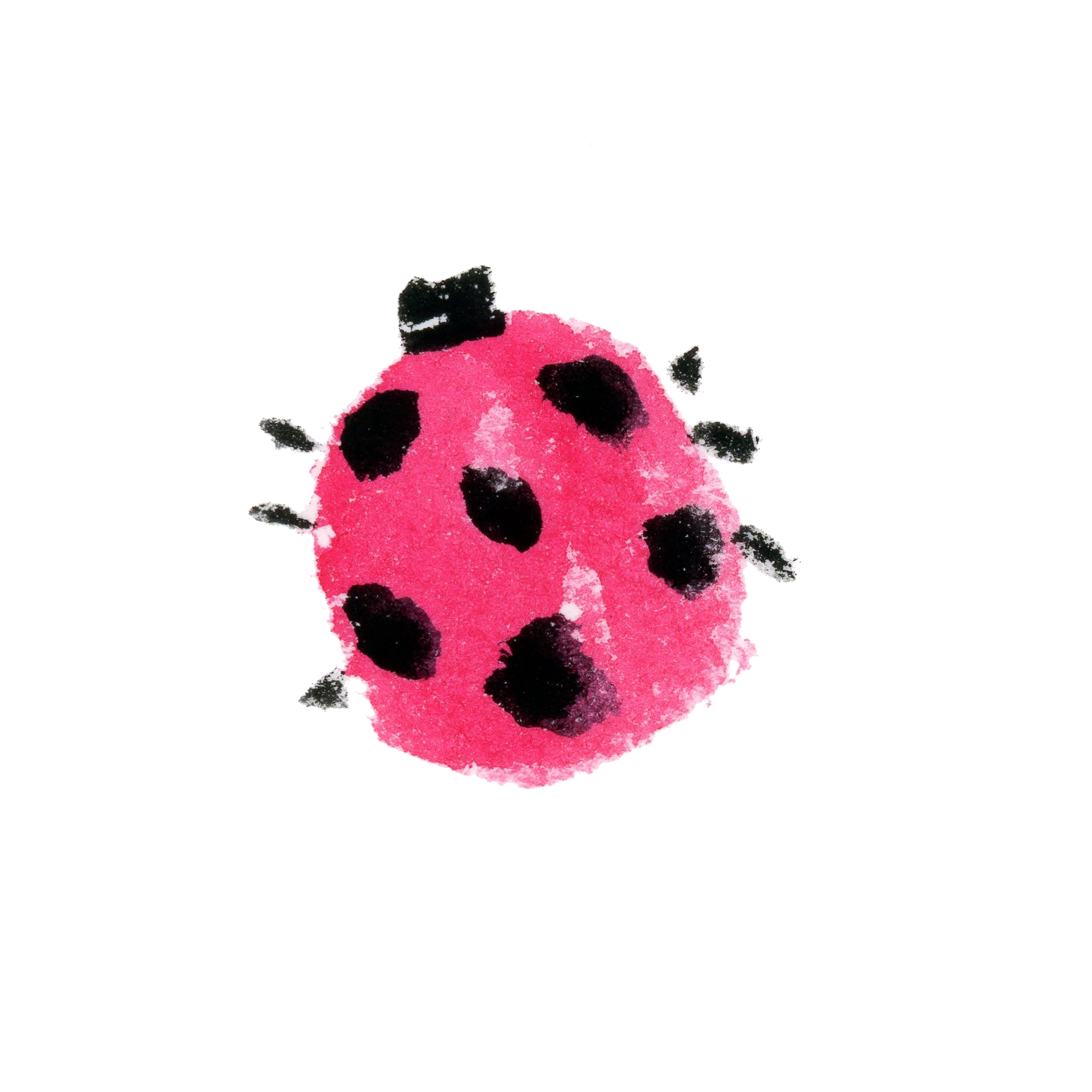
2-6
TETSUと人生を浪費しながら停滞していた間、仕事とかどうしてたの? と問われると当然ながら普通に全然していなかった。わたしは真っ当な社会人の倫理など持たない。職場に行けば仕事があった定職時代はともかく、いまは書けなければどうしようもない。信頼と収入が減るだけだ。
とはいえこちらにも罪悪感も責任感も多少はあるので、休んでいる間を埋めるように書いた。それはもう、いっぱい書いた。書く以外の仕事もした。恋愛論の対談とか私にさせるべきじゃなさすぎるけど、散々迷惑をかけた編集からの依頼だったので義理で受けた。そしてウケた。
「迷惑かけたんじゃなくて、心配かけたんですよ」
と、少し年上の編集者は言う。
「先生は恋愛で身を持ち崩すタイプじゃないと思ってたので、余計に」
「今更持ち崩せるような身がないんですよねー」
「相手とはどうなったんですか?」
「ちゃんと破綻しましたよ」
ちゃんと、破綻したのだ。
TETSUが私を人生からパージしたので、私もTETSUと繋がったテザーを切った。私はそれなりに安穏と生きてるのでTETSUもどこかでゴキゲンハッピーでいてくれたらいいな。
プロテイン飲んでヘルメット被って、トム少佐とはサヨナラの時間だ。
「その割には元気ですね」
「仕事があるので」
「あ、でもすこし痩せました?」
「仕事が、いっぱいあるので……」
「そろそろスケジュール管理する人雇ったらどうですか」
ダメージは当然あるけれど、人生どん底ってとこからサバイブすると多少のことは鈍麻するものだ。おかしいくらい好きだったけど、いまもまだおかしくなっちゃうくらい好きかもしれないけど、そもそもあんまり真っ当な性格はしてなかったのでマイナスとマイナスをかけてむしろプラスかもしれない。
TETSUの生業が表舞台に出ることはなく、関係が終わってしまえば私からTETSUの気配は見えない。
反対に、こんな体たらくでも仕事は軌道に乗っている。本だって平置き。困ったことにTETSUがいないと仕事が筆は乗りに乗り、書きまくり売れまくり。自分でももう引くくらい売れてる。仕事と仕事と仕事の管理と事務作業と仕事で多忙を極めて感傷に浸る暇はない。いっそ止まるのが怖いくらい。
このまま自分にできることをちゃんとしつづけていれば、いつかどこかでTETSUが私の飛躍をちゃんと見守ってくれるかもしれないな。なんて、そんな健気なことを思う。
あとついでにイニシャルグッズのTの文字を見る度に元気かなぁって思うし、街ででっかいハマーを見かけるとナンバーを確認する。ていうかハマーじゃなくてもいかつい戦車みたいな車を見る度に目を凝らして運転手を確認する。けど探してないから、全然TETSUのことなんて探してないから。向いのホーム路地裏の窓にTETSUのこと探してるわけじゃないんだからね。言ってて虚しくなってきたな。一目会ったところでできることなんてないし。
K先生のもとには後日、謝罪とお礼のために尋ねた。
「お二人の関係の経緯はKEIさんから聞いています」
と、プライバシーに配慮したのか人払いした先生は、ふたりきりの診察室でそう言った。
「恋人や家族、……親しい間柄の人間が大病を患えば、ケアをする側も多大な負担がかかる。疲弊して、時に判断が鈍る」
お一人でさぞ苦労されたでしょう、と慮る表情は本気だ。あるいは本気に見えるようにしていた。医者ってすごい。
「一人で他人の命を背負うなど土台無理な話だ。あなたがあの期間を気に病むのであれば、次こそは後悔のないようにしてほしい」
つぎ、と復唱した私に、先生ははじめて困惑した顔した。そうしてみれば意外と若い。私とそう変わらないのではないか。
「次はないです。TETSUさんとは終わったので」
「終わった……とは」
「えーと、絶交しました。そのほうがいいと思ったので」
はじまってもいなかったですけどね、と笑うと先生は一瞬だけぽかんと呆けた後、形容し難い表情をした。なにその顔。絶交なんて子供の喧嘩みたいだもんね。こういうときKEI先生なら「誤魔化さないの」と言って更に問い詰めてきただろうけど、K先生の性格なのか、それ以上TETSUとの関係について追求はされなかった。そもそも私が彼の患者じゃないからかな。
「食事はきちんと摂れていますか?」
「まぁ、それなりに」
唐突な問診にちゃんと答えなかったのも、やっぱり私は彼の患者ではないからである。
ここまで引きずるならTETSUと離れるべきじゃなかった、とは、ちっとも思わない。気持ちの整理に時間がかかるのはあらかじめわかっていたし、これ以上私がTETSUにできることもなければ、TETSUが私を求めることもない。このまま目の前のことだけ見てればそのうち時間が解決するだろうと期待した。それなりに楽しいうちに終わらせてしまったほうが、美しい思い出になるだろう。
だからいま苦しいのも一過性のものだ。いやこの場合の苦しさって、心じゃなくて。
「これ絶対熱ある……」
ふらふらするし頭痛もする。変な汗も出てきた。
ソファから起き上がれないまま、手探りで体温計を探す。うまく取れずに体温計を入れていたケースが床に落ちた。ついでに一緒に入れていた絆創膏や鎮痛剤なんかの細々したものも床にバラバラと散らばる。それも拾えない。
朝からなんかめまいがするなぁなんて思っていたのだ。起きぬけにソファに座ってノートパソコンを開いてメールを返して、そのまま仕事をする。水分と食事を忘れるのはこの頃日常茶飯事だ。茶飯事なのに茶も飯も摂ってないとはこれいかに。一時期かなりまめまめしく料理をしていたのが嘘みたいだ。あの間の私の伸びしろはすごかった。友達誘って料理教室とかも行ってた。無駄にビリヤニとかパンづくりとかもやった。TETSUの健康期間がもう少し長かったら蕎麦とか打ちだしてたかもしんない。
ひとまず水分……と思ったけどマグカップには昨日の飲み残しのコーヒーしか無かった。お察しの通り生活は荒れてる。胃も荒れてる。
体温計、いや、水分……あと塩分……? 整腸剤、鎮痛剤……、いやその前に何かたべたほうが……。視界と思考がぐるぐる回る。あーこれやばいかも。ここで動かないとマジで床のシミになる。孤独死TIPsなんだけど床で死んで時間が経つと床に「自分」が染みるのでソファとかベッドの上がいいらしい。後の人がちょっと楽だとか。死んだあとのことなんか知らないけど。
えいやと残りの力を振り絞って冷蔵庫までたどり着く。部屋が狭くてこれほど感謝したことはない。こういうときのための買い置きスポドリを取り出してキャップを回す。キャップを回す。キャップを回す。開かない。HP赤メーターでへぼへぼの握力と手汗によりプラスチックが滑って回らない。こういう全ての人間が使用する機能はユニバーサルデザインであってよね。
「た、たすけてぇ〜……KEIせんせぇ〜っ」
泣きつく相手はどこにもいないけど情けない声が出た。単身、出勤のない自営業、枯渇したHP―――、人生とグッバイしてしまう可能性が脳裏によぎる。
ガチャリ、と。
玄関の鍵が回った。熱と冷や汗で動悸が止まらなかった心臓が、一瞬凍りつく。その直後にバクンと、さっきまでよりずっと激しく胸が鼓動した。携帯はソファのあたりに落ちていて、私は立つのもままならないし当然大声も出ない。まずい。
為す術もなく凝視していた玄関扉のノブが揺れる。開かれた隙間から外の空気が流れ込んでくる。昼間の日差しが眩しくてくらくらする。
「おー、死にかけてんな」
数え切れないほど夢で会っているので、いっそ懐かしさなんて欠片もない男。
ドクターTETSUがそこに立っていた。
「え、天使……?」
「……遅かったか」
もう手遅れだ頭がな、と言外に告げられた。ブーツを脱いでズカズカと我が家に踏み入って、床にへたり込んだままの私にしゃがみこんで目線を合わせる。状態を診られている。いつだかもこんなことがあった気がする。
「とりあえず脱水だな。症状は?」
「……あたまいたい、くらくらする、し、幻覚が見える……」
「俺は幻覚じゃねぇよ」
「だって……」
カラカラの身体なのに涙は出るらしい。とはいえわりと控えめにぽたりと一滴落ちるような奥ゆかしいものだったが。
貴重な水分を使うなと叱られ、自分の体重さえろくに支えられていない私を両腕ですくい上げる。そのままソファに座らされ、背中を背もたれに預けられた。
常温の経口補水液のキャップをぱきりと開けて、そのまま突きつけられる。
「飲めるんなら口から飲め。吐いてもいいから」
ぼーっと見ているとしびれを切らしたのか「吸い飲みでつっこまれるのと点滴どっちがいいんだ」と二択を迫られる。
仕方なく震える両手でボトルを受け取って、少しずつ口に入れる。こくりと嚥下して喉が震た。
少し水分の戻った唇でやっと男の名前を呼べる。久しぶりに出した音なのに、唇はこの動きを忘れていなかった。
「てつさん、なんで……」
「なんで、とはご挨拶だな……」
小さな金属音とともに男は右手を掲げる、人差し指に引っかかっていたのはドラゴンソードキーホルダー、そして鍵。私の家の鍵だ。そういえばいつのまにか何処かに失くしていたな。それどころじゃないので完全に忘れていて、たったいまその存在を思い出した。TETSUが持っていたのか。
それでも、果たしてこの男はなんで一番私が会いたい時に来てくれるのだろうか。名前すら呼んでいないのに。
呼べなかったのに。
「こないだ、朝の番組出てただろ」
「見てくれたの?」
「たまたまな」
そう、いまの私は自分でも気力体力ともに追いつけないくらい引くほど売れてるので、朝の情報バラエティで数分の宣伝インタビューくらい受けるのである。事前収録とは言え、前述のとおり最近のコンディションは最悪で、わりとボロボロの出来だったので見てほしくはなかったけど。
TETSUと朝番組、似合わないね。
「えらく痩せたじゃねぇか。顔色もヒデェもんだ」
むに、とゴム手袋に包まれた指で頬をつままれる。TETSUはわたしよりよほど私の身体に詳しい。そのまま下瞼をつまんで貧血の程度を確かめて、「舌出せ」と言ってベロと喉奥を診察された。
無遠慮な手が身体を弄って、すこし浮いた肋骨に眉をひそめる。
「脱水と、免疫低下で風邪の引き始めだな。ちゃんと食え」
「……TETSUさんには関係ないじゃん」
きれいな形の眉毛が片方だけぴんと跳ね上がる。
「私のこと、いらないって言ったくせに……」
完全な恨み節である。こんなこと言いたくなかったのに。言わずに済ませたくて、だからあんな別れ方をしたのだ。取り縋るなんてみっともない。自分から潔く離れて、きれいな思い出でありたい。とはいってもスタートが嘔吐胃洗浄なので綺麗さにも限度があるけど、映画でも終わりが潔いとなんとなくいい映画を見た気がするものだ。 だから、こんなはずなかったのに。
眦にまたじわりと涙が滲んで、ごまかすようにそっぽを向いて経口補水液に口をつける。めちゃくちゃ美味しいから身体がほんとにだめだったんだなと気づく。
「……薬を出してやるからなんか食って飲め」
「いらない」
「医者の言うことはちゃんと聞け。死にたくないなら」
「TETSUさんは私のドクターじゃないでしょ」
可愛げも儚さもない。完全にただの意地っ張りだ。誰ひとり得しないけど、つい喉はそう震える。
「……だったらとっとと西城KEIのとこにでも行ってりゃよかっただろ。朝から死人見てぇな顔晒してねェでよ」
「だって……」
TETSUはまっすぐとこちらを見ていた。相変わらずキラキラと光るきれいな茶色い瞳。その上から眉毛をしかめてあからさまに目つきを悪くして、闇医者はこちらを見ている。怒っているのかもしれないし、怒っているふりをしているのかも。
「だってTETSUさんとのこと聞かれたくなかったもん」
「なんだそりゃ」
「ちゃんとしなさいって言われてたの。流されて時間を無駄にしたなんて……言えないよ……」
多分K先生経由でとっくに知ってるとは思うけど。いやどうだろう、一応守秘義務の範囲なのか。ともかく、KEI先生に叱られると思うと背筋が冷える。馬鹿みたいなことはたくさんやってきたけど、二十代になってからは結構落ち着いてきたはずなのだ。闇医者と懇ろになったとこまでは勘づいているだろうが、低く低く流れ落ちてやばかったことまでは流石に言えない。
「そりゃ悪かったな、お前の時間を無駄にして」
「ちがうよ、私の言い方が悪かった……」
無駄にしたのはTETSUさんの時間だよ、とぼそぼそ言いながら俯く私にはっきりとした声が投げかけられる。
「どうしてえんだよお前は」
「……わかんない」
視界の中には黒いアームカバー。折り曲げられたコートとの間に白い肌が見える。相変わらず土気色。少しは血色を感じるが、病の存在を匂わせては私を空恐ろしくさせる色だ。どうしたいんだろう。TETSUはどうしたいのかな。
「どの道を選んだらTETSUさんが一番長生きしてくれるかわかんないの。私といたらTETSUさん早死しちゃう……」
TETSUがいなかったら寂しい。TETSUがいたら嬉しい。当たり前だ。でもこの人は病身で、私よりも年上で、世界中のあらゆる論理が「死ぬぞ」と訴えかけてくる。私が病や不慮の事故事件に巻き込まれる可能性も決して低くはないけれど、そんな可能性よりもずっと明確に、運命はこの男を私の人生から引き剥がそうとする。
なによりも実績が語りかける。苛む。
K先生たちに会ったからこそ強く。
私がそばに居たって何も出来ない。治療もケアも保護も。ただいたずらに時間を空費して後悔ばかり生まれるのだと。
なにか言おうとして、なにも言えず黙りこくる私にTETSUは少し息を吐いた。無意識にぴくりと体が震える。
呆れとも諦めとも違う声音とともに大きな手のひらが頭に乗って、わしわし乱暴にかき混ぜる。普通なら「ふざけんな」と思って当然な行為だが、この闇医者相手だと不思議となんでもない気持ちになって許せてしまう。
「作家先生は偉くなったもんだね」
「なに……」
「俺の時間の価値をあんたが決めるんじゃねェっつってんだよ」
乱れた前髪越しに見上げると、お医者の先生はまっすぐにこちらを見ていた。ぎゅうと眉間に深く刻まれてもう消えない皺、筋肉の凹凸、年齢のわりにきれいだが、間近で見るとちゃんと毛穴がある肌。つよく角度の付いた美しい形の眉毛。皮肉ぶって片頬を上げて、整った鼻梁のむこうに精悍な法令線がくっきりと見える。恐ろしく長いまつげの奥に、すこし黄ばんだ白目が爛々と輝いて、瞳の色を際立たせていた。
とうてい死にそうには見えない。
「俺を長生きさせてぇならテメェが長生きしろ。まずは食え、あと寝ろ。適度に運動して酒は控えて医者の言うことはちゃんと聞け」
「保健指導?」
「そして二度と俺に真っ当なことを言わせるんじゃねぇ」
医者としてそれはどうなんだ、と思ったけど言う雰囲気ではないので口を噤んだ。満足そうに鼻を鳴らした男は中身の減ったペットボトルを取り上げてまだすこしめまいのする身体をゆっくりと抱えあげる。非常にゆっくりと。もしかしたら優しくと言い換えられるのかもしれない。
「寝ろ」
「やだ」
「ンでだよ」
「TETSUさん居なくなっちゃうし」
掃除をサボりまくってるので自分の匂いがやたらと染み付いてしまっているベッド、そこにそっと降ろされる。布団くらい干しとけばよかった。
「居てやるからちょっと寝ろ」
「ほんとに?」
「ああ。2時間くらいで起こしてやる」
布団をかけてくる手付きは柔らかい。その手を掴むけど、丁寧にほぐして布団の中にしまわれる。
「いい加減にしろ。一発打つぞ」
「ハイ……」
目を閉じたらまもなく睡魔が襲ってきたので注射はされずにすみました。
湿気と匂いの乗った少し重い空気を吸いながら目を覚ました。ぐぅとお腹がなる。漂ってきたのはそういう匂いだったのだ。
ダイニングキッチンから人の気配がする。のそのそ起き上がると、相手の方もそれに気づいたのかこちらへやってくる。コートを脱いだ軽装で、手に持った我が家のおぼんが放つ所帯っぽさがまったく似合っていない。
「メシだ」
「めし……」
サイドボードに置きっぱなしの本を避けて、水と薬と、湯気の立つ器が置かれる。お粥だった。くたくたの真っ白い米が輝いている。
「おかゆだ……」
「冷蔵庫に卵もねぇなんてどうなってんだこの家は」
「えっ、つくったの……? そんなことできたの?」
「俺のことなんだと思ってやがる」
動揺を隠せない私を見て「嫌なら食うな」と器ごと没収されそうになり「いるいるいりますください」と慌ててその手を引き止める。
手のひらの中にあたたかい料理がある。しかもTETSUが作ったものが。こんなの、想像すらしたこと無かった。感極まってほんのり泣いてすらいる。
「うれしい、ありがと……」
「……お前今までで一番喜んでるな」
「そりゃあね。そういうもんだよ」
「そういうもんか」
「そういうもんです」
そうか、ともう一回言って、沈黙が長引く前にTETSUはダイニングに戻ってテレビを付ける。私はベッドの上で、TETSU及び数は諸説あるがどうやらいっぱいいるらしいお米の神様に人生で一番感謝のこもった「いただきます」をした。

ごちそうさまの頃にはお腹がくちくなってうとうとしだして、慌てて薬を飲んで布団に潜り込む。そのまますこんと寝てしまい、目を覚ますと夜中だった。サイドボードに置いていたお皿はなくなっている。電気も消えていて、ダイニングに続く扉から明かりとテレビの音が漏れていた。
誰かが起きている間に自分だけ先に寝ているのって小さい頃を思い出す。
ダイニングでは、驚くべきことにTETSUが居た。当然みたいに居た。いつのまに持ち込んだのか点滴を吊るす棒をソファの近くに立てて、薬液の袋から伸びたチューブがソファに座る病人の腕に刺さっている。本人は目を閉じて動かず、ただ規則正しく胸が上下していた。眠っているのだ。
散らばっていた紙束と書籍は彼が少し整頓してくれたようで、周囲に可燃性の高い山脈を作っている。その上に、TETSUが来る前に散らかした体温計や絆創膏類が箱にきちんと収まって置かれている。テレビでは知らないタレントの深夜番組が流れていた。リモコンでぷちんとテレビを消すと、横の巨体が「ん」と身動ぎする。あんたのリモコンでもあったんかい。
「起こした?」
TETSUは「いや」と少しかすれた声で反射みたいに返事をした。
「熱は」
「まだ測ってない、けど大丈夫そう」
ソファに座って、箱から取り出した体温計を脇に挟む。彼は薬液の終わったそれを腕から抜いて、テキパキと始末をした。
「ごめんね、TETSUさんも体調よくないのに」
「いちいち謝るんじゃねぇよ。何度だ?」
ピピッと電子音が鳴った棒を取り出す。数値を見て「よぉし、大丈夫だな」とお医者さんは笑う。
「これもしかして体調悪いままだったらTETSUさんずっと居てくれる? あ、でもそっちも免疫下がってるからまずいか」
「調子戻りすぎだろ」
「だってTETSUさんがこんなに優しいのって……」
慣用表現で「はじめて」と言いそうになったけど、この人の概ね優しかったなと思い直す。
「久しぶりだもん」
「…………」
「ねぇ聞いてる? TETSUさんはいつも優しいね」
「うるせぇ何度も言うな」
返事がないと聞こえてないみたいじゃん。
TETSUはその日の朝出ていった。「じゃあな」と珍しく別れの言葉を言って。引き止めたがる私を「気が向いたら来てやる」と合鍵を見せながら制して。
また来るなら、と病み上がりの私はぼちぼちと部屋の掃除をして、冷蔵庫を整理した。また来るなら、とムダ毛も剃って全身つるつるすべすべふわふわに保湿もした。
また来るなら、と仕事も仕上げてスケジュールを見直した。
数カ月後のTETSUは私の肌を触って「ククク」と破顔した。
「気合は認めてやる」
「えっ、だめだった? ガチすぎ? 引く?」
「少しな」
「引いたか〜」
敗因は食卓が完璧に整いすぎてるとこかもしれない。プレースマットまで敷いてるし。頭を抱えていると、TETSUは「絶好調だな」となんだか満足そうににやついていた。
「確かにパン焼いたけどさ、でもちぎりパンだし……」
「なんでそこで罪一等減ぜると思うかね」
「このビーフシチューすごい美味しく出来てるし……」
「否定はしねェがな」
そうだよね、おいしいよね。西城に出入りしているときに習ったから料理は自信がある。キッチンにスツール持ち込んで仕事の合間に手間ひまかけて作ったビーフシチューは会心の出来であった。TETSUがいつ来訪するのかは不明なので、これは先日出来た名作を冷凍していたものだ。パンはTETSUが来た時たまたま作っていたところだった。しかもこの人が「貰い物だ」と上等なワインを持ってきたので図らずも完璧な食卓が出来上がってしまったのだ。
「TETSUさん、食事はきちんと摂れているの?」
この間まで不摂生を極めていた人間としては少し勇気のある問いだった。
あれからTETSUは何度か来たが、復帰最初に手料理を出した日に至極ゆっくりと、ゆっくりとだが全て、全て食べたこの人を見て私は大層後悔したのだ。弱りつつある優しくて強い人に無理をさせてしまったことに。あれ以来少し軽めに盛り付けることに彼も当然気付いていて、当然みたいな顔で完食していく。
「オメェが食わせてんだろ」
「残してもいいんだよ?」
「…………」
返事はせずに匙を口に運んだ。そこまで甘えてはくれないようだ。
食後、お盆にお皿を載せる私を制してTETSUがシンクに立つ。ソファでぼんやりテレビを見ていると、洗い物を終えた彼がドスンと隣に座った。反動で少しお尻が跳ねる。
ついでに甘えて肩にもたれかかると抵抗はなく、むしろ大きくて温かい手のひらがぐいと引き寄せてきた。
液晶の中では、最近売れてきた芸人がいかにも楽しげに声を張り上げて美味しそうな豪華フレンチを食べていた。
こちらはTETSUが顔を近づけてきて、わたしもすんなり目を閉じる。ちゅ、ちゅ、と小さく啄まれてまさにフレンチキッスだね。なんてね。おやじっぽさが感染したのかもしれない。
「は……」
我ながらとろとろに理性がとろけた顔を晒してしまう。TETSUは私の頬を撫でて、指先で首筋をなぞる。
「可哀想なやつだなぁお前は」
哀れみはお腹いっぱいだけど、彼に言われるならいつでもおかわりできた。
「そう?」
「俺なんぞに縋るなんて」
こういう時のTETSUは私の命を救ったこととか、二人で薄汚れた青春もどきを演じたこととか、いちゃいちゃ風の夜を過ごしたことなんて忘れているらしい。命を救った相手を前に卑下することは、相手共々見下げることなのにね。
何度好きだと言っても穴の空いたバケツからは漏れていく。それがこの人だ。
「TETSUさん、すき……」
それでも言わずにいられないのはなんでだろうね。
大きな手のひらが熱を持って私に触れる。雨みたいに降り注ぐ言葉がどれだけすり抜けようと、言わずに後悔するよりはずっとよかった。