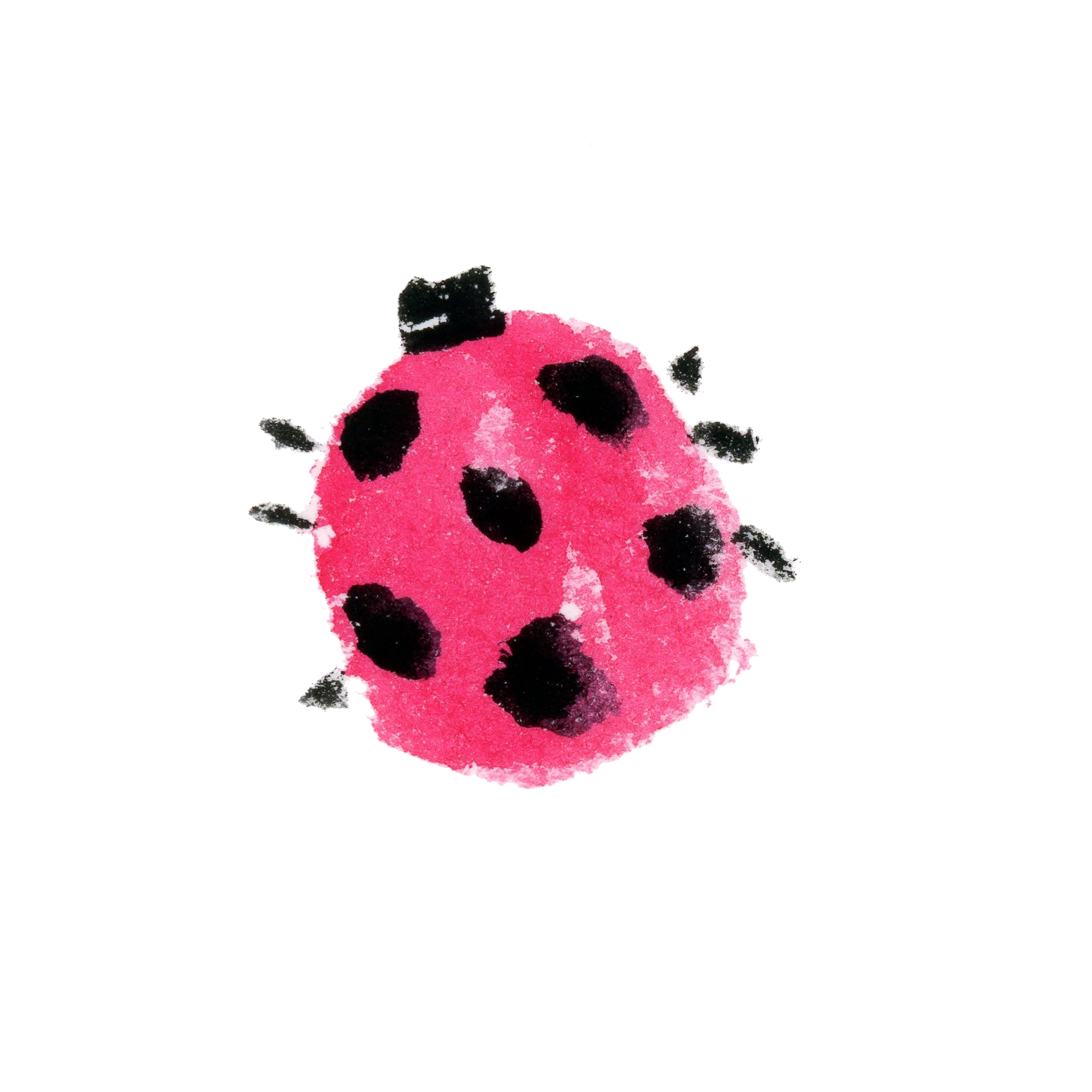
2-5
診療所は想像よりも山奥にあった。真田医院は郊外ではあってもそれなりに街に近かったが、この診療所がある場所は本当に辺鄙なところだ。建物自体はそれなりに拓けたところにあるけれど、そこに至るまでの山道は自然と徐行してしまうくらい細く曲がりくねっている。
エンジン音とライトに気づいたのかK先生は診療所から出てきて、車から降りる私達を出迎えた。
中学生にしてはずいぶんと大柄な一也くんではあるが、ドクターKも相変わらず見上げるほどに大きい。TETSUさんとそう変わらないのではないだろうか。切れ長の瞳は委縮してしまいそうなほど鋭いが、不思議と表情に険は無い。
「こんな時間まで大切なお子さんをお預かりしてしまい、申し訳ありません」
「頭を上げてください、あなたには責任のないことだ。おおかた一也が自分でついて行ったのでしょう」
「それでも……」
「それに、元を正せばドクターTETSUのはじめたことしょう」
「……そのドクターTETSUの話なんですが」
わかったうえであえて不躾に大人の会話に割り込んで、一也くんは手の中の資料を持ち上げる。
「見てほしいものがあるんです」
ここからは医者の領分だろう。TETSUももう私を要らないと言うし、私にできることはない。
医者たちからそっと離れようと、足を動かす。じり、と湿った土の上を重く靴が滑った。
「待ってください」
踵を返そうとする私の名を一也くんは呼ぶ。
「僕はあなたにも関係があることだと思う!」
振り返ると、まっすぐとした瞳の子供がこちらを見つめていた。
「ま、待って……私はその、TETSUさんの家族とかじゃないし……」
「ドクターTETSUにここまで関わっていて、ですか?」
「でもそれは……」
でもそれも今日までなのだ。TETSUは自分の命をドクターKに託すことに決めたのだから。そう言いかけて、子供相手に何言うつもりなんだろうと口ごもる。
「ここまで関わって、他人事で済ませるのは無責任だと思います」
「落ち着け、一也」
真っ直ぐで純粋な言葉の刃を抑えるように、この場で一番大人であるK先生が間に入った。「込み入った話になりそうですから、よろしければ中へ」と私を診療所に導く。喧嘩してるわけではないのに少し剣呑な雰囲気になりかけていたことに気づいて一也くんと二人でバツが悪く顔を見合わせる。ごめんねと思いながら情けない顔で微笑むと、一也くんも眉毛をハの字にしながら苦笑いした。私も先生みたいにちゃんとした大人を出来ていたら、ドクターTETSUともこんな終わり方せずに済んだのかな。
おずおずと踏み込んだ診療所の中は意外と広く、清潔な匂いがした。お医者さんの匂いだ。こうなる前はTETSUからもこんな匂いがしていた。勧められて、患者が座るような丸椅子に腰掛ける。
一也くんから受け取ったノートとカルテを見て、先生は眉をひそめる。
「スキルス性胃がんか。かなり進行しているな」
「僕はこのカルテの患者をどうしても救いたいんです」と、一也くんは言った。倫理と道徳から外れた医療の道を歩んだ男を、それでも生き延びて研究を続けてほしいと言う。
―――あぁ、これがTETSUさんが自分の命を託した人か。私はTETSUさんのことなんにもわかってないけど、この人は、この人たちはドクターTETSUと同じ世界を見て読み解くことができる。TETSUさんの死を未来に寄与する、意味のあるものにできるのだ。
私には光の医療も闇の医療もわかんないし、彼に生きろと言えるほど熟慮した強い説得力もない。
「このノートがどういう結末をむかえるのか…読んでみたいんです‼」
青少年の主張を受けて、K先生は口元に手を当ててたっぷりと考えた。
沈黙が診察室に溜まっていく。ややあって、切れ長の瞳がこちらを向いた。
「あなたはどう思われますか」
え、と、情けなく怯んだ声が出る。意見を求められるとは思っていなかったのだ。
「その……TETSUさん……ドクターTETSUが望んでるなら……私には何も……私の言うことなんか聞く人じゃないし……」
「ドクターTETSUの意思ではない。私はあなたの意思を聞いているのです」
「私の意思って……」
喉が渇く。視線が彷徨う。自分の手が震えているのがわかった。
「私の気持ちは、関係ないじゃないですか……」
うろつく視線の端で一也くんがなにか言いたげに口を開きかけたけど、やっぱり閉じた。
「どうして」
「だ、だって……」
いたたまれなくて俯く。直視したくない気持ちがすぐそこにある。逃げ続けてたけど、もう年貢の納め時だと先生の瞳が言っていた。年貢って。TETSUが貢いでくれた米みたいだね。
「TETSUさんが私に何も言ってくれないのは、私が理解できないからで……」
ちがうな、これじゃない。こんな話してない。こんな話をしたかったわけじゃない。混乱した脳が走馬灯みたいに思考のヒストリーを探る。
「―――私その、高校の時……あの……」
これも違う。過去のことなんか蒸し返しても意味がない。「ゆっくりで大丈夫ですよ」と、先生は低く穏やかに、落ち着かせるような声をかける。そういう雰囲気はKEI先生と似てて、少しホッとした。初めて会った時の彼女も、混乱する私をそうって落ち着けてくれたものだ。
「―――……覚悟してたつもりなんです。多分ろくな人生にならないって」
本当に話したかったことは、かなり遠目のスタート地点から始まった。でもこれがするべき話なんだって、すぐにわかった。
ここ以外で話すこともないだろう、でも大事なことだった。TETSUさんが私にKの話をしたように。一人じゃ抱えきれないくらいの気持ちは、いま以外のどこで零せるのか。
「けど、TETSUさんに会った時思ったんです、いままでの全部、TETSUさんに会うためだったんなら良かったなって」
ほんとは違っても、そう思って生きられたらステキだ。
自分のことは好きだ。KEI先生のことも好き。ほんとは世界中のことだってそんなに嫌いじゃない。それだけで完璧だったと思っていたのに、TETSUと過ごすのは楽しくてうれしくて気持ちよくて、いろんなことを塗り替えてしまうくらいめちゃくちゃで心地よかった。TETSUもほんの少しでもそう思ってくれたらいいなって、サンタさんに願うより強く祈った。
たった一人のために生きる人生は空虚だ。自分のためだけに生きる人生も、誰かのためだけに生きる人生も虚しい。でもTETSUさんと一緒に生きられたら楽しいだろうなぁ。二人で生きられたら、もしくは二人よりもっと多くのなにかを見られたら。もしそうならなくたって、その幻想だけでも抱けたら。きっと、その心地よさには人生をかける価値がある。
でもTETSUさんは、私をもう人生から切り離してしまった。もう彼と一緒に面白おかしくモラトリアムみたいな何でも無い時間を生きられない。テツさんは一足先に自分の人生のゴールを見つけちゃったから。はじまっていないものにも、ちゃんと終わりはあるんだね。
「大切なのであれば諦めてはいけない。」
「でも私、―――わたしは……」
それでも私は、TETSUさんがずっとドクターKから逃げ続けてくれたら良かったのにって思ってる。卑怯だけどこれが本心だ。二人で一緒に見なきゃいけないものから目をそらして逃げ続けたかった。でもやっぱりTETSUさんは私とは違うね。私の心のTETSUさんが座ってる場所、TETSUさんの心のなかではドクターKが座ってるんでしょう。ひとりだけずるいよ。死んだ人はあなたを受け入れないし、拒絶もしない。死はこの世界の何よりも確実で永遠だ。
ボニーとクライドにはなれない。
ロボとブランカにも。
どのみちどちらも願い下げだ。
嫌気がするほど身勝手。TETSUさんの気持ちなんて少しも慮ってない。
自分のこういうところには我ながらほとほと嫌気がさしている。KEI先生がだいぶ性根を叩き直してくれたけど、やっぱり私はこういうとこダメだね。
「生きてほしいという願いにあなたの立場は関係ない。それはすべての人間の持つ普遍的なものです」
その願いは特別なものではない。だからその願望を持つことに分不相応などというものは存在しない、と。それはあるいはそうであれ、という希望だったのかもしれない。ほとんど祝詞のようにつぶやかれた言葉は、泥濘に沈む思考を洗うように襲った。
「わたし……」
こんなこと彼に言うなんておかしいのかもしれない。だって本人にも言ってない。神様に祈ったことは口に出さないように。本当の望みも願いも欲しい物も、隠したほうがいいはずなのに。
「TETSUさんに生きててほしい。一緒に生きたい。もうそばにいられなくてもいいから」
いままでみたいに始まりも終わりもない時間を一緒に生きられなくてもいいから、同じ時代を生きててほしい。
「……どうしよう、テツさん死んじゃう……」
その時初めて、遅すぎる不安が胸を襲ったのだった。

黒須一也はいない。カリウムもモルヒネもない。ノートもカルテも……。
―――あいつも居ない。
さして驚きもしない。当然の末路だ。

一晩、診療所に泊まった。
泊まった、みたい。酩酊したあとみたいに記憶は無い。あのあと、泣き崩れてしまったわたしは先生たちに促されたのか、あるいはそのまま気を失ったのか。とにかくとても運転して帰宅なんてできないような状態になって、空いてるベッドに寝かせてもらったのだ。シャワーも浴びず、メイクも落としてない。おまけに涙で顔はぼろぼろだ。TETSUさんが少しでも綺麗だと思ってくれたらいいなと仕込んだアイメイクもひどい有様。
おずおずと起きて部屋から出ると、女性看護師さんと遭遇した。柔らかい黒髪に優しい眦の、知的な雰囲気の人だった。
「あら、大丈夫ですか?」
「だ、大丈夫です」
「冷やすものを持ってきますね」
彼女は気づかわしげな表情で、細い指で自分の瞳を指す。泣き腫らして酷い顔になっているのだろう。視界がいつもよりすこし狭いのもあって、まぶたの腫れぼったさは鏡を見ずとも分かった。
保冷剤をタオルに包んで持って来てくれた彼女にお礼を言い、まぶたを冷やす。
「すみません……」
いいのよ、と彼女は笑った。少し苦い笑みだ。
「……誰にも理解されなくていいんですよ、きっと」
聞き逃してもおかしくないほどさらりと告げられた言葉は、軽やかさを知らしめるみたいに鼓膜を揺らした。
綺麗な笑顔の人だなぁとぼんやり見つめ返すと、すこし気まずそうな笑顔が返ってくる。
「そう、ですよね……」
最初はただ空気を流すための同調だったけど。彼女の瞳を見ていると自然ともう一度同じ気持ちが押し寄せてくる。「そうだよね……」。
彼女は返事の代わりに、長いまつげを震わせて目じりを下げる。
「彼が、じゃない。私に彼が必要なの。……生きててほしいよ。」
彼の理想に殉じたら、あの人死んでしまうんだし。
テツさんが求めていなくても、私テツさんに生きてほしい。次の喧嘩をするのなら議題はこれだ。
あなたもし自分が生きられるってわかってとして、はたして死に急いでいられるの?

「手立てはあります」
K先生がそう言ったので、シャワーを浴びて昨晩ぶりに先生に謝罪を述べてこざっぱりしたわたしは呆然とした。
おとぎ話みたいな願望はあっけなく目の前に提示されていた。世界のどこかでなにかをやった人が、現実を理想に近づけたのだろう。
「で、も、癌のステージ後半……なんですよね?」
「ええ、それも難易度の高い症例です」
ですが、と先生が解説してくれた術式はすばらしくわかりやすく、医学素人の私にも筋道は理解できた。
「とはいえ、完治する可能性は高いとは言えない。年齢も考慮すると、寛解する前に天寿へ至る可能性もあります」
服の裾を子供みたいに握りしめて、自分の手の甲を見ながらその声を聞いていた。
「ですがこの方法なら『闘病』が出来ます。安楽死や、ゆるやかに経過を見守るホスピスとは違う手段です」
先生がこの話を私にした理由はわかる。「身内」と見なしてくれているのだ。言葉の約束も法的根拠もなく、ただシチュエーションでそう扱うと決めてくれたのだ。今更「なんで」なんて野暮なことは言わない。最終的な判断するのは当人であるTETSUだけど、それでも先生は私を関係者にしてくれたのだから。
麻上看護師や富永先生に礼を言って、わたしは車のエンジンをかける。横には先生、後部座席には一也くんと手術に即して用意してくれた必要物品たちを乗せて。
K先生たちがオペをするという話に、TETSUはひどく狼狽し抵抗した。全員身長180cm超えのでかい男三人で言い争われると、自然と壁側に退避してしまう。ジュラシックパークみたいだった。言い争いというか、TETSUがあしらわれてるだけだったが。この人一番年上なのに。
ふたりのKが去り、Tと私だけが残された。
彼はそこで漸く私を見た。
「―――……泣きすぎだろうがよ」
診療所へ行く以前も以後も、何度も泣いて真っ赤に腫れ上がったまぶたを見て不意をつかれたのだろう。仕方のないやつだと言わんばかりに苦笑する。
「……消えろと言ったはずだ」
「私あなたの何でもないから、従う理由がないもの」
どすん、と崩れ落ちるようにTETSUはベッドに座る。私も隣に座る。TETSUは日焼けしてひび割れた壁を見ていて、私もそれを見る。遠くで先生たちが準備をしている気配がした。彼が受けるべき術前の処置もあるはずだけど、多分二人はその前に私達に少しだけ時間をくれたのだ。
昨晩まではあんなにゆるやかな絶望だったのに、先生や麻上看護師たちに出会ってからまるで風向きが変わったように感じる。廃病院の暗さも、TETSUの病状もなにも変わらないのに。本当に不思議だ。
TETSUはゆっくり、ゆっくりと身体を折り曲げた。膝に肘をついて、両手で顔を覆う。ふー、と疲れたように深い溜め息をついた。しょぼくれいてる。病のせいで憔悴しているし、頼みの一也くんにあなたのKではないと告げられたことも、牙を折るのに十分なことだったのだろう。
「Kェとはよ……」
ぽつりと、大きな体に似合わないくらい小さくて繊細そうな声だった。
「……ダチみてェな、もんだったんだぜ」
すこし躊躇いながら心のある単語を口にした。この人が誰かと温度を感じる関係性について話すのは初めて聞いた。
それは寂しいね、と思うけど、口には出さずに丸められた肩に凭れ掛かる。丸まった背中がぴくりと少し揺れた。
「TETSUさんがいないとさびしいよ……」
驚くほど小さく掠れた声が出て、ほとんど聞こえないかもしれなかった。それじゃだめだなって、いまはもうわかってる。咳払いをして、緊張で震えたまま強張った口を動かす。
「TETSUさんが生きてくれないと寂しい」
今度ははっきりと、ぼろぼろの廃墟に私の声が響いた。好きとかヤりたいとかよりも口にするのが断然怖かった。喉がカラカラだ。はりきりすぎて先生たちまで聞こえたかもしれない。
「……どのみち俺は、そう長くねぇんだよ。年齢考えろ。算数くらいできるだろ」
「そこが困りどころなんだよね」
顔を上げて彼の腕にしがみつく。むき出しの上腕なんとか筋は服越しでもすこし温かい。
生きてる。
「後悔することになるぜ」
「後悔ならもうしてる」
左側から見上げると、TETSUさんの左目がよく見える。そうだ、こういう色をしていたんだった。微かな光を吸い込んで少年みたいにキラキラ光ってゆれている。元の鋭さと狂気を残しながら加齢で少し目尻の下がった、茶色い瞳。
「なんでもっとはやく会わなかったんだろうってずっと後悔してる。だってどんなにがんばってもTETSUさんとはもうあんまり同じ時間を生きられないんだよ……」
120歳くらいまで生きてくれなきゃやだ……。と泣きつくと「そりゃ無理な相談だな……」と困ったように笑った。
「……お前やっぱ遺産が惜しくなったのか?」
「いらないよ。お金で傍に居た女にしないで」
この雰囲気でそれ言う? この男ホントこういうとこあるよな。意地悪そうにクツクツ肩を震わせる病人に思いっきり肩パンしてしまった。TETSUはそれでも笑ってた。

ややあって一也くんがやってきて、術前準備のために彼を連れて行く。
長い時間が……とはいえ数えられる程度に何時間と、経って、病室で頭を抱えていた私の鼓膜にガラガラとストレッチャーの音が響く。
うつ伏せていた寝台から顔をあげると、先生は一言告げた。
「手術は成功です」
それを聞いて自分の目からまたぼろぼろと涙が流れていることに我ながら驚く。まだ泣けるのか私。そろそろ干からびるかも。
TETSUはまだ麻酔が効いて眠り姫で、その身体を大柄な先生達がそっとベッドへ移乗させた。
触れた手の内で、手首の脈がゆっくりと揺れている。
自分より少し高い体温、倍は大きい手首と手のひら。節くれだって少しカサついた指先、ところどころ横線状にくぼんだ、爪半月の狭い切りそろえられた青白い爪。乾燥して白く厚くなったさかむけ。
なんどもしゃくり上げて言い損ねて、すうーと息を吸って漸く単語が唇から正しく発音できた。
「ありがとう、ございます……」
なにかあれば別室にいますので、と言いつけて先生方は片付けや後処理のため病室を出ていく。
壊れたブラインド越しに、窓の外で揺れる木陰を月が照らしている。TETSUの鼻梁に前髪の影が差して、表情を変えて見せた。
すう、と静かな寝息だけが部屋に響いている。息をする度に胸が膨らんではへこむ。生命力が規則正しく律動している。鼻腔が少し広がったり萎んだりしていた。長いまつげは少しも動いていない。夢すら見ていないのかもしれない。
このときだけはさすがのTETSUさんも私だけのTETSUさんだな、と思いつつ、いややっぱりそんなことないやと頭を振る。このTETSUさんはK先生に延命されたTETSUさんで、そもそもかつてのドクターKという楔を深く心に残したTETSUさんだ。私だけを心の椅子に座らせるTETSUさんって想像付かないしちょっと嫌だね。
胸に頬を寄せると、柔らかく心臓の音がした。
体温、匂い、鼓動。質感、声と重み。離れたときに最初に忘れるのってどれなんだろうな。
「ごめんね」
掛布を肩までかけ直して、ベッドの脇から立ち上がる。
私に医療の心得があったなら、勿論どうあれ私なのでTETSU相手に執刀なんてできたもんじゃなかっただろうけど、彼のノートの意味くらい理解できたし、似たような視点で世界を見ることもできたかもしれない。あるいは深い慈愛と優しさがあったら、低いところに流れ落ちるように死へ向かう重篤患者を受け止めて、発破をかけて心を守ることができたかもしれない。もっと素直で真っ当な人間であったら、正しさを行使してこうあるべきだとこの人を諭せたかもしれない。無理矢理にでも病院かなにかにつっこんで、体力を温存させるべきだった。どうせそこから彼が逃げ出すとわかっていても。
強力な正義感は痛くても正しいんだって、その姿勢はK先生が見せてくれた。
人と人が交流してああも強靭でぶれない選択を見せられたら、二人でいたら現状維持どころか刻一刻と膿んでいくみたいな関係しかつくれない私とTETSUは間違いだってわかる。このどうしようもない前科何犯かわからない男に生きてほしいと祈るなら、相応の姿勢を取るべきだったのだ。私もKEI先生からそうやって救われた側の人間である。拒絶されるとわかっていても、正しい道を選ぶべきだった。もう遅いけど。
だからTETSUさんのそばにいるべき人は私じゃないし、TETSUさんは私のそばにいるべきじゃない。
「TETSUさんの大事な時間を無駄にしてごめん」
私じゃ駄目だよね。
誰に聞かれても、本人に聞かれてもいいと思った。心からの謝罪だった。

一也が目覚めると、ドクターTETSUはいなかった。あの人も。
ドクターTETSUの知人女性。一也からしたら友人とか恋人とかそういう聞き慣れた関係性に見えるが、本人たちが違うというのだから違うのだろう。大人って難しい。昨晩遅くに出ていったのだと、K先生は言った。
「引き止めなかったんですか?」
驚いて尋ねると、「オレに色恋の機微がわかると思うか?」と冗談めかしていった。もしかして冗談だったのかもしれない。
ひと月後、角形2号の分厚い封筒が診療所に届いた。
差出人の名はない。丸の中に「T」とだけ書かれたサインが、なによりも明確に送り主を表していた。
それを見て思い出したのはあの夜だ。違法な研究と闇の施術ばかりが載ったドクターTETSUのノート、そのうち一冊を開いた時にひらひらと揺れて落ちたのは、挟まれていた薄いメモ紙だった。あの紙片に書かれていたTには、触角と黒い丸が足してあって子供の描くてんとう虫みたいだった。
戯れ合いみたいな落書きの紙片をそれでも彼は捨てなかったのだ。
捨てなかったのだ。