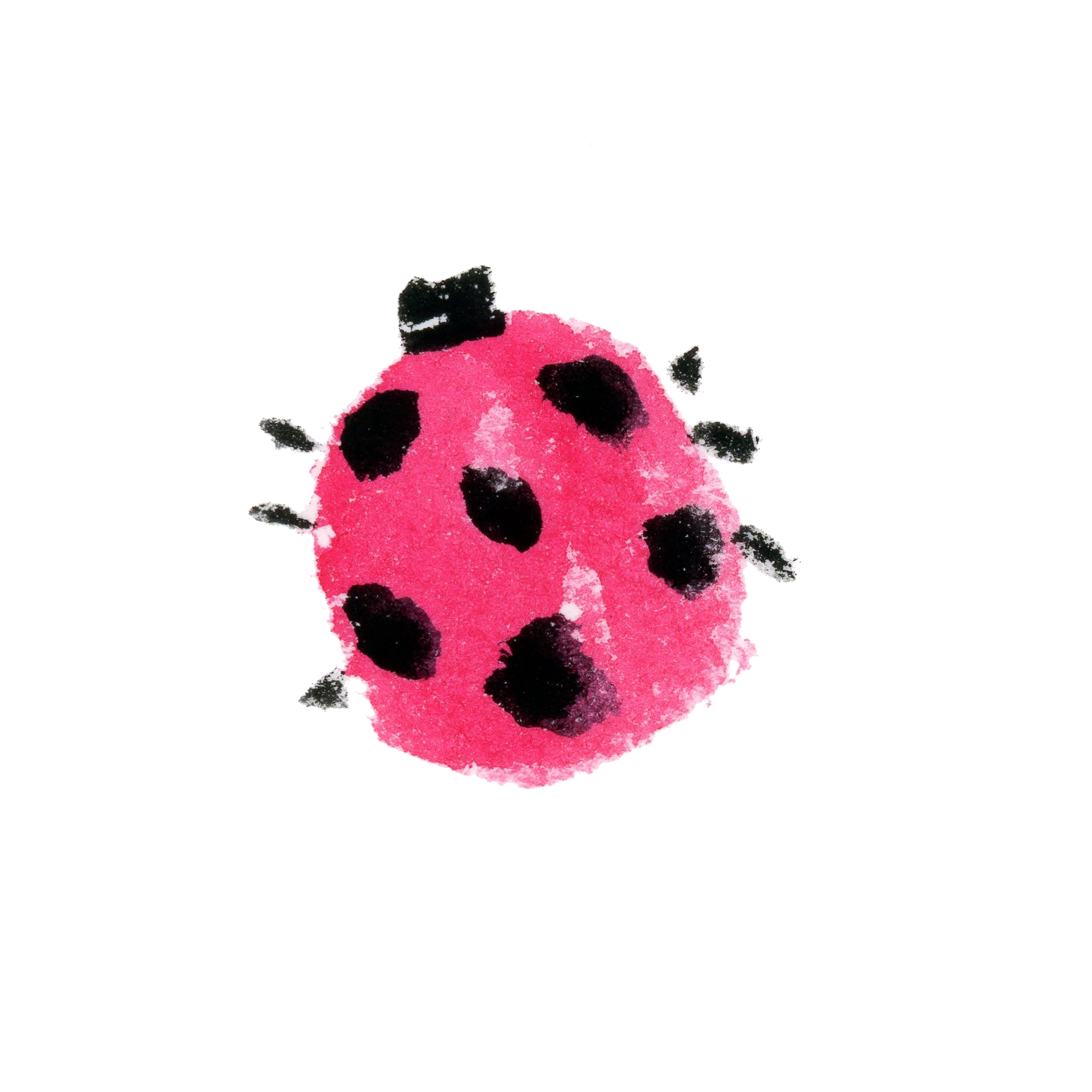
2-4
そばにいても良いという許しを得たが、TETSUが生き方を変える気になったわけではない。相変わらず病に取り憑かれていて、抗うような姿は見られない。出会った頃はあんなに元気だった人が、見る影もなく日に日に憔悴していく。食事も碌に食べないし、あまり眠れていない様子。あんまり干渉するとまたまたどこかに消えてしまいそうで、そうなったらもう二度と見つけることはできないだろう。KEI先生にカルテを持っていこうとしたけど、それも見つかって止められた。
そう、そのときに初めて「抱かれた」のだけれど、あれはセックスというよりはTETSUの自傷に近く、お互いうっすら傷ついて終わった。彼のほうだって「抱いた」とは思ってないだろう。ゴムがないからかなのか挿入まではいかなかったし、それでも気持ちよくはあったけど、双方の身体を使った自慰行為みたいで虚しかった。推定がん細胞でずたずたの身体で性行為のリスクなんてTETSUのほうがよくわかってるだろう。彼の触れ方がとにかく優しかったらいっそうつらくて、私がちょっと傷ついたことでTETSUも傷ついたのか、あるいは「アルコール、タバコ、ジャンクフード」と並び目に見えてやさぐれるためにそんな手段に出た自分がショックだったのか。とにかくいまの自分たちはそういうのではないのだと確認してしまったので、それ以降一度も彼とそういうことはしていない。
どん詰まりだ。TETSUは自分の病状のことよりも思い出の中のKに夢中。しかたあるまい、この人の一番若く美しくどうしようもなく輝いていてどうしようもなくどうしようもなかった頃は、ドクターKとともにある。彼の心を持ち去って、ドクターKはそのまま死んでしまったのだ。そして今この人は私の心を奪ったまま、Kのもとに行こうとしている。
問うに落ちず語るに落ちるとはこのことで、あれだけ聞いても教えてくれなかったKの話を、彼はおとぎ話がなにかのように語りだすようになった。失伝したくなかったのだ。
「あいつの……」
隙間風と闇だけが流れ込む病室の固い寝台。埃っぽいのは嫌だから私が洗ったシーツと毛布に包まる。黒くて長いまつげの奥で薄い色の瞳が輝いている。私じゃない何かしか見ないそれに向きあうのがつらくて、胸板に頭をすりつける。においとぬくもり。それから心音。じゃれてくる犬を撫でるように大きな手が髪を梳く。頭上でかすれた声がつぶやく。
「あいつにはクローンがいる。無事生きてたらいまは中学生か……」
ドクターKまわりの荒唐無稽っぷりは正直半信半疑が止まらないのだけど、否定してもしょうがないから聞き流している。いまのTETSUはKとの記憶を現世にとどめているだけの外部装置だ。自分の研究をノートに書き留めて残すように、Kとの思い出を脳に書き留めて反芻する。壊れるまで。生への渇望はそのためだけに残されていて、私のことなんて記憶を投影するスクリーンとしか思ってないだろう。
「あいつの……KAZUYAの、クローン……」
唇の中で咀嚼するみたいに、もう一度彼がその名を呼ぶ。
ぱちんと、間違ったピースがはまる音がした。

「おめェ遺産要るか?」
「いらなーい」
なんていう会話をした翌日だった。死ぬなよって思ったし闇医者の遺すものって具体的になに怖〜、とドン引いたので断ったのだ。ハマーはちょっと欲しいかも。いややっぱ要らない私も愛車あるし。あんなでかい車、即擦る自信ある。あの大食らいハマーちゃんの維持費どんだけかかるんだろうね。税金高そ~。
そんな事考えながらヤサに行ったら知らない男が居た。
「えっ」
「ま、待ってください! 怪しいものじゃないんです!」
富山の一件が普通にトラウマ気味な私は近くにある武器っぽいもの(期限切れの消火器)を掴んだが、制止する声音が意外に幼く丸くて困惑した。見た目以外はまだ子供だ。よくみたら学生服。
「僕はドクターTETSUに呼ばれて……あの、関係者の方ですか?」
まさかな、という気持ちが視線に乗りすぎている。どうしてみんな私とTETSUがつるんでると信じられないみたいな顔するんだろう。
「ちょっとした知り合いです。……あなたは?」
「僕は黒須……」
「待って、こういうとこで会った他人に名前とか教えちゃだめだから!」
こういうとこで会った他人に翌日のこのこ会いに行った人間なのでどの口が言うんだといった内容だったが、そのあとちゃんと二人で拉致監禁されてるので少なくとも実感はこもっていたはずだ。少年はぐ、と口を噤む。素直だね。
「TETSUさんは?」
「いまは検査の後寝ています。……スキルス性胃がん、それもかなり悪いです」
「そう……」
TETSUがどうして自分で検査をしないのかと言うと、お腹に外科的アプローチをする必要があったから、らしい。本人が言っていた。自分で自分の腹を捌くなんてブラック・ジャック先生みたいなマネ、よほどの緊急事態じゃないとリスクでしかない。この場にはTETSUと目の前の彼だけ。KEI先生に聞いたばかりの継承の神話。007が殺しの番号なら、Kの名は医神を表す。
「あなたもKなの?」
「僕は……」
少年は少し狼狽して、瞳を伏せた。こうしてみると、図体ばかりでかいただの子供だ。
「……いえ、当代のKは僕じゃありません」
「そう」
であればいずれ継ぐのか。KEI先生のところにいたあのマントの大男がいまのドクターKだとは聞いているけれど、血縁であるというKEI先生含めてKってのは全員でかいんだね。ドクターKの子供にしては少し大きすぎる気もする。弟とかかな。ていうかドクターKって一子相伝?
「ドクターTETSUがなんのために僕を呼んだかはご存知ですか?」
「え?」
検査と、なにかわからないけどなにか神がかり的な施術のためなんじゃないのか。私の表情を見て、彼は悲しげな瞳をした。
「……なにも聞いてないんですね」
「ごめん、私医療関係者じゃないから……」
医学も薬学もちんぷんかんぷんだ。
TETSUはああみえてかなり説明上手なので必要なことは丁寧に教えてくれるが、医療知識は門外漢の私には、メディカルな話など殆どしないし必要ない。じゃあなんの話ししてるのって尋ねられると、基本的に益体もない話しかしてない。四川風麻婆の「風」の部分が持つ甘えについてとか。そういう話しか。
「……僕は、ドクターTETSUを安楽死させるために呼ばれました」
はい。暗転。

そして明転。
「大丈夫ですか!?」
「え、あ、ううん、大丈夫」
地震かと思ったけど揺れたのは私だけだったらしい。ごめんね、と余りある反射神経で咄嗟に支えてくれたらしい少年に礼を言って離れる。私みたいなやましいところしかない人間がこんな真っ当そうな子供に触れるのはなんかの罪状が付きそうだ。客観的に見ればどうみても動揺しているか弱い女性って感じですごくはずかしい。弱ぶるのって一瞬で被害者になれるとこが嫌いだけど、いまは本当に動揺と動転で視界がぐるぐるしていて、地動説も天動説も嘘かもしれないってほどだ。本当は世界は回ってなんかいなくて、私一人がから回ってるいのかもしれない。
「どうしてっ―――……いえ、ごめんなさい」
情けなく裏返った声が出て咳払いする。どうしてなんて決まっている。TETSUは自分の人生の結末を決めただけだ。
当然、私は彼の門の外なのでその決断もこの少年にそれを託す理由も、私になにも教えてくれなかったことにも文句など言えない。考えないようにしていたのだ、TETSUが闘病もホスピスも温かいベッドも畳の上も拒否してこの寂しい場所で私とともにだらだらと時を浪費する理由を。時間は有限で、彼の持つそれはとても短いはずなのに。目をそらしていた結果がこれだ。間違え方が元彼と別れたときとおんなじ。後悔はそんなものよりももっとずっと深くて、いかにも私らしくて納得した。
「あなたはどうするの? そもそもあなたいくつ?」
「中学三年生です」
彼は答えづらい質問を飛ばして、明確な答えのあるほうだけ返答した。それだって私には十分ショックで、あの人、十五歳かそこらの少年に自分を殺させようとしてるなんて。そんな。どうして。いったい何を。愚問ばかりが頭を占めていく。
「あの人のノートです。いままでの研究や施術の記録が書かれています」
少年が差し出したのは、よく彼が書き付けているやつだ。覗き込んでも隠さないけど、変わりになんの意味もわからない。人体の図解を見て医者って絵もうまいんだなって思ったり、意外と字がきれいだなって思ったりするだけ。
開かれたのは「安楽死」について書かれたページだ。
「僕は……」
彼は何度かためらって口を閉じる。
「僕はドクターTETSUに」
生きて欲しい。と言った。確かに言った。
あの男に命を託された少年は。
「…………TETSUさんは死にたがってるのに?」
ひどく意地悪な言葉がどこから来たのか考えたくなかった。嫉妬も憐れみも同情も等しく醜くて無価値なのに。
彼は決まりきった答えみたいにためらいなく唇を動かす。「認めません」。口にした言葉をもういちどなぞって確かめるみたいに、喉を震わせる。
「僕は認めません」
見上げた顔立ちは相変わらずあどけない。
人生のことはきっと私のほうが知っている。TETSUのことも、もしかしたら私のほうがまだわかるのかもしれない。でもこの人はTETSUの気持ちを慮ったりしない。忖度もない。理解する必要はないのだ。生きるか死ぬかの二択の答えは明確で、生きたいと死にたいの天秤のどちらに加担するかは既に熟慮しているのだから。
人の魂には等しく美しく価値があると、そう心から信じている瞳だった。
案内された部屋で、麻酔の効いたTETSUはひどく魘されていた。うわ言が何度もひとつの名を呼ぶ。「K」と。聞いていられない。そのうちにハッと起き上がった彼が目の前の少年を見たときの瞳。
その瞳に、私は映らない。
中学生に自分を殺させたい男と、医者じゃないのに検査はする少年が目の前で言い争っている。ふたりとも狂ってる。けど止められない私にそれを指摘する権利はなかった。真人間の第三者がほしい。野次とか飛ばして欲しい。野党とかね。
問答の末に決心した顔で子供が部屋を出ていく。その時になって、ようやく彼は私の存在に気づいたようだった。TETSUは何も言わず、私はなにも言えなかった。しばらくして絞り出せたのは相変わらず可愛げのない憎まれ口だ。
「自分が何をしようとしてるかわかってるの?」
「―――睡眠薬投与後、カリウムを静脈注射し……」
「そうじゃない、中学生に人殺しをさせようとしてるんだよ」
「だから何だ。あいつはKになる男だ」
「あなた……あなた子供好きのくせに!!」
感情のギアを上げないように必死。だけどギリギリ振り落とされそう。知ってるんだから、どれだけあなたのこと見つめたと思ってるの。園児のお散歩を下校中の小学生を部活帰りのジャージ達を、あなた自分がどんな瞳で見ていたのか知らないでしょ。知らないんだから伝わらないか。ここでヒートアップしても仕方ない。一言話すたびに彼が遠くなっていくのがわかる。無理だ、終わる。今度こそ。この人のことを見つけられなくなる。
「医者はいつか死という壁にぶつかる。オレは、まだ死を知らねェKの最初の『死』になる」
「そんなのわかんない」
「お前にわかってもらいたいわけじゃねえ」
「わかんないよ……」
これ以上は泣いてしまう。縋るように問いただしちゃうよ。彼が一番大事にしているKすら憎みながら。あんたのクローンでさえなかったら、彼はあの子供にそんなことさせようとしなかったはずだ。それがどうしてこんなことになってしまったのか。わからない。おしえて、わかんないけど。それでも私になにを伝えたくて、なにを伝えていないのか。そんな、言わないようにしてた沢山の言葉をぶつけて、最後には全部を失うだろう。そうなる前に背中を向けた。
「責任取ってやるつもりだったがな……。お前の人生を巻き込んじまった分くらいは。」
だから、そう言った時のTETSUの顔はわからない。「もう時間切れだ」と呟く声音はゆったりと穏やかで、もしかしてこの人、本当はこんなふうに話す人間だったのかもしれない。
「結局お前も、俺には相応しくないんだろう」
ちいさく呟かれた言葉の意味を測りかねて、二の句が継げない。声の温度はやたらと温い。待って、今なにを言おうとしているの?
「……さっさとオレの人生から消えな」
そう響いた言葉はさっきとは打って変わって硬質で、冷たかった。

「こんな時間までごめんなさいね。送るよ、とりあえずお家に電話しといで」
自分なりに気を使ってドクターTETSUと彼女を二人きりにしたけれど、彼女は意外とすぐに部屋から出てきた。
ドクターTETSUと関係のありそうな彼女は、普通の女性だった。何を持って普通とするのかは時と場合によるが、少なくとも一也は彼女が街中の交差点で信号待ちしていても見つけられないかもしれなかった。今後見つけられるように特筆して特徴のある部分を探すと、まろやかに下がった眉尻と眼尻の出す柔和そうな雰囲気は印象的だったかもしれない。見た目で人を判断すべきではないと重々わかっているが、とても闇医者と関わりがあるような人間には見えない。
「自己紹介、まだだったね」
一也が公衆電話で診療所に連絡を入れたあと彼女の車に乗り込むと、すっと名刺が差し出された。そのときに初めて彼女の名前と職業を知った。「作家」と印字された下に見覚えのある名前が刷られている。道徳の授業で先生が用意したプリントに、一部抜粋で短編が載っていたのを見たことがあった。 学級文庫にも置いてあったから、先生がファンだったのだろう。
「本名ですか?」
「違うよ」
「わぁ、あの、僕、道徳のプリントで読みました!」
どうとくのプリント、と牧歌的な響きをぽかんとしながら口ずさんだあと、ふふ、と笑った。困ったみたいなハの字眉で笑う人だった。「好きな方で呼んでね」と教えてくれた響きは本名なんだろう。筆名のほうが似合っていて、きっと彼女は自分にふさわしい名前を自分でつけたのだ。
車が動き出すと、見知らぬ大人の運転する車の助手席に乗っていることを自覚してにわかに緊張する。それを敏感に感じ取ったのか、彼女はさりげなく授業のことや学校のことを質問して、一也の返事を待ってはゆっくりと会話を広げた。少し前と打って変わっておだやかな時間がしばらく流れて、一時は状況を忘れさせたが、車が山道に差し掛かり、村への細い山道を辿っていくと、今度は運転手のほうが少しずつ緊張しているようだった。
「あの、K先生は多分怒ってはないですよ」
「そうじゃないの、大人には責任ってものがあるのよ」
子供を巻き込んでいい話じゃなかった、と言う彼女に一也は自分から巻き込まれに行ったと答えると、困ったような顔をする。
「君がそう認識しててもねぇ……」
「ドクターTETSUのことであなたが責任を感じる必要はないと思います」
「…………」
彼女をかばったつもりだったが、難しい顔をして黙りこんでしまった。沈黙が気まずくなる前に彼女のほうが口を開く。
「一也くんは西城病院のKEI先生の親戚にあたるの?」
「KEIさん、ご存知なんですか?」
「かかりつけなんだ」
「僕はそのKEIさんの……甥に当たります」
嘘ではない。ただ秘密にしただけだ、遺伝子上兄であると。そのかすかな感情のゆらぎを気づいた上で無視するように彼女は「素敵なおばさまで羨ましい」とあえてはしゃいだような明るい声音を出した。
「怒るとめっちゃ怖いけど」
「怒らせたことあるんですか?」
「いっぱいある……」
僕はKEI先生を怒らせたことはないけど、たしかに怖そうだった。
「じゃああの、当代のK先生も親戚?」
「遠縁には当たるみたいなんですが、僕も知ったのは小学校の時で」
「あ、ごめん。肉親の話とか結構突っ込んだこと聞いたよね」
家系の複雑さが匂ってしまった返答に慌てた謝罪を受ける。たしかに複雑だが、自分の出生よりはよほど口にしやすいそれを思うと、家族の話が苦手なのは僕じゃなくて彼女なんだろうと気付く。
「K先生は……先生なら、TETSUさんのこと、どうにかできる?」
「……そうだったらいいと思います。僕よりもずっと知識も技術もある人です」
「そう……」
あくまで楽観視できない状況を、複雑そうな顔で受け止める。
「だったらいいな、って、私も思う」
ドクターKにすら救いようがなかったらTETSUさんがあまりにも可哀想だね、と寂しさを取り繕って少しはにかむ彼女に、僕は何も言えなかったし、「あなたもドクターTETSUを救いたかったのか」なんてとても聞けない。