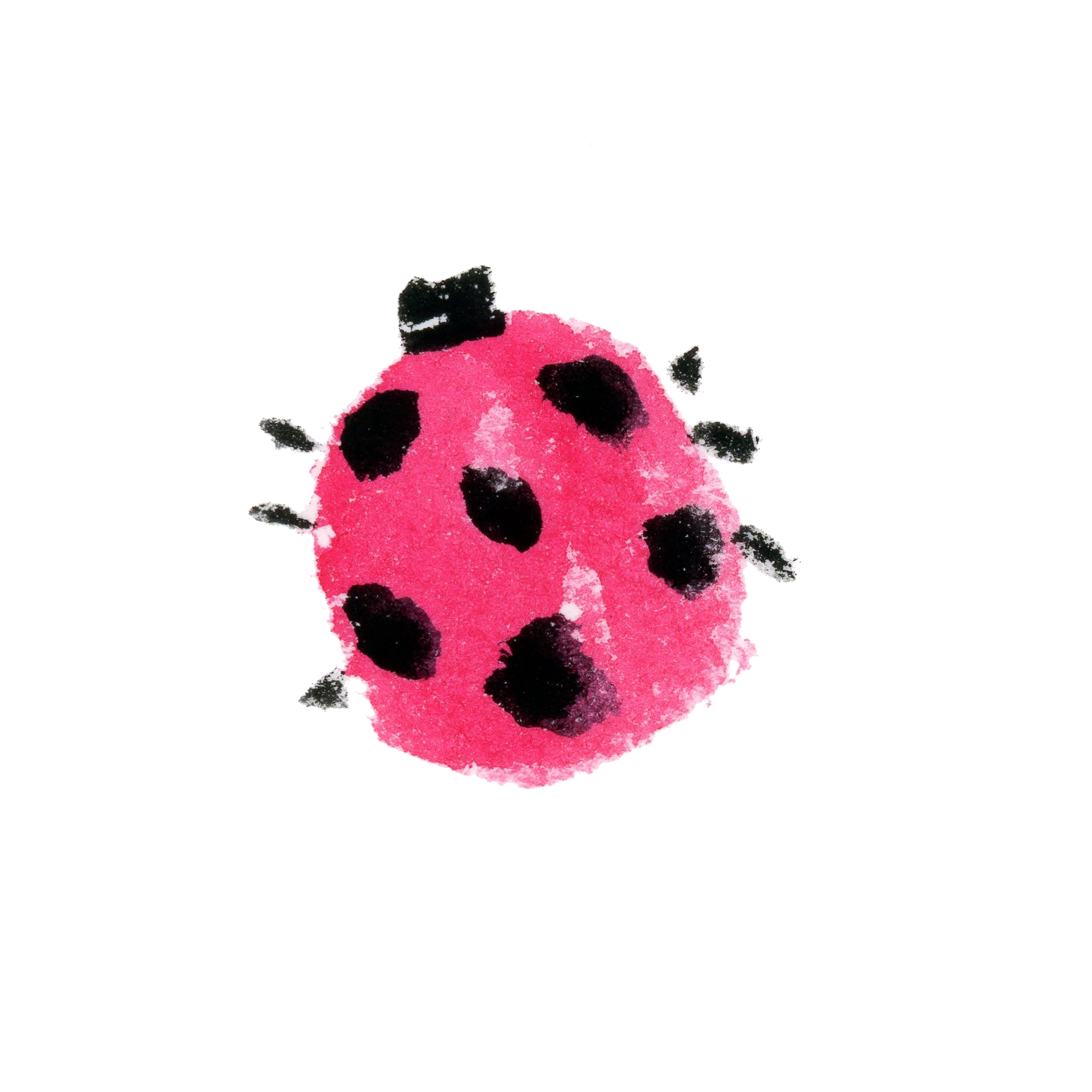
2-3
病院の廃業情報を新旧問わず調べて片っ端から様子を探る。基本的には明るい時間、たまに夜も。どう考えても不法侵入だし、TETSU以外のなにかとエンカウントする可能性もあり大危険だけど、これ以外の手段は思いつかなかった。捜査の基本は足である。
こんな泥臭くて不確実で手間がかかって滅法危険な橋渡るってわかってたら流石のKEI先生も先に止めてただろうから、彼女には内緒。あの人私の能力高めに見積もってるからなぁ……。
知ってるアジトは何周か巡ったが、寄り付いた気配は感じなかった。
この時期ばかりは他人に趣味を聞かれときに「廃病院めぐり」と答えるしかなかっただろう。何度か薄らやばい目にも遭いそうになりつつスレスレで回避して、十数軒目かの廃病院。夕方から巡って本日3件目。なんでも跡継ぎがいなくなって相続も曖昧になり、放置された病院跡に、彼は居た。紛れもなく。愛車がその近所に停められていたのが決め手。絶対にここだと確信して20時の闇をすり抜けて建物の中に入る。外見も荒れていたが、中身はもっと荒れていた。もうほとんど外だ。日中に限って言えば、屋根が光を遮る分外よりも寒いのかもしれない。
「…………あのー」
控えめに出した声がリノリウムに反響する。懐中電灯で探し当てた壁のスイッチを押すと、パッと蛍光灯がついた。ほとんど割れているか切れているかしているせいで薄暗い明かりだったけど、確かに通電している。それだけ確認してロビーの電気を消した。
「て、TETSUさーん……?」
十何件探したとしても、人の気配がすることは稀なので全然場数が踏めてない。今回はかなり確証があるけど、TETSUと同じ車に乗った別の不審者だったらどうしよう。別の闇医者とかさ。
診察室の扉に手をかけてゆっくりと開く。懐中電灯で差し込んだ光の中に人影がまじり、探していたもののはずなのにびくりと身体がはねた。
埃っぽい部屋の中、古ぼけたソファに横たわったTETSUには彼を探す私の情けない声が届いていたのか。私を見ても驚きはせず、鬱陶しそうに片目を開いた。煩わしげというよりは、元気がなくて億劫そうだ。
「……てめぇ、なぜここが」
心配に感謝してほしかった訳では無いだけど、あんまりな口ぶりにこっちも気丈に振る舞ってしまう。ほんとは顔が見れて震えるほど嬉しい。
「あんな姿見てから消えたら誰だって心配するよ」
「心配? お笑い草だろう」
人を笑うためにこんなことまで探しに来たりするわけないでしょそこまで暇じゃないよ。と、思ったけど。それを言う前に、あからさまに置かれたコンビニっぽいゴミやアルコール飲料の缶、ぐしゃりとタバコの潰された灰皿が目に入る。タバコなんて吸ってなかったでしょ。体臭やキスの味でわかるよ。やさぐれ方があからさま過ぎて、なんかもう、そういうところが。
「うちに髭剃り置きっぱなしなんだけど……」
言うべきことは絶対それじゃなくて、でもなんて言っていいかわからない。もともと口やかましいタイプじゃなかったはすけど、TETSUといるととにかく調子が狂う。「捨てりゃあいいだろ」と至極当然なことを言ってTETSUは手で追い払う仕草をする。ワンコ相手にする仕草みたいでちょっとムカついた。
「……どうしたの? らしくないですよ」
「お前にオレらしさなんざわかるわけねぇだろ」
「それは……」
それはそうだね。
TETSUのことなんてほとんど知らない。全然、まったく。理解不能。
そもそも理解できることなんてこの世界になにひとつないのだ。自分自身のことすらわからない。
自分のことも彼のことも、わからなくたって大切だし、知らなくたって好きなんだから。だからそれでいいじゃない。
でもそれを素直に伝えて果たしてなんになるのだろうか。
「でも、訳くらい聞かせてくれてもいいはずでしょ」
言おうかどうか迷ったあと、やっぱり言葉を付け足す。「私を憐れんでくれるなら」。
憐れんで、甘く見て、体温くらい恵んでやってもいいと思っているのなら。一度でも思ったなら。
今でもまだ思ってくれてたら。
ソファの横に立って見下ろすと、目線の下にいても彼は大きい。その巨体が背もたれを支えにしてゆっくりと起き上がる。顔色が悪い。すえた臭いとタバコの臭いが混じる。男は私に見下ろされるのに慣れないのか、ゆっくりと時間をかけて立ち上がった。いつもの目線だ。見上げると少しまごついてから目を逸らして、TETSUは小さく低く言葉を漏らす。
「―――俺は恐らく胃がんだ」
「胃がん…… ―――って、癌ってこと!?」
日本人の死因トップクラス。聞き慣れた病名に頭を殴られたような気分。困惑する私に、ドン、と胸に書類が押し付けられる。これ、カルテだ。お医者さんが持つべきもので、私は自分のカルテですら読んだことも手にしたこともない。一応は目を通すけど、添付されているX線らしき画像を見てもよくわからない。氏名の欄は空白だった。
「で、でも癌って、いまはそんなに怖い病気じゃないって……」
「ところがだ、こいつは恐らくスキルスだろう。自覚症状もなく検査では見つかりづらい。進行も早く完治も困難と来た」
気づいたときには手遅れだったってわけだ。と、絶望的なことを言うくせに鼻で笑う様子で、吐き捨てるみたいに言った。
「だからって、えっと、こんなとこにいる必要ないんじゃない」
うちだってあるし、うちじゃないとしたら普通に病院がある。入院での闘病とか、緩和ケアとか。詳しくないけど世界にはそういう物があるって公共放送健康番組が言ってたし。
「一緒に帰ろうよ」
「―――どこにだよ」
「う、うちがあるじゃん」
「俺に帰る場所なんざねえよ」
思い上がるな。と、切り捨てる時彼はそっぽを向いてしまって、前髪に隠れて表情はわからない。
「で……でも。私……、に、できることなら、何でもするから……」
できること、ないだろ。と冷静な部分がうすら寒く笑った。TETSUと私の関係性に名前はない。彼に抱くこの気持ちの正体も知らない。交際はしてない、友人でもない。セックスもしてない。性欲よりも肉から遠く、恋にしては生々しい。友人みたいに助け合えず、恋人みたいに救い合えない。なんでもないのになにができるのかな。
「なんだってする。……ご飯だって作るし、話し相手にだってなるし、な、なんだって…………なんだって……」
しまいには情けなくも涙声だった。
「ぜんぶTETSUさんにあげるから。好きにして、いいから……」
こんな自分知りたくなかった。この人と会わなければこんな哀れっぽくて惨めに縋り付く私になんか気付かずにすんだのにね。
「血だって内臓だってなんだってあげるから」
どうせそんなもの要らないのはわかっていたけれど、仕方ないじゃない。ほかになにも持ってないんだから。
なにを捧げたら、彼は私を選んでくれるの。
あなたの神様ドクターKじゃなくて。
「――――――ふざけんじゃねぇよ」
ぐっと胸ぐらをつかまれる。ちょっと苦しい。襟首が引きつって髪の毛が巻き込まれて痛い。それ以上に怖い。当たり前だ。こっちは平凡な体躯の女性だし相手は2mから数字を引いてったほうが早い大男だ。そんな男が本当に怒っているのを初めて見たし、本当に怖いと思ったのもはじめてだった。出会ったときですら、私はこの男性のことをここまで恐れていなかった。いままでこんな強い感情をこの人から向けられたことなかったから。
「適当な御為ごかしで善人ぶって満足してんじゃねぇ。ヒロイン気取りなら余所でしな」
TETSUの怒りも最もだった。献身なんて意味がない。だって求めないよね。
「これは俺の人生だ。アンタに付き合ってる暇はねェ」
この人は私に求めない。私を求めない。そんなもの人生の岐路で丸ごと差し出されても迷惑だろう。こんなの全部私がしたいことで、彼がしてほしいことじゃない。いままでだってずっとそう。そりゃマジギレもする。
「なんでもするってんなら今すぐここから――」
「わたし、ほんきで……」
わたしはどこまでも自分本位に、続きを聞きたくなくて一生懸命言葉を探す。
「本気だよ……てつさん。」
威勢よく言うことはできなかった。だって目の前の男が怖くて。大きくて、強くて、そして死にそうで、だから。
「だったら」
獣が唸るみたいな声だった。くぐもって喉の奥から絞り出すような。そこからひとつため息みたいに深く息を吐いて、そして吸う。顔をそらして頭を掻いて、次に出た声はもう感情を抑えていて、この人はまた自分を隠そうとしているようだった。低くて、張りがあって明瞭で、でも掠れてて美しい声が、投げやりな様子で吐き捨てる。
「脱げよ」

「お前が言ったんだろ。オレのためならなんでも出来るって」
薄暗い廃墟に嫌に反響したのは、言葉を発した男自身のほうこそがその響きの悪意と害意に反吐が出たからかもしれない。馬鹿馬鹿しい程に棒読み。傷つけるためだけの卑怯で下卑た言葉だった。
びく、と言われた相手は肩を震わせた。うつむかれると、ついに女のつむじしか見えない。髪の毛がボサボサになっているのは自分の理不尽なやつあたりのせいだ。暴力性に反吐が出る。こんな男になる気はなかったし、こんな面を見せる気などなかった。気持ちを預けたら自分ではいられなくなるのなんてとうに理解している。
みっともなく縋れるかよ。
人と人は触り合うことで変容する。それがどんなぶつかり合いであれ。
自分の人生に勝手に痕跡を残し、そして消えた奴がいた。それで学んだのだ。相手の手が届くところに自分を置けば、変質してしまうのは自分の方だ。だから誰にも心を許してはいけない。まして触れさせるなど。
温もりが良いものであることなんて知っているのだから。
今更そんなものを手にしたら。
こっちの心中など一ミリもわかっていないであろう生き物が、怯えて泣いているように見えた。逃げる余地を作ってやるために、手を放して身体を引く。
怒りの端で冷静さを失ってはいなかった。脅せば尻尾を巻いて逃げると期待した。眼の前の人間は存在も人当たりもやわらかくて、自分と違うのは軽薄な部分だ。薄くて軽い生き物は、どこに触れても手の内から逃げて、決定的な瞬間には破れてしまうことをわかっていた。――今更この薄い熱を手にしたら、鼻先にぶら下げられたら、自分はいつか相手を食らいつくす。甘いものを我慢できない子供みたいに。内臓を貪る鷹のように。相手の人生をめちゃくちゃに壊すだろう。
離れるタイミングは何度もあった。本当は富山で突き放してしまえばよかった。その一件のあとも、この女に絡んだままだった悪意を退けて周囲の除菌を済ませたらそこで去ればよかった。手を切る瞬間はいくらでもあった。
それなのにどうして今まで手放せずにいたのだろう。
いま逃げたら許してやろうと思ったのに、いつまでもどこにも行かないことに痺れを切らして、脅しすぎたかと眼の前の相手に意識を戻す。
―――女はもう震えていなかった。
バッとこちらを見上げた瞳には恐怖や困惑の色はなく、ただただ何か正体不明の感情ばかり強かった。
服の裾をまくりあげて、情緒もてらいもなくばさりと脱ぎ捨てる。
「はあッ!?」
脱ぎっぷりよくシャツも放り投げて、ボトムスのフックに手をかける。患者でもないのに自分の前でこんなに色気なく肌を晒す人間など、居ていいわけがない。
「おまっ……気でも狂ったか!?」
「狂ってるのはTETSUさんでしょ!!」
相手はあられもなく、あっというまに下着姿になってこちらににじり寄る。
こいつ……引くに引けなくなってやがる…!!
呆然とする男に、そのままの勢いで掴みかかって、自分よりよほど大きい身体をソファに沈める。簡単にマウントポーズに持ち込めたのは油断と困惑の隙をついたからだ。隙を作ったのは彼女の手柄と言えなくもない。
「こんな、こんな私に簡単に押し倒されるくらいよわってるのに、強がって馬鹿みたいっ!」
薄闇に女の肌が白くぼんやりと光っていやに綺麗だ。
眩暈がする。
「TETSUさんの気持ちなんてわかんないよ……でも、私の気持ちも知らないくせに!」
こんなもの! ポケットから何かを取り出して、はずみで金属が床に落ちる。センス皆無のドラゴンソードキーホルダーがリノリウムを滑って、蓄光塗料でうす青く光っていた。合鍵の家主はそれには目もくれず、紙クズを引き裂いてぺしんと床に投げつける。小切手だった。お前これ金と一緒なんだぞ。そんな扱い方するな。
「どれだけ探したと思ってるの!? なんで探したら見つかるの!?」
「そ……れは、探したからだろ!?」
「めちゃくちゃ探したよ、すごい頑張ったよ! でも探したからって見つかるなんて、そんな私に都合のいいこと、起こるわけないのに……」
本当に懸命に探したのだろう。迷子の犬でも探すみたいに。
「闇医者のくせに。本気出したら私なんかに見つかるわけないのに……」
「どうしたかったんだよお前…」
しまいには子供みたいに駄々をこねて泣きじゃくって、これではどちらが迷子だったのかわからない。
「……なんでお前がオレを探すんだ……」
どうしてそんなになってまで必死に。
自分と居ることにそこまでの価値があるのだろうか。真っ先に思い浮かぶのは「あぁ金か」というわかりやすい評価値だ。あまり良い目を見せた記憶はないし、むしろしっかりと危険な目に遭わせたことすらある。手切れとばかりに小切手を渡したのはその詫びという側面も強かった。あるいは金じゃないとすれば恩か。最初に助けてやったことをいつまでも引きずっているのか。そんなものとっくに貸し借りなしだろうに。
適当に埋め合わせて、とんずらこいて、それくらいで切れる縁だったはずだ。
まさか切った糸を無理やり手繰ってこようとは。他人というものは本当によくわからない。
「そりゃ探すよ… いい加減私のことナメすぎだから!」
他人の気持ちなんかわからない。自分の気持ちだってわからない。
ただ確かなことはあの日、あの晩、こいつが俺のヤサに侵入りこんできた夜。
オレはこいつの人生に居場所を作ってしまったのだ。
「運命感じちゃうじゃん! む……報われたくなっちゃうじゃん」
ともかく、向こう数年見られないようなキレイな逆ギレだった。
「受け取ってくれないのはもう知ってるからさぁ……」
胸ぐらを掴まれても、痛みも恐怖もなかった。当然だ。小さくて軽薄で弱い生き物など恐れるものか。
だけど振りほどけない。自分のほうがよほど力と暴力に慣れているのに。これだから女って奴ァ――こいつときたら――参るぜ。
「そばにいるのくらい許してよ……」
今逃げたら許してやろうと思った。
目の前の人間は逃げなかった。
だから許してやろうと思った、この女の我儘と、そんなもんに負ける自分を。白旗のかわりに両手を上げる。手のひらを返して、術衣を着る際には禁則な程厭味ったらしく高く。
「わかった」
そんな文脈もお作法もなにひとつ知らない人間が、ぎゅうと寄せた眉根のまま目を見開く。
「わかった、俺の負けでいい」
オレは生まれてはじめて、自分より小さく非力で愚かで利口で可愛くて不愉快な生き物に負けたのだった。