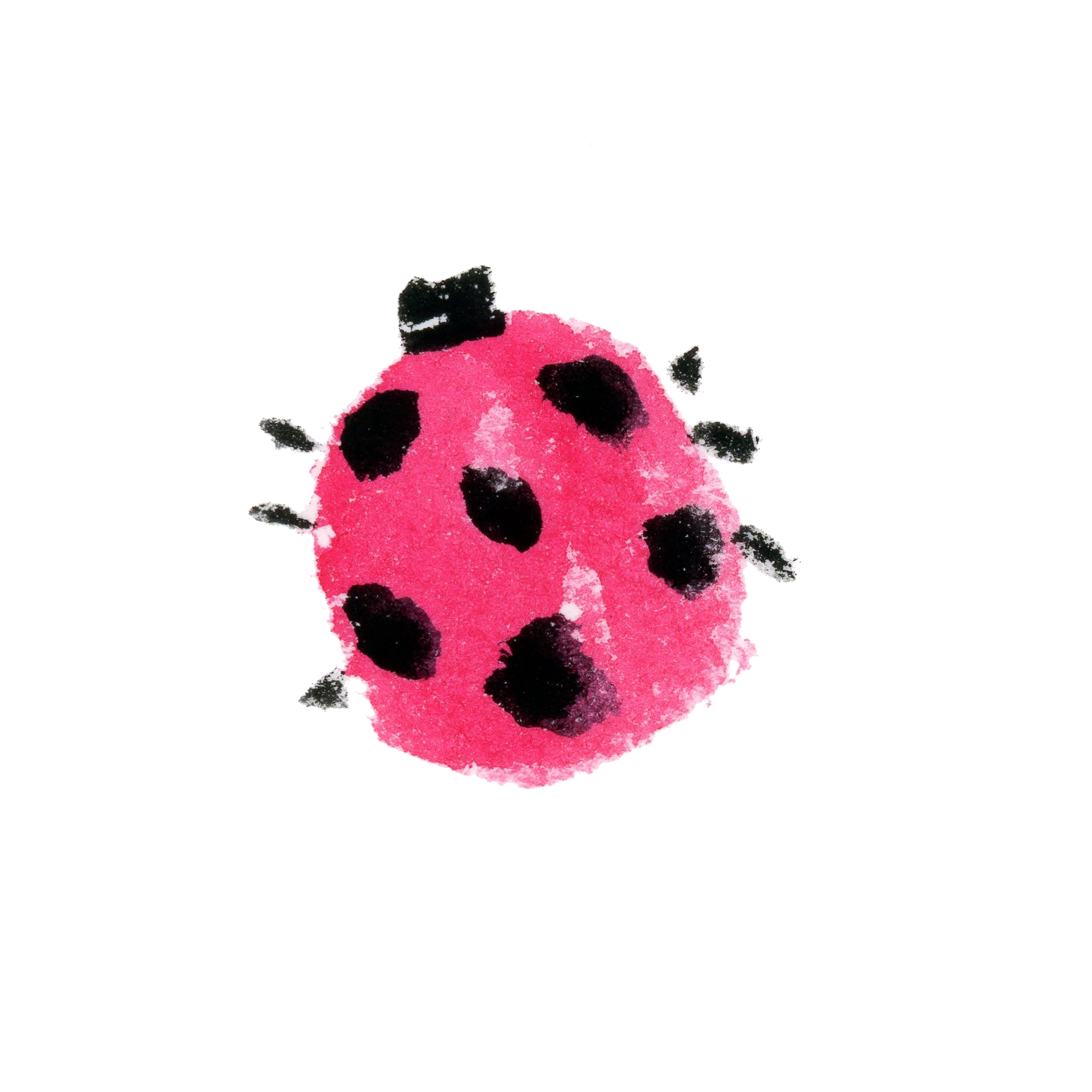
2-2
普段通りの夜だった。やってきたTETSUはなんかずぶ濡れだったので仕方ないなぁと甲斐甲斐しくタオルを渡すと、がしがしと乱暴に髪の毛を拭いていた。
「雨降ってたんだ」
「お前んちなんで駐車場ねぇんだよ」
うちの安普請には駐車場がないので、TETSUは近場のパーキングに停めてくるらしい。そこもわりと狭いので、あのギリギリのスペースによくあの化け物みたいな車を駐車できるなと感心する。日本国内で扱いやすい規格ではないだろう。そのうえあの車は一挙手一投足うるさすぎるので、近所迷惑だから絶対に家の周囲に停めてほしくない。
軽く水気を払った黒い髪は、濡れても前髪の元気さが失われてない。形状記憶合金で出来ていると言われたら信じる。ドライヤーをかけただけでこの髪型になるので、ひどいくせ毛なのだろう。
勝手知ったる素振りでシャワーを浴びに行く背中を見届けて、夕飯を温め直す。我ながら健気だ。将来介護が必要になったら食事の介助もしてあげる気まである。オムツ替えはそのまえに関係性がステップアップしてから考えたい。でもTETSUはタッパがあるから介護のこと考えると大変そうだね。
私がそんなこと考えているとはつゆ程も思わず、濡れ鼠から、湯気をまとって水も滴るいい男となりバスルームから出てきた彼は当然みたいな顔して食卓についた。懐かぬ猫が懐いたみたいだ。
別に美味い不味い言ってくるわけじゃないし出したのものを残したりもしないけど日本食のほうが食いつきがいいので最近は和食と和洋食に凝ってる。多少失敗してもTETSUは何でも食べた。健啖家というよりは食べれるものを食べれるときに摂っておくタイプなんだろう。もしくはお家の躾がかなりきちんとしていたのか。
心配しなくても食べられないものを残したって文句言わないし、お腹が空いた時はうちに来ればいつでも何かしら用意してあるのに。
「ね、お味噌汁、出汁変えたんだけど」
「ふーん」
今回も特に感想は言わずに啜ってる。毎度毎度こうなので、TETSU以外だったら五回はキレてるかも。世界中でTETSUだけは許します。手狭なキッチンに立つ大男を見つめて、自分でお皿を洗っててえらーいとすら思う甘やかしよう。尽くすタイプなのでTETSUには大甘である。ちなみにこういう性格のせいで元カレとは最悪の別れ方をしました。反省はあんまりしてない。
食欲が満たされたら残りは排泄欲と睡眠欲だよね、あと性欲! と思うけどTETSUは相変わらず身持ちが硬く、触れてはくれても進んではくれない。
「先寝るね」
寝支度をして声をかけると、ソファでドイツ語っぽい医学論文を読んでた男はばさりと紙束をテーブルに投げた。別にまだ起きててもいいんだけど、
量販店で買ったベッドはTETSUには小さくて窮屈そうだ。自然、丸まった大きな体の中に入り込む形になる。TETSUの腕は腕枕にしては高さがありすぎるので、後ろから重なるように抱きすくめられる。首筋に鼻が触れて、ふーとため息みたいにつかれた大きな鼻息がくすぐったい。
「くすぐったいよ」
「お前少し痩せたか?」
髪の毛を耳にかけられて首筋が露わになる。そこにがぶがぶと甘噛してくる生き物を後ろ手で撫でた。厚みがないとじゃれつきがいがないのかもしれない。「最近忙しくて」と言い訳する身体を外科医は撫で回して、大きな手のひらが胸についた軟らかい脂肪の塊に触れる。
「っ、てつさ……ん……」
見返ると、何も言うなとばかりに唇を塞がれる。形を確かめるみたいに、上唇と下唇を順番に食んで、舌でくすぐる。同時に手のひらは器用に動いて身体のラインをなぞる。全身がぼんやりと粟立って、身体が言うことを聞かない。星座を指で繋げるように、太くて熱い指が血管を撫でて筋肉の隙間を辿り、骨を確かめる。触れられるたびに熱を移されたように火照った。これ性欲じゃないな、支配欲とも少し違う。手術欲、解体新書欲だ。なにその欲望脳のどこに入ってるの。
「ふぁ、ふ……っん」
「は、っ……」
一度開放されて、再び口唇が塞がれる。好きに触っていい身体を逃さないように、脚が絡んで引き寄せられる。手のひらが腹部を撫で、薄い皮膚と脂肪と筋肉を暖める。
「はふ、きもちぃ……」
甘えたくて身体を擦り付けると、巻き付いていた腕にぎゅ、と力が篭ったのでもうそれだけでよかった。成人女性としてそれなりに育っているはずの私の身体をいとも容易にくるりとひっくり返して、まっすぐ視線がかち合う。眇めた瞳の奥が揺らいで、たしかにそこにはなにかの感情がちらついていた。
「…………綺麗な身体してんな」
「え、なに、口説いてる?」
「口説いてねぇよ」
クク、と喉の奥を震わせて笑う。私からしたら、年齢を感じさせない彼の鍛えて絞った身体のほうがよほど綺麗だと思うけど。それを言うとTETSUみたいにおっさんくさい口説き文句みたいになっちゃうので口には出さなかった。いつもみたいに甘えた声で「TETSUさん」と呼んで大胸筋に耳をくっつける。私のよりゆっくりとした心臓の音を感じて、やっぱりTETSUが私に触れる気持ちと私がTETSUに触れる気持ちは違うものだな、と思った。それが何かは私も彼も適当な言葉を知らないけれど。

変化が起きたのは未明のことだった。
「ゥ………、」
苦しそうなうめき声にふと目を覚ます。獣でもいるのかと思った。
TETSUは歯を食いしばって体を丸めていて、私が目を覚ましたのに気づいてかすれた声を絞り出す。
「オイ……俺の荷物……もってこい……」
慌てて常夜灯の室内を駆け抜けて玄関先に置いたままの巾着をひっつかむ。TETSUがたまに背負っているバックパックだ。蹲るTETSUの横に置くと、腹を抑えたままのっそりと起き上がった手負いの獣がガサガサとバッグに手を突っ込んで、しまいにはベッド上にひっくり返した。ケースを取り出して、薬を口に放り込む。薬の名称は私でも知っているもので、痛み止めだった。気を利かせて水を用意すると、喉仏を震わせてゆっくりと嚥下。しばらくは苦しそうにしていたが、時間をかけて段々と呼吸を落ち着けてゆく。
かなりたっぷりと時間が過ぎた後に、閉じていた目をふっと開けた。顔色は青いまま。
「TETSUさん……大丈夫?」
医療の心得などちっともないので、苦しげな背中を擦ることしかできなかった。いつか私がガラス片を取り出した背中だ。あれだってかなり痛そうなのに飄々としていたものだが、その分今回は本当にきつかったのだろう。
復帰した男は私の手を振り払う。「もういい」とぶっきらぼうに告げて。
久しぶりに、本当に久しぶりに拒絶みたいなものを受けて面くらい、すごすごと手を引っ込める。かなりショックだったけど、あからさまに傷ついたって顔をしたくなくてなるべく気持ちを隠す。体調不良者の前なのだし。
具合の悪そうな男は自分が散らかした医療器具をバッグへと仕舞いキュッと紐を留めた。
ベッドの上を動く体重が去りゆくことに気づいて、慌てて声をかける。行かないでとは言えなくて、「外は雨だよ」とだけ。一瞬腰を浮かせかけたが、どすんとベッドに重みが戻る。座っていた私ごとマットが揺れる。こちらに背を向けたまま、男が横たわる。常夜灯のオレンジ色の光の中、背中の筋肉が隆起する。呼吸に合わせて微かに震えて、たまに身じろぎをする。
その背中を一晩中見つめていた。
何を言えばいいか分からなかったから。
だから青白い朝日が安いカーテンに透けて部屋が明るくなりゆく頃に男が布団を忍び出ても、寝たふりしかできなかった。目が合えば縋りつきそうだったから。それくらい、その日の彼は弱々しくて、私は彼のことを何も知らないのだと目の当たりにしてしまったから。
それから2週間経った。TETSUはその後うちにやってくることはなく、普段通りの日々が続いている。2週間というのは、TETSUが姿を表さない期間としては特別長いものではなく、数ヶ月合わないことなんてざらにある。むしろここ最近が頻回すぎたとも言えるのだけれど、とはいえ気になるのは。
「絶対大丈夫じゃないよね……」
みぞおちを押さえて苦痛に脂汗を浮かべていた。怪我じゃないのは状況的に明白だったので、だとすれば身体の中のことだ。ちょっと胃が痛いとかそういうのとは明らかに違う様子。夕飯のメニューは私と同じなんだから食あたりってこともないだろう。ふるえながら痛み止めを飲む姿が目に焼きついている。そりゃ若くはないが、長身筋肉質で頑強な身体は病気とは無縁そうだというのに。
友達であれば気軽に連絡くらいできる。仕事上の付き合いの人でも、様子確認くらいは難しくない。けれど私とTETSUはなんでもない。連絡先も知らないし、知る機会があっても飛ばしの携帯なのでそのうち連絡がつかなくなる。いくつか知ってる拠点も、ほとんど使われていなかったり知らぬ間に他に流されていたりして、生活の実態を掴むのはむずかしい。根無し草だ。唯一根を張る植木鉢といえば愛車くらいだろう。
そもそも今このあたりにいるとも限らないし。
―――そう思ってるのになんで探しちゃうかなぁ私は。東京も日本も意外と広いのに。自分自身に呆れながら、右ポケットのクシャクシャに丸めた紙をより一層握りつぶす。手の汗でぬるくなったドラゴンソードつきの合金とともに。
昨日郵便受けに、合鍵とともに無造作に突っ込まれていたそれは、大層な金額が印字された小切手。ゼロの数を例えるならば、この金額の借金を背負ったら返済か死か逃走か迷いつつやっぱり死に肉薄するような金額だ。
私が不在の間にこれを仕込んでいったんだろう。彼は私から離れる気だ。
そう思うと途端に許せない気持ちがムカムカと湧いてきた。そりゃTETSUと私は何でも無いし、TETSUからしたら充分筋は通したつもりかもしれないけどさぁ。彼的にはこれで充分なのかもしれないけれどねぇ。でも年単位で絡んでて終わりがこれって。これってさ。これってさぁ。なんかさぁ。あんまりだ。ふんじばってでも言い訳を問い詰めたくて、彼を探す私はきっともうおかしいのだろう。人生一度くらいおかしいほど誰かに執着しても許されるはずだ。木訥で誠実な真人間相手ならともかく、相手は闇医者なんていう謎存在だし。闇医者、ブラックジャックで絶滅したはずだけど。以前そう言ったら彼は「いねぇんだよ、ブラックジャックは、現実に」と倒置法でつっこんでいたが。
探し方はシンプル。まずは富山に飛んだ。嘘、今回は夜行バスで行った。
真田医院はもう無かった。跡形も。
柱一本残ってない。私の記憶違いで間違った場所に着いてしまったのかと思ったほど、綺麗さっぱりなにもなかった。近所の人に聞いたら、半年ほど前に業者が解体してさっさと片付けていったらしい。「いわく付きで縁起が悪いし、雰囲気も暗かったからすっきりしたわ」とおばさまは言った。真田家の墓も無かった。TETSUが仕舞ったのだろう。
次いで向かったのは西城医院。KEI先生は私の顔を見るなり少し驚いて「なにかあったのね」と確信を持って言った。多分酷い顔だったのた。
「………TETSUさんが行方知れずで」
KEI先生は、私がTETSUを探すのを止めたりはしなかったけど「あの男は元々闇に紛れて生きているのだから、本気で行方をくらませたら貴女が見つけるのは……」
無理だ、という言葉を、先生は優しく飲み込んだ。TETSUが私相手に本気を出すとも思えないけど。
「……ケーのこと教えてください」
この人は知っている側の人なんだろうというのは、考えなくてもわかった。案の定KEI先生は少し息を呑んで難しそうな顔をする。
TETSUからそれについて教えられていないってことは、知らなくていいことか、知られたくないことだ。大切なものほど人からは隠してしまったほうが良い。TETSUは私からそれを隠したのだ。
KEI先生は私の人生トップレベルの恩人である。TETSUには「よくそんな性格で生き延びてんな」と言われるが、先生がいたからに他ならない。引き際を見極めてくれるのは彼女だ。ドクターストップをかけるのであればそれでも良い。むしろそうしてくれたほうがホッとしたかもしれない。諦めもついたのかも。自分自身の責任で身を引くには私は彼に入れ込みすぎている。
私の主治医は少し考え込む仕草をしたあと、ワーゲンのキーを手にした。
「詳しいことは、道中で話すわ」

「私の一族は」から始まった話は兄の死で終わりを迎え、まるでいまはエンディングのあとみたいだった。
エンドロールの上の方に名前が載っているであろう彼女は運転中なのでずっと前を向いたままで、だからこそすんなりと話せているようだった。こんな話、面と向かってだとお互いどんな顔していいかわからないもんね。
私の人生をほぼほぼ知っているこの人間の、出会う前の話を詳しく聞いたのは初めてかもしれない。只者じゃないとは常々思っていたが、くぐり抜けてきた修羅場が予想の斜め上すぎる。TETSUがKEI先生について語ってたことの意味もわかった。
そりゃああんな経験してたらなにを話しても泰然自若と受け止めてくれるはずだよ。
「兄とドクターTETSUは水と油のようだったわ」
同じように高い技術を持ちながら相容れず、徹底的に反目し合った。
過ぎ去った物語の中のドクターTETSUは私の知らない男みたいだった。私の知っている彼は、片方無くしてもなんとかなるからと似たような白い靴下しかもってないようなおじさんだったから。私はTETSUのことなにも知らないし理解していない。
私が、KEI先生が、あらゆる全ての人がそうであるように、人は歳を取る。TETSUにもおじさんじゃなかった頃があるし、それほど執着するドクターKを失っても、人生は続く。歳月は過ぎる。
それは何を諦めるのに十分な時間だったんだろう。
フォルクスワーゲンは山奥の廃れた洋館にたどり着いた。
TETSUに関わるものはあらゆるものが既に「過ぎ去ったもの」だ。終わって廃れたものを流離うような生き方。最初から失くなっていたら、これ以上失うことはないもんね。
四角い墓石に名は刻まれていない。かつては美しかったであろう、枯れかけた仏花が供えられている。ここに誰か来てから少し時間が経っている。多分TETSUだった。
持ってきた花を供えて手を合わせる。
「いまだから思うけど、兄が私に結婚を急がせたのは一族の宿命から逃がすためだったのね」
「それは……」
勝手ですね、と言う言葉を飲み込んだ。死んだ人の行いをジャッジするのは危険だ。そこには真意が喪われている。人間のやることを外殻だけなぞって断罪するのは、チョコレートの箱を前にして開けないようなものだ。フォレスト・ガンプのママなら卒倒する。開けたらチョコなんて入ってないかもしれないし。
あるいはもっと素敵なものとか。エルピスとか。「沈殿するため開封する前によく振ってください」の注意書きをパンドーラちゃんが見落としたおかげで箱の底にそれが残ったのは有名な話だ。
「あの男は、兄と似ているのかもしれない」
TETSUを開けた中には何があるのだろう。それはドクターKの中にもあったものだろうか。いまとなってはもうわからない。多分TETSUにもわからない。人は他人の身体よりも自分の体のほうがずっと見えない。女の子はお砂糖とスパイスと素敵なものいっぱいでできていた時代があるらしいけれど、いまの私は血と骨と内臓とドロドロした何かで出来ていたらいい。少なくともチョコレートではない。甘くも苦くもない。ただ辛いけだ。
TETSUとドクターKが似てなかったらいいのに。だってその人早逝したんでしょう。死って全部終わりなの理不尽でだめだよね。
けど似てなかったらいいのにっていうときは大体似てる。
「ほんとうは止めるべきなのでしょうけど」と前置きをして、KEI先生は私を見た。出会ってからそれなりに経ったけど、この人は変わらない。いつだって堂々と背筋が伸びて、だれが相手でも怯まず自分を持っている。
あきらめない強さとためらわない優しさをどちらも手にして、そのうえでメスまで持っていつも誰かの心と体をどちらも救うことができる。
どこか陰を背負いながら、一層輝く私のあこがれ。
私の先生。
風が吹く。木漏れ日が揺れて先生の瞳を照らす。緑と土の匂い。遠くで鳥が飛ぶ。
揺らいだ影が先生の瞳を翳らせて、そして輝かせた。眩しい光にも暗い陰にも怯まずに、まっすぐに私を見つめている。
「見届けるわ、私はあなたの主治医だもの」
優しい口調だけど、それは「はじめたなら始末をつけなさい」と同義だった。先生はいつも正しい。