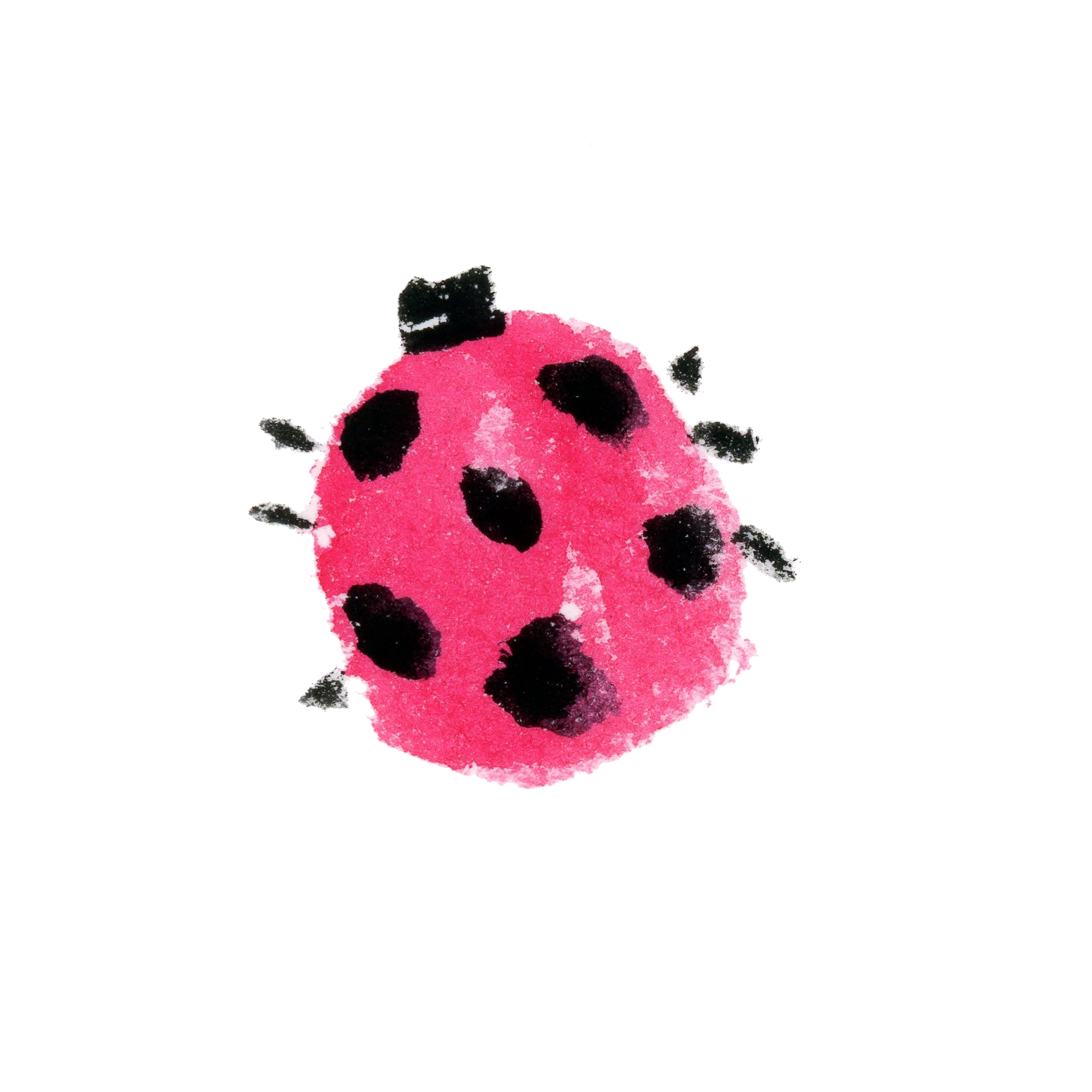
1-3
○○地区までは車で30分くらい、国道から少し外れたやや郊外の農村部だった。少なくない乗車時間のうち最初の10分が沈黙で満たされ、さすがに気遣ったらしい運転手さんが「お二人さんはどちらから?」なんて話を振ったけど、その優しさはTETSUの無視によって無駄となってしまった。
「ねぇ、大丈夫? ちょっと寝てていいですよ?」
私はさっき少し寝たし、と、廃工場にて結構な大立ち回りを見せつけてくれた男に言う。私なら三日三晩熱出して寝込んでるような作業量だ。TETSUは一瞬なんのこっちゃという顔をしたあと、ああ、と納得したように少し笑った。見慣れたわざとらしい悪辣とした笑顔じゃなくて、眉根を緩めて少し目尻を下げた、本当の笑みだった、と、思う。
「人のこと心配してる場合かよ」
「…………」
「オイ?」
「っい、え、膝枕くらいならサービスしてあげようと思って」
「いらねェ」
狭えし、といって男は腕を組んで窓側に頭をもたれさせた。私は動揺を隠すように、反対側の窓へもたれる。ひんやりとしたガラスに、のぼせた頭が少しだけ冷えた。もうすっかり昇った朝日が街を青く照らしていて、まだ活動し始めていない家々がすごいスピードで視界を横切っていく。
程なくしてタクシーは路肩に停まって、TETSUは窓ガラスからふっと頭を上げた。
「ちょっと待ってな」
彼は私を残して、すぐそばにある小さな墓地の丘を登る。たどり着いたのは真田家之墓と刻まれた古い墓石。あまり手入れはされていないようで、周囲の墓はささやかな花や洗った形跡があるけれど、このお墓にはどちらもない。
TETSUが躊躇わずに納骨室を開けたのでぎょっとして声を上げることもできなかった。骨壷の隙間から劣化した革財布を引っ張り出して、タクシーから見守る私に投げてよこす。
「それで払っとけ」
財布の中には、最近出回り始めた新札とは違う所謂旧デザインのD号券が入っていた。新渡戸稲造と目が合う。待たせていたタクシー運転手に支払い、お釣りをもらって、財布にお金を戻す。小銭入れには青く錆びた硬貨に混じって鍵が入っていた。
タクシー運転手にお礼を言って振り返ると、丘の上で彼は真田家の墓を見つめていた。なんとなく邪魔はしたくなくて、墓を見つめる彼の丸まった背中を遠くから見ていた。変なカップルからちゃんとお代をいただけたことに安心して、タクシーが去る。
風はしょっぱくて、海の音が近い。
TETSUの背中を見ているときゅうと胸が締め付けられて、なんだか私までものすごく寂しくなってしまう。さっきあんな笑顔を見せられたせいかもしれない。油断したみたいな、虚を突かれたみたいな、そういう顔を。
苦しい胸に新しい空気が必要で、草をかき分けて丘をさらに下る。海が近くなる。松の生えた断崖の向こうに、昼の光を浴びた海がキラキラ光っていた。遠くに何かを見つけて、崖の縁まで行って目を凝らす。
「魚……?」
バシャンと水しぶきを上げて、大きな生き物の影が揺れる。一匹だけだ。ひとつぶんの命だけが、波に逆らいぴょんぴょんと自分の生命を主張している。
沖の方へ向かって、やがて見えなくなった。
「―――イルカか」
「わぁっ⁉」
このひと、人を驚かせるのが趣味なのかな。
落ちるぞ、といつの間にか近づいていたTETSUに首根っこを掴まれて崖っぷちから引き戻される。
「能登の方だと多いんだがな」
群れからはぐれたか、と独り言みたいに呟いて男は目を凝らした。海のお友達が見えなくなった水面をただじっと見つめている。陽の光が眩しそうだ。
「地元なんですか?」
確信を持った問いかけを「さぁな」とはぐらかして、波間から目をそらして踵を返す。
丘を登って、横道にそれて、少し下るとまばらながらも住宅街が現れた。そのうちのひとつの建物の門扉をてらいもなく彼はくぐっていく。外壁には落書きがあって、いくつかの意地悪な言葉や下品なマークが書かれていた。地面に落ちて欠けたのを邪魔だから敷地内に放り投げたみたいな表札には「真田医院」と彫られていて、さっきのお墓を思い出す。玄関の引き戸は一応鍵がかかっていて、TETSUは私が返した財布の小銭入れから鍵を取り出してそれを解錠した。手慣れた手付きだった。中は入るのを躊躇うほど半壊していたが、表札で事前知識を仕入れなくとも「病院だった」と感じられる程度には診療所然としていた。しかし廃墟だなぁ、と思った。この人はいつも廃墟にいるね。今回の廃墟巡りで一番ぼろぼろで、どこか人為的に破壊されたような気配がある。
天井と壁と床があるだけでほとんど外と似たような室内を彷徨っていると、やがて診療所から生活スペースのようなところに出た。町内のお知らせや埃被った民芸品、朽ちた紙細工から、地域と生活と診療所が密接だった名残が見える。大きな柱に彫刻刀でひっかいたような傷があって、指でホコリを払うと縦に不規則に並べられた横線と文字が見えた。5歳から始まる「タケシ」と「テツロウ」の背比べだ。彫刻刀で掘ったものなのであらゆる筆跡が直線で、シとツの見分けは付きづらかったしウの字はうかんむりに似ていた。「テツロウ 五」と「タケシ 八」はずいぶんと私の目線の下にあるのに、二次性徴前夜であろう「テツ 十二」はすでに私の目線くらいあってでかい。「タケ 十五」はもう完全に私を越えてるし世間の平均も越えてそうな位置だ。保護者ももう十分だと思ったのか、それとも「テツロウ」が中学生になるときにこの行為からも卒業したのか、目盛の最大はそこで終わっていた。
テツロウならぬTETSUがなにやらせっせと旧診療所の机をずらしたり床下収納をあけたりしている間に私は他の部屋を眺める。奥の部屋には仏壇が見えて、抜けそうな畳を恐る恐る辿って最奥へたどり着く。軽く埃を払って床に落ちたご位牌と御本尊を戻すと、少しほっとした。なんであれ神仏として崇められたものが床にいるのは落ち着かない。うつ伏せに倒れた写真立てを戻すと、真田医院の表で撮られたものだった。父母と多分タケシと恐らくテツロウの四人、どちらも小学生の時分か。私は写真立てをもう一度裏返した。
これ、倒れていたんじゃない、伏せられてたんだ。
秘密というほど秘めやかではないが、ひそひそ話程度に囁かな家族の会話みたいなのを暴いてしまった気がして、謝罪代わりに手を合わせる。
「――……信心深いのか」
「そう見える?」
いまの声かけは驚かなかった。ぼろぼろの床が軋むので、誰がどこにいるか丸わかりなのだ。居間のタイルをひどく鳴らして、畳の間に入る直前で男は止まった。この部屋のほうが劣化がひどいので、あのサイズの男が入ったら畳が抜け落ちるだろう。ちょっと見たいな。とはいえ自分がそうなるのは勘弁なので、根太が入ってそうな床を選びながらゆっくりと男のもとに戻る。
「私はクリスマスのあとに初詣に行くし、死にそうな目に遭ったときには神に祈る程度には信仰心が篤いよ」
そういう私の薄っぺらさには目もくれず、TETSUは仏壇を見つめる。
「片付けたところで無駄だぜ。どうせここはすぐ壊すんだ」
「じゃあなんで残してたの?」
「……忘れてた」
そんなわけなくない? と思ったけど嘘だってバレても別にどうでもいいんだろう。彼が正直でいたかった相手はもうどこにもいない。多分だけどみんな墓の中にいる。残るのは虚勢と嘘。そうじゃなきゃこんなでかくなっちゃった少年みたいな男が身体一つぶらさげてうろうろ彷徨っているわけがないのだ。神仏も目的地も帰着地も、そういう目に見えないものは全部放っておいて、TETSUはいつの間にか大きなボストンバッグを背負っていた。
「いくぞ」
と言われて、ぽかんと口を開ける。
「なんだよ、今夜はひとりで野宿するか?」
「え、もういいの?」
「ここはもう人の住む場所じゃねぇんだよ。装備を整えに来ただけだ」
それはわかっている。たしかにどう見ても寝泊まりには適さないだろう。外のほうがなんぼかマシだ。とはいえ雪こそないもののまだまだ寒いので、野宿なんてしたら危うく凍死するだろうけど。
でもここ仏壇のあるあなたの家なんだよね。名残惜しさとか、里心とか、そういうのってさぁ。
「表に出れねェ医者の俺に家なんざあるか」
「ブラックジャック先生は家があるじゃん」
しかもわりと立派な家だ。高度な手術をしようとするとそれなりの設備がいるのだろう。
「TETSUさんも無免許?」
「そう見えるか?」
「そうじゃなきゃいいなって思う」
「安心しろ、免許ならある」
「よかった。じゃあなんで闇医者なの?」
「―――……おめぇはその好奇心と迂闊さでなんでまだ生き残ってんだ」
「えー…………」
闇医者に闇の理由を問うのは失言だったらしい。なんで生きてるって問われても、ねぇ。
「たまたま……」
ここにいるのも偶然だし、そもそもあの廃病院でTETSUに会わなければ今頃どうなっていたか。TETSUに会ったからこそ北陸で死ぬような目に遭ってるとも言えるけど。
「TETSUさんが助けてくれたからね」
「俺に会うまでよくのたれ死ななかったな」
「縁に恵まれたんだろうねぇ」
昔の話とかあんまり掘り下げられたくなくて、でもTETSUのほうもさっきの感じやっぱり自分の過去に触れたくなさそうだから、「見つけてくれてありがとうね」とだけ言ってここで会話を切り上げた。
バスを乗り継いで人口の多い場所に出るまでの間は、サラダに混じっててもぎりぎり許せる虫って何? とか、手相の生命線ってどれ? みたいな話だけをした。TETSUの生命線はめちゃくちゃ長かった。よかったね。

廃病院廃工場廃屋と渡り歩いて、ようやくまともな屋根の下で眠れると思ったけど。こちらとしても手配してもらったので文句を言うつもりはないけど。
繁華街を抜けてたどり着いたのは面構えこそアーバンな品格みたいなのを繕ってはいるが、外壁には「休憩」と「宿泊」の料金が示されていた。どうみてもラブホテルだった。
「ラブホじゃん」
「あいつらの息がかかってねぇのだけは確かだ」
「なんで?」
「敵対組織の縄張りなんだよ」
ああ、先に依頼受けたっていうほうね。
ラグジュアリー系っぽいドアを開ける前に、フロントから男性がすっとんできて、TETSUとなにやら言葉を交わしている。男はTETSUの背後にいる私に気づいて彼越しにこちらを覗き込もうとしたが「成り行き上のツレだ。気にすんな」と制止されていた。
部屋に入ってまっさきにしたことは薄暗い照明を昼白色に設定してなんらかのムードを消すことだった。
「シャワー先浴びていい?」
「好きにしろ。あんたアレルギーあるか?」
二人眠れるサイズのベッドど真ん中にぼっすんとボストンバッグを置いて、TETSUはルームサービスのメニューを手に取る。お腹すいたんだね。あんだけ暴れたもんね。私はそれに返事をして、ガラス張りのジャグジーにカーテンを引いた。
熱いシャワーを浴びたあとに廃れた建物めぐりをしてきた服を再度着る気になれず、バスローブで部屋に戻るとTETSUは「警戒心死んでんのか」と闇医者のくせに常識的なことを言った。
「TETSUさんも早く入りなよ。ドラム式洗濯機あったよ」
「俺ァ後でいい」
そのうちにルームサービスがやってきて、広い部屋にカレーの匂いが漂う。狭いテーブルにカレーとオムライスとパスタとカツサンドとチキンバスケットがぎゅうぎゅうに乗ってて、わんぱく食いしん坊少年の夢みたいだった。
「コーヒー飲みます?」
「ああ」
コーヒーと煎茶を淹れていると「カレーとオムライスとカツサンドとスパゲッティどれがいい?」と予想外の選択を迫られた。私に選択肢があったとは。どれでもいいよ。
「なにカレー?」
「たぶん牛」
「余ったのでいいですよ。TETSUさん何が好き?」
「なんでもいい」
頼んだ人が先に選んでくれ、あと身体おっきいから肉食え、と思ったので無言でカツサンドを押し付けた。
「オムライス食べていいですか?」
おん、みたいな返事をして、ペペロンチーノとカレーを手元に引き寄せたTETSUがオムライスをこっちに寄越す。
「ラブホでペペロンチーノ食べる人いるんですかね」
「居るだろ、ここに」
「いやそういう意味じゃなくて」
「食いてェときに食いてェもん食える関係のほうが健全だろ」
オムライスと格闘する私を尻目に、TETSUはカレーとパスタとカツサンドを簡単に平らげて、チキンバスケットに手を伸ばした。身体が大きい分燃費が悪いのかもしれない。
「ねぇ、やっぱり私達ってこのあと追われる感じですか?」
「メンツ潰されて黙っちゃいねぇだろうな。依頼蹴ったことだって、依頼そのものよりも敵陣についたことが気に食わねぇやつらだ」
「逆恨みだぁ」
「成り行きとは言え巻き込んだしな、そのへんの始末はつけといてやるよ」
チキンバスケットのポテトを貰いながら、そうなんだ、ありがとう。と告げると眉頭をぎゅっと寄せて嫌そうな顔をした。最初にお礼しに行ったときもこんな感じだった。感謝されるの嫌いなの?
「謂れのねぇ感謝なんぞいるか」
「あるでしょ謂れ。助けられてますし」
「お前は俺に巻き込まれてんだぜ」
「最初だって、TETSUさんがいなかったら私多分ひどい目に遭ってたよ」
「あんな胸糞わりぃ場面見たら誰だってそーすんだよ」
「誰でもそうするかもだけど、いたのはTETSUさんだったので」
TETSUさんが居てよかった、と呟いてコーヒーカップで煎茶を啜る。TETSUさんは手の大きさとカップがあわないのかなんなのか、取っ手をつままずにカップ自体を手で覆うように持って、コーヒーを飲む。熱くないのかな。
「……あんた馬鹿だろ」
「ホントのことでも言っていいことと悪いことがある」
「認めんのかよ」
「よく言われるんだよね。私ってほら、いかにも無害って感じだし」
「そうみてェだな、その様子だと」
「先に差し出したら意外とそれ以上酷い目には合わないから」
「つまんねェ生き方しやがって。おめぇみてぇなの、イライラするぜ」
「そうかもねぇ」
笑ったつもりだけど乾いた声しか出なかった。これぞ私の人生なんだよな、笑えねぇー。でも私の人生は笑うしかない瞬間だけで構成されている。TETSUとの拉致監禁大立ち回りはちょっと本気で面白くて、絶対滑らない話なんだけど絶対人には言えない話すぎた。フィクションってことにして本でも書いてやろうか。
ドクターTETSUがそれなりに気にかけてくれるのだって、あまりにも私が情けなくて無力だからだろう。世間ではそれを「舐め」とも呼ぶ。そうじゃなきゃいくら巻き込んだとはいえ実家っぽいとこにまで連れて行かないはずだ。警戒する必要もない相手だもんね。
笑い話がてら元カレの話でもしようと思ったけど、食べ終わった皿を重ねたTETSUが洗面所に手を洗いに行ったので話し損ねる。よく考えたらTETSUにそんなことまで話す必要はないんだけど、彼相手だと油断して口が滑りそうだ。
お腹がくちくなって血糖値が上がってきたのか少しダルくなって、ソファに横たわった。ベッドがよかったけど、散々闇医者本人から警戒を促されたあとなので、ちゃんと自制した結果だ。
「気分不良か?」
「ちょっと眠いだけ」
「起きろ、見せてみろ」
ゆっくりと起き上がると、巨体が横に座った。ずんとソファが沈む。ニトリルの手袋をぱつんと付けて、大きい手のひらが顔に添えられた。
「ちゅーします?」
「しねぇよ。ニンニク臭ェぞ」
首筋と額の熱感を測られたあと「ちょっと眩しいからな」と瞳孔にペンライトを当てられる。「薬で体調崩したことあるか?」といかにも医者っぽいことを聞かれて、闇医者だけど免許は持ってるんだったなと思い返した。
「先日、お酒に混入されて」
「ノーカンに決まってんだろ」
「じゃあ、ない」
「定期的に飲んでるものは?」
問診みたいというか、多分そうなんだろう。最後に「おい、手ぇだせ」と手のひらを差し出され、素直に手のひらを乗せる。
「そっちじゃねぇ」
ぐいと引っ張って腕を露出される。ゴムチューブをぎゅっと腕に巻かれ、肘の内側のやわいところをアルコール綿でさっと消毒。
「え、あの」
ちょっと待って、と言うにはあまりにも手際よくて自然だった。
「言ったろ、プロは違うもん使うんだよ」
過去一うまい注射だった。
ふっと目覚める。まだ頭が起きてない気がする。寝返りを打ったらべしゃりと床に落ちた。暗闇の中でしばらくうとうと入眠と覚醒を繰り返してから、ここがソファの足元なことに気づく。絡みつく毛布から二度三度失敗しつつ脱出し、よたよたと這うようにベッドへ辿り着こうとしたのは本能か習慣か。ともかく、やたらに眠くて力の入らない身体では床からベッドに登れずにあっぷあっぷだった。
ベッドのふちで床に溺れそうになってると、なにかにぐいと引っ張り上げられる。そのでかくてあったかい抱きまくらみたいなのに抱きついて、再度就寝。

目覚めると眼前に人の胸板があったのでびっくりして押しちゃった。「うっ」とうめき声。ごめん。もはや見慣れた男は、油断してたところにどつかれて普通にダメージ食らってた。
「え、あ、どゆこと⁉」
「おめぇがソファからこっちに這い上がってきたんじゃねぇかよ」
「ええ……ごめんね?」
苦しそうに咳き込んでから、TETSUはのろのろ身体を起こす。ひと風呂浴びたのかバスローブ姿だが、アームカバーは欠かせないらしくパイル地の下に黒い布が見えた。
ベッドサイドにはいつのまにかコートがかかっていた。その横には私のバッグ。
「あ、バッグ……」
「取りに行ってきたんだよ」
まだねむそうに大口を開けてあくびをしている。よたよたと起き上がる様を見るに、身体が辛そうだ。
「いつ戻ったの?」
「あー……3時間は前か」
ベッドに埋め込まれた電子時計を見やる。外はまだ暗い、明け方だ。あれから半日以上寝ていたらしい。彼のほうはまだ断然眠いだろう。
「おい」
「わっ、なんで脱ぐの⁉」
「ここの破片がどうしても取れねぇんだよ」
かなり丈が足りてないバスローブの下には包帯が巻いてあって、それをしゅるしゅる解く。背中には生々しい傷跡がまだ血をにじませていた。怪我人は困惑する私にピンセットと脱脂綿を渡す。
「頼む」
「ほんとにどういうこと……⁉」
「あっちの処理が終わったらあんたは置いてこうと思ってたんだが」
「ど、どんな処理」
「対抗組織をけしかけたんだよ。後腐れがねぇようにはしといてやったから安心しな」
「大暴れした気配がすごい……」
「こいつは事故みてぇなもんだよ。ガラスの破片が降ってきやがって」
ジャリジャリしたぜ、と。それ絶対ジャリジャリだけじゃ済まないよね。
「あらかた取ったが深いとこのがどうしてもとれねぇんだよ」
「なんかさ、そういうのって地元のお医者さんコミュニティとかでお願いできないものかな」
「……俺はこのあたりの医者と折り合い悪くてな」
「ふぅん……―――あっ、ていうか私になんか打ったよね、注射!」
「よく眠れただろ」
「安全なやつなの? ねぇ〜!」
「普通に医療行為でも使うやつだから安心しろ」
「抵抗しないから次は覚悟決めさせてね」
次って、と闇医者がつぶやく。
一応カバンを取りに行ってくれたみたいだし、私のこと置いてく気だったのはもうよいとして、急な注射で昏倒させるのはよしてほしい。ていうかそんなに引っ付いてきそうな女に見えるかな。だとすれば人を見る目があると思う。
「うぅ……」
「はやくしろよ」
「むり……痛そう……」
「こっちは痛ぇんだよ」
「ごめんって……」
向けられた背中には痛々しい裂傷がいくつもあった。古傷もある。闇医者って過酷なんだな。昨日みたいな事態、慣れてそうだったし。
指示されたところにピンセットで触れる。冷たいステンレスを人の肉に差し込む感覚、嫌すぎる。意外と奥までピンセットが入るたびに、血と肉の熱と脂で金属が曇った。よく見えないから奥に押し込んでしまいそう、でもあんまり掻き回しても絶対痛いだろう。
「うぇえ…」
「やめろその声」
「だって結構深い……」
「んなもん浅いほうだ」
「麻酔とかしなくていいの?」
「そこまでじゃねぇが痛ェからさっさと済ませてくれ」
「しばらくお肉食べれないかも。……富山名物ってなに? 富山牛?」
「ベニズワイガニ?」
「カニ! 食べて帰ろ!」
「勝手に食え」
「一人で食べてもつまんなくないですか?」
なんか蟹の身ほじってる気分になってきた、と言うとでかい背中が少し震えた。
「ごめん、痛かったですか?」
「なんでもねぇよ」
ちょっと声も震えてた。笑ってる?
指定されたところをすべて取り終わり(結構深いところにでかい破片があったりして血の気が引いた)、言われたとおりに消毒と保護をする。おっきい血管傷ついてなくてよかったですね、と言うと「こっちは縫った」と左腕の真新しい包帯を見せられた。病院いけ。いや闇医者保険証ないか。それでなくてもさっき言ってた感じ、なんかこの辺の医者とは訳アリっぽい感じだし。あの真田医院の惨状となにか関わりがあるんだろう。
組織をどう処理したのかはそれ以上詳しくは言う気が無さそうだったが、無害化したならもうそれでいいと思った。一件落着といったところか。
「映画だとこういうとき」
安心したのか、自分でも唐突に思えるくらい突然メーターが振り切れた気がする。吊り橋効果というのか、あるいは単純に長く一緒にいたせいか。命の危機に瀕すると生存本能により性欲が増すとも言うし、理由付けはなんでもよかった。
「ふたりは見つめ合ってキスしてハッピーエンドですよね?」
爆発オチも悪役の小気味よい死も花も歌もダンスもないけど。
身体を寄せて頬に手を添えても抵抗がなかった。ゆっくり顔を起こして、少し厚い唇に自分のそれを寄せる。触れただけなので音もなく唇が離れる。あっけにとられた顔をしていたのがいい気味なのでふふんと笑って、もう一度口づけた。今度はわざとらしくちゅ、と音を鳴らす。肌の匂いと消毒液の匂い。自分より高い体温の匂い。
えらく懐いて来るとおもったら、とTETSUは低い声でうなった。
「……カラダ目当てかよ」
「いまそうなったかも。なんかそういう気持ちになった」
「女だろうが、もっと自分を大切にしろ」
「学校の先生みたいなこと言うんだね」
「身体機能を考えてみなよ。世の中ろくでもねぇ話が多すぎるんだぜ」
そもそも同意を取れ、と正論を言われたけど、じゃあTETSUさんも注射打つ前は同意を取ってよ、と返すと黙り込んだ。
「TETSUさんみたいな男、多分人生で二度と出会えないんだから。ここで思い出くらい作っても許される気がする」
「俺は怪我人だぞ、盛ってんじゃねぇよ」
見ろよこの腕、と、包帯が巻かれた左腕をひらひらとされる。
「…………」
「………………」
「ず、ずるい物言い……」
「フッ」
話はここでおしまいとばかりに、一笑に付してTETSUは寝転んでシーツを被る。自然な流れで一緒に横になって、あ、ベッドは大男の怪我人に譲ってソファのが良かったかなと思い直したけど、眼の前の男がご丁寧に私が寝やすいように少し身体の位置をずらしたので、テリトリーから抜け出るタイミングをなくしてしまった。
目を閉じれば、眠気の続きがすぐにやってくる。こっちは日が昇ったらカニ食べる気満々なのでTETSUにしがみついた。こうしないとどっか逃げそうだったし。

腕の中で目覚めると、大立ち回りをしてきた怪我人はさすがに疲れていたのだろう。すーすーと意外と静かな寝息を立てていた。ともすれば生きているか不安にレベルの静寂だ。
眠るときにも眉間のシワが深い。この人の正確な年齢は知らないが、瞳を閉じるとぐっと精悍さを増す。
「……ぅ…………」
やべ、起こした? と静かに慌てたが、長いまつげの間からあの野性味と少年にグリッター気分で少しの狂気を混ぜたキラキラの瞳が覗くことはなく、ぎゅっとまぶたを閉じたままうんうんうなされているようだった。
「……け、ぇ……」
なんだかわかんないけど苦しいみたいだ。縋るように手が伸びてきて、私を通り過ぎてシーツを掴む。この腕力で掴まれたらただじゃおかなさそうだけど、それはそれとして眼の前にいるのにスルーされると、相手にされてないのが如実に現れていて少し寂しい。この人の世界に私の居場所はないのだ。
「……よーしよし、つらいんだねー」
男の人を慰めるのってわりと得意かも。人から警戒されないのと同じくらいには。苦しくない程度に、ぎゅうと胸に抱きすくめる。落ち込んだときはおっぱいを揉むのがベターだ。男も女も人類の過半数はおっぱいの世話になって大きくなってるのだから。女体嫌いには逆効果だけどそういう感じではないしね。男は兄さんとケーとやらを繰り返し呼んでは、浅い眠りの淵でもがいている。意外と柔らかい髪の毛を撫でていると、ラクトンⅭ10臭が効いたのか、少しずつ呼吸が落ち着いていくのを胸で感じた。
キレーな骨格してんなぁとしばらく眺めていると、少し湿ったまつげが震えた。小さく身じろぎして小鳥が目覚めるみたいにやわらかく瞼が開く。寝起きのかすれた声がまごつくみたいに小さく零れ、悪態をつく。
「―――けが人に盛るなっつったろ……」
「盛ってないよ慰めてたの」
「おめェ俺じゃなきゃとっくにヤり捨てられてんぞ」
「TETSUさんじゃなきゃこんなことしないけどね」
そォかよ、とどうでもよさげに呟き、少し生えた髭を搔きながらのそのそと洗面室へ消える。眠り姫が一気におっさんになったのを見た気分だ。午前十時に消えるタイプの魔法らしい。
戻ってきたTETSUは「無精髭のでかいおっさん」から「怪しい風体のでかいおじさま」程度には小綺麗になっていた。こっちは昨日のシャワーでプリミティブなすっぴん姿になってたので怪しくとも美丈夫である闇医者を前にしてちょっと恥ずかしくなってきた。けどそもそも初対面でゲロと胃内容物を晒していたので、さっさ開き直ることにする。胃液なんて元カレにも見せたことなかったのに。
「あ、洗濯機回してくれたんですね」
TETSUがシャワー浴びるのを待とうと思っていた洗濯だが、彼により意識の強制シャットアウトを謀られたので結局回せていなかったのだ。寝ている間にやっといてくれたらしい。―――いや、気遣いというよりは、廃工場に戻ったときに結構な出血や返り血的なのを浴びただろうからそれを洗いたかっただけか。ともあれ洗濯乾燥の終わった服はほかほかで、生活の気配がした。一気に日常に戻ってきた感じがする。まだ全然富山の知らないラブホテルだけど。そろそろ帰りたいな。
「あ、でもその前に蟹だよ蟹! この時間ならもうお店開いてるよね」
「なんでテメェと蟹食いに行かなきゃならんのだ」
「今回の思い出を富山旅行ってことに上書きしたいです」
「一人で行け」
「祝勝会しましょうよォ、私TETSUさんとまだ話したいことあるし」
「俺にはねぇんだよ」
とはいえ、引っ張ったら普通についてきてくれた。
繁華街はまだ眠っていたが、十一時頃になるとランチで開いている店もちらほらと見られて、その中の一つに適当に飛び込む。平日の昼間っから食べる蟹は美味しかったし、多分私は蟹を前にした人類史上一番よく喋ったと思う。TETSUはセオリー通り口数は少なかったけど。
蟹ちらし食べながら元カレの話をしてたら、同情したのかTETSUが奢ってくれた。生きてるといいことあるね。蟹ちらしは文句なしに星5リピありの味だったが、元カレのレビューは「殴ってもよかったんじゃねぇか」と男性目線でも辛口評価だった。勢いで仕事やめたと言ったらそっちも「後先考えろ」と低評価。そりゃそう。私も他人がそんなことしてたら止める。
蟹を食べたあと、さてどうしたもんかと帰路について思い巡らす。こちとら退職前の身なので、基本的には節約したいものだ。
高速バスか、電車か……。疲労困憊なので体力的にはかなりきついがバスしかないだろうかと考えていると、どこかに行っていたTETSUが戻ってくる。
「おい、飛行機とれたぞ」
「え、あ、ええ、お金……」
「人の金で蟹食っといて今更なやつだな」
なんて言われて、あっという間に機上の人になってしまった。
最初は流石に恐縮したけど、高度が安定したあたりで意識が飛び飛びになって最終的には健やかに寝ていた。プレミアムクラスじゃなかったらTETSUにもたれかかっていただろう。なんでわざわざアップグレード席、と思ったけど、このひと体がでかいからエコノミーだと窮屈なのかもしれない。こんなでかくていかつくて前髪長い人乗ってきたら隣の席の人も気まずいだろうしね。
離陸直後、窓から富山を見てみよう、と思ったけど窓際のTETSUがじっと外を見ていたので、邪魔しないように前に向き直った。月並みなことだけ書いてある機内安全マニュアルを見てたら、すぐに眠気は襲ってきた。
眠気の急襲は羽田についても全然覚めることはなく、というか薬、頸動脈絞め落とし、再度薬で眠らされて私の体内時計もうめちゃくちゃなんじゃないかな。とにかく飛行機を降りてもむにゃむにゃしていた。
「いい加減起きろよ」
「むにゃ、だめだTETSUさん、これ帰れない……」
「捨ててっていいか」
「次に連れ込まれる廃墟にも居てね……」
「…………」
タクシーで送ってくれた。
だんだんわかってきたけど、この人主導権取るの苦手っぽい。そりゃセックスしようとしても躱されるわけだよ、えっちってコミュニケーションの極北だし。段階を踏めと言うわけだ。まずは交換日記からか、あるいはお茶からか。
「コーヒーくらいだすよ」
と、玄関に入っても靴を脱ぎたがらない男の裾を引っぱる。空港から結構な距離だったので耐え難い眠気も落ち着いていた。後ろ手に玄関扉を閉めると、怪訝そうな顔をされる。
「よく知らねぇ男を家にあげんな」
「私TETSUさんにゲロも見られてるし九死に一生スペシャルもしたし、今更じゃない?」
「まともな人間ってのはよ」
普通はよ、と。闇医者のなのにまともな人間とはなにかみたいな講釈を垂れてくれるらしい。なにがまともかわかんないと闇医者ってできないのかもな。光がわかんないと闇ってわかんないし、闇がなければ光は生まれない。
「世話になったってわかってても、廃墟くんだりまで礼をしに来ねぇんだよ。女なら特にな。なぜかわかるか」
なんとなくわかる。頷く私を見てTETSUが言葉を続ける。
「アブねぇからだよ。実際、テメェは俺と拉致されてんだろ。まともな神経してりゃ廃墟の仏壇整えたりもしねぇし、一緒にホテルに泊まったりもしねぇ」
よっぽど育ちがいいのか、よっぽど馬鹿なのか。と、唸っている様は少し面白い。
「でも、TETSUさん……。めちゃくちゃ私の好みなので、バカにもなるというか」
「――――……………………」
絶句させてしまったけど、私だって結構年上の闇医者にこんな気持ちになるのは予想外なのだ。恋と言うにはかなり下世話な感情すぎるけど。
「口の硬い女とヤリたくなったら来て」
「そんな提案は女の扱いを知らねぇどっかの馬鹿にでもしなよ」
「じゃあ何でもなくても偶に来てよ」
ここ来てTETSUは漸く、自分の眼の前にいる女が相当碌でも無いことに気づいたみたいだ。そう、私はカッとなって仕事辞めて、廃病院にものこのこ現れて、拉致監禁ダイハードをやっても怯まないタイプの人間なので諦めてほしい。私の人生どうせいつかめちゃくちゃになるなら、その原因はこの人がいい、と思ったのだ。
黙ってしまったので、これ幸いとかなり頑張って背伸びをして唇をくっつける。抵抗はされなかった。こっちが引くとTETSUも引くのに、押すとされるがままになるとこ可愛いなって本気で思う。調子に乗ってちゅ、ちゅ、と繰り返し可愛さの余韻を味わってると、がしっと大きな手が私の頭に触れた。身構える間もなく、少し上を向けられてそこに唇が落ちてくる。私のやってることが「ちゅー」ならこの人のは「キス」通り越して「キッス」だった。古風に「口吸い」と呼んでもよかったかもしれない。逃げようとする舌を攫われて、擽るように触れられる。くちゅくちゅと唾液の絡む音が鼓膜に響いて、脳を揺らす。
「んふ、ふぁ」
いつの間にか壁際に追い詰められていて、上背を丸めた男に覆いかぶさられている。震える腰に鞭打って、目の前の大型動物にしがみつく。あ、だめ、落ちる。そう思った瞬間に唇が離れた。
「っふ、―――あんまり下手なんでな」
開放された呼吸機能ではぁはぁと必死に息を吸えば、開きっぱなしの口から垂れる。唾液を親指が拭う。キスの仕方くれぇは教えに来てやるよ、と男は悪辣な顔で言った。