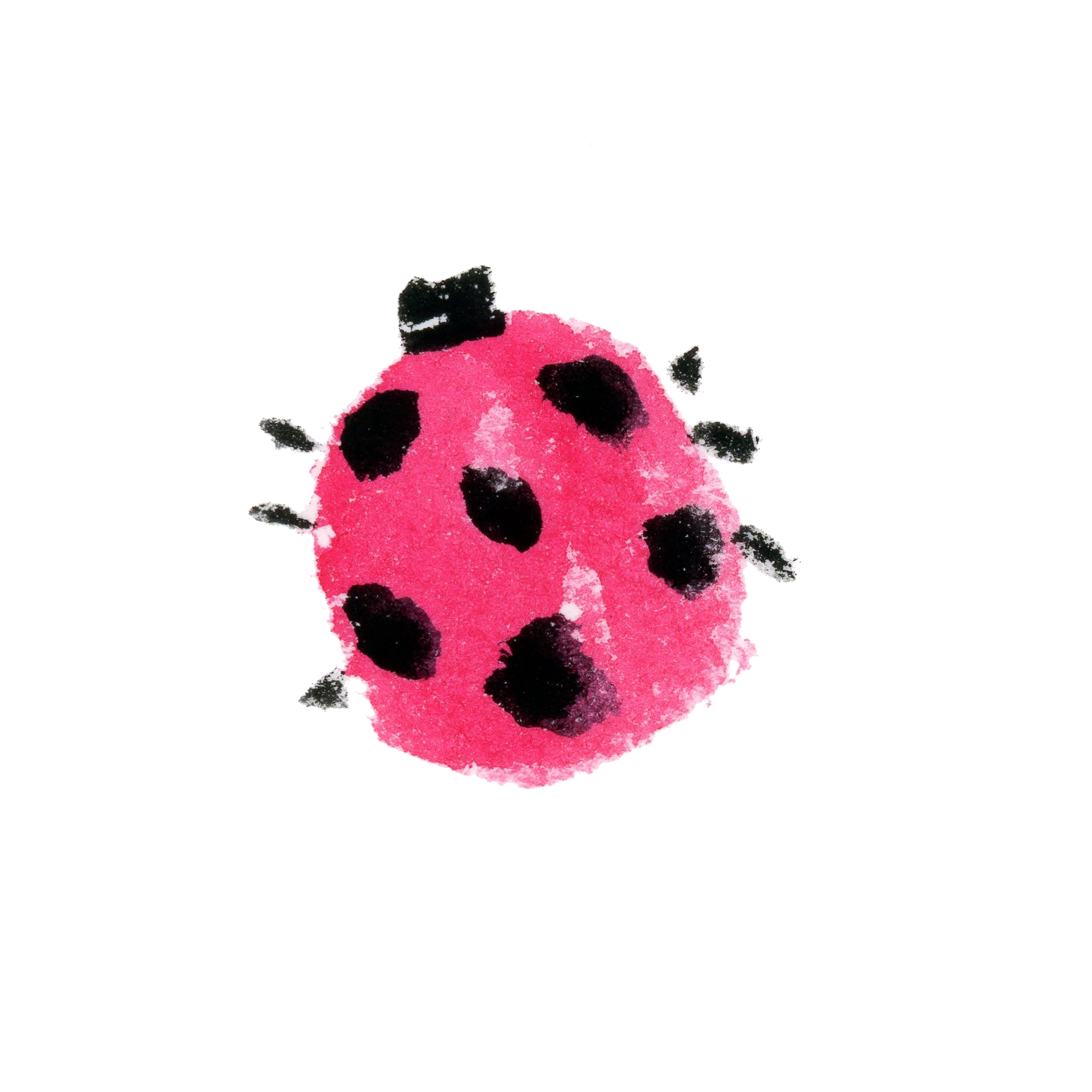
1-1
人生、いつかこんな日が来るんだろうと思ってた。
最初に、そう、そんな考えに行き着いたのはいつだったか。多分中学の頃別に好きでもない男の子に「ごめん、他に好きな子いるんだ」と振られたときかな。あれはそもそも友達の話に合わせて「あーかっこいいよねー」とか適当に話を合わせていただけだったのに。あるいは推薦枠争奪のときに「のびしろ」とかいう訳のわからん理由で私よりも成績の低い男子に席を譲らされたときか。ともかく人生の殆どの期間、頭の片隅に「自分の人生いつかめちゃくちゃになるんだろうな」という予感があった。
彼氏だと思ってた男が浮気してて、実は本命は他の女の方だった。つまり彼氏の婚約者からしたら私のほうが浮気相手である。そんなことってある? って思ったけどよくよく思い起こせばなんとなくそれらしいヒントはあった。他人の欠点に目をつぶ
るのが得意ゆえ、彼氏(……もはやそんなんじゃないけど)の怪しい部分からもしっかり目を反らしていたらしい。
そしてそれを会社経由で知ることとなった。社内では私たちの交際は皆の知るところだったので、みんなやや同情的だったが、それはそれとして上司は私に告げた。
「まぁ、ね。向こうさんも訴訟を考えてるらしくてね」
「はぁ」
「○○くんか、あなた、どちらかを別の部署にしてほしいと」
そして私のことを飛ばすことにしたらしい。なぜ私。原因作った元カレのほうではなく。のびしろとか言い出したらぶっとばそうかな。
「いやぁ、ね。彼のほうが成長株というかね」
ぶっとばした。
嘘です、さすがにそこまではしてない。社員証を首からぶちりともぎ取って床に放り捨てただけだ。辞めてやる、と思った。
そんなこんなで、恋人と社会的信用と職を同時に失った私は、さすがのさすがにやさぐれていた。自分のバカさとか、短慮さ(これはホントそうだよねぇ)とか、どうしようもない虚しさとか。
特別好きだったわけじゃなかったのに。そんな相手とずるずると関係を続けて、挙げ句このオチだ。無様すぎて笑えてくる。仲の良かった後輩から「絶対許せないから、○○のデスクの朱肉をうちの部署で一番ボロくてカッスカスな私のと変えてきました」という慰めメールが来たことくらいが唯一の救いだ。にんげんってやさしい。でもあなたこないだ間違えて自分の印鑑に黒インクつけたあと慌てて朱肉につけてたから、真っ赤な海にしっかりあなたの苗字が刻み込まれてるよ。バレるよ。
こういう日に、人間にできることは少ない。
竹が折れないのはしなやかに曲がるからだが、しなやかに曲がれるのは中身がからっぽだからだ。人も、折れないために中身を空にする必要がある。
やけを起こした私はもう全部どうでも良くなって、歓楽街をさまよっていた。嵐をやり過ごす一番簡単なことは、酒を飲んで寝ることだ。今日とか明日とか明後日とかのことを考えず、今晩のことすら考えずに、落ち込む思考を緊急停止。ありきたりな生存戦略。飲んで飲んで飲まれて飲んで、途中見知らぬ男二人が声をかけてきたけど、軽くスルーして痛飲。泥水。頭痛、眠気。―――あれ? とはいえそこまで飲んだ覚えもないけどなぁ? 眠気。眠気。眠気。眠気。―――おかしいなぁ。ふらつき。めまい。嘔吐感。
あとは無。

「―――っは」
浮上。消えていた意識がふっと現世に舞い戻る。睡眠って簡易的な死かもね。うすい痛みと違和感で、腕に「刺さっている」なにかを抜き取る。直後、すべてのシチュエーションのおかしさに気づいて飛び起きた。上にかかってた布がばさりと落ちる。
「は、え?」
ぷらぷらと真横でチューブが揺れて、引き抜いたそれが点滴だと知る。少し目を凝らすとだんだんと周囲の状況が把握できた。無理に腕から抜いたので、引き攣れて少し血が滲んでいる。真っ暗な部屋に壊れた蛍光灯、壊れたブラインド。街明かりがそこから差し込んで床に散らばる。ベッドの頭には、かつてなにかの機械が埋め込まれていた形跡がある。そうまるで、病院みたいな。
一見して廃墟だが、不思議とシーツからは埃っぽさがない。
「ようやくお目覚めか」
声がした。
跳ねるように後ずさって、背中がブラインドをがしゃんと潰す。
部屋の真ん中に置かれた応接用らしきソファに、大きくて薄白い影が座っている。
「まったく悪運の強ぇ女だな」
別に面白くないのに、それっぽいから一応笑ってる、みたいな声だった。低いが明瞭で、少し掠れている。
良い声だ。
「だ、誰?」
「そんなことよりも自分の身体を心配してな」
「っ」
慌てて自分の体を顧みる。吐いた痕跡がある。床に私のカバンが放り捨てられていた。酩酊嘔吐後特有の頭痛と喉のいがらっぽさ。身体のだるさ。意外とお腹は軽い。ブラのホックは外れていた。バッと彼を見る。
「おっと、俺じゃねぇよ。治療にゃ都合良かったがな」
「治療……?」
「胃洗浄と点滴だ。大方、酒になにか混ぜものでもされたんだろう」
これに懲りたら、自分のグラスは手放すなよ。と説教めいたことを言って男はソファから立ち上がる。
月光に照らされて男の面容が浮かび上がる。年嵩の色男だ。年齢は四十絡みといったくらいだろうか。後ろ髪が長い、それ以上に前髪が長い。切れ長の瞳にすっと通った鼻梁、細めだががっしりとした顎。立体感のある造形で、光に照らされた陰影は彫刻のように明瞭だ。かなりの長身で、それをひょいと少し丸めている。私が着たら引きずりそうな丈のトレンチコート。恐ろしく長い足が頑丈そうなロングブーツに包まれている。百人中百二十人が「カタギじゃない」と判断しそうな男が、そこにいた。
呆けている私を見て「チッ、なにも覚えてねぇのかよ」と少し苛立ったみたいだ。
「あんたは男二人に抱えられてここに来たんだよ。大方、薬で潰して廃墟に連れ込んでマワす気だったんだろう」
ありゃ手慣れてたな、と男は眉根を寄せて唇を歪めて不愉快そうだ。全体的なパーツが大振りなので迫力がある。見てるだけで怖気づくほどだ。
「だが生憎ここは俺のヤサなんでね。解散してもらった」
「そ、その人たちはどこに?」
「さぁな」
さぁって。
この人には関係ないことだもんなぁ……。助けてもらった(?)だけで恩の字だろう。
「立てるんならさっさと出ていけよ」
私に背を向けて、男はドアから出ていく。足音が響く、遠ざかる。廊下を右の方に歩いてったみたいだ。ドアの音、閉める音。
ヤサって言ってたし、ここに住んでるのだろうか。
立ち上がろうとしたが、うまく足が立たずぺたんと床に座り込む。薬の影響が、疲労か。古くひび割れたリノリウムは冷たくてゾッとした。
その瞬間、スイッチを入れ直したみたいにバクンと心臓が跳ねた。ぶわりと汗が出て今更な警戒警報が頭に響く。完全な異常事態だし犯罪に巻き込まれてるし被害者になりかけた。と言うかすでに被害者か。たまたま運良く外傷なく生きてるだけだ。いまここで大きな怪我なく五体満足で居るのは奇跡だ。そんな自覚が決壊するように溢れてくる。根性だけでベッドを支えに立ち上がる。うん、歩ける。「逃げられる」。カバンをしっかりと掴む。
本当に逃れるべき相手はもうここに居なかったけど、とにかく体が逃げたがるから衝動的に走った。ドアを開けて、男の去った方を見る。廊下だ。反対側を振り向くと、いかにも病院の名残らしい受付カウンターと出入り口があった。廊下で朽ちかけている健康習慣ポスターを横目に走って、ひび割れた自動ドアだったものを横に引っ張る。少し重いがちゃんと開いた。外だ。深い時間を通り過ぎて夜明けの直前、街灯だけが明るい。振り向くと、廃病院は一層暗く、いまにも深い闇の中からなにかが現れそうで恐ろしかった。あわてて、開けたときと同じように曇ったガラスのドアを閉める。
大きい通りへ出ると、詳しくはないものの見覚えのある道だった。この位置なら駅からそう遠くない。どこかであの男達に見られてるんじゃないかと疑心暗鬼になって、駅前でタクシーを拾う。血相を変えた私に運転手は少し訝しんだが、特に何も聞いてこなかった。あ、貴重品。と思ってカバンをあさると、中身には特段変化はなかった。家の鍵も携帯電話も財布もある。減っているものはなにもない。個人情報を握られてる恐れは依然あるが、少しだけ冷静になれた。
自宅のひとつ前の路地で降ろしてもらい、少なくない金額を払う。ふらふらしながらアパートの階段を上り、安普請のドアを開いた。しっかりと鍵とチェーンをかけて、上着とカバンを放り捨てる。ベッドに倒れこんで、そこで意識は途切れた。
―――携帯電話の振動で意識が浮上して、今日がいつかわからないまま目を覚ます。仕事、と思ったけど昨日退職願とともに有休消化のターンに突入したんだった、と思い出す。着信はすでに止まっていた。ぱくりと開くと、不在履歴が3回分、知らない番号。いったん無視してベッドから這いずり出る。
時刻はもう昼前、カーテンの隙間から差し込む日差しは高く、燃えるゴミの日だったけどゴミを出し忘れたことを思い出した。床に座り込んでベッドにもたれかかると、携帯が4度目の着信を告げる。またも同じ番号。面倒くさいなと思いながら、職場関係の電話の可能性が1%くらい存在するので、一応通話ボタンを押す。
「……はい」
『〇×警察署の××と申しますが、ミョウジ様のお電話でお間違いないですか』
一気に覚醒した頭で、要件を手近にあった紙に書きなぐる。通話が終わった後着信があった番号で調べると、地域の警察署の番号であることが判明した。

シャワーを浴びて歯を磨いて、一応真人間っぽい容姿に整えて家を出る。まっすぐに昇った太陽が熱くてまぶしい。昨日の後遺症だろうか。じりじりした日差しに負けてところどころ休憩しながら、平素の倍は時間をかけて最寄りの警察署にたどり着いた。アポっていた名前を告げて何らかの部屋に通してもらう。ほどなくして恰幅のいい年かさの男性と、私より少し年下くらいの女性が現れる。
おじさんめいた男性警察官が「ああ」と声を上げる。手にはなにやら資料。
「○○病院から情報提供があった件だね」
なぁにそれ、とは言えずに「はぁ」とついついわかるふりして適当に返事をする。彼は女性警察官に「胃洗浄で薬物反応が出てるから」とカタカナの薬品名を交えながら簡単に説明する。
「点滴もしてもらったんでしょ。○○先生してはマメだね。あそこヤブって話だけどねぇ」
体調がいいならいいんだけどさ。なんてのんきに言う警察官を、しっかりしてそうな年下の女性警察官がたしなめる。そして責任感の燃える瞳が気遣わしげに私を見た。
「類似の事案が捜査中なので、関連性が疑われています」
必ず検挙しますので、任せてください。と、力強くて頼もしい凛とした声に、私は情けなく「はい……」と返事する他なかった。他にもつらい目に遭っている人がいるかもしれないと思うと、とても安心はできない。自分だけ謎の男により救われたっぽいことに罪悪感すら覚える。
「ですが、今後はできるだけすぐに警察のほうにも来てくださいね、お辛いとは思いますが、きっとお力になれますので」
やんわりと説教までされた。慮ったものなのも正しいことなのもわかるけど、正論ってこういう時すこし胃に重い。ショックやら疲労やら罪悪感やら多分後遺症的なもののせいでぼんやりしてる頭は「○○病院、○○先生」の名前を刻みつけるので精一杯だった。
調べてたどりついた隣駅最寄りの○○病院は、年季の入った町医者って感じだった。雑居ビルの二階。警察署を出たのがもう午後の2時すぎだったので、そのまま病院まで直行した。当然のように見覚えのない病院である。外観通り建物の中も古く雑然としていて、受付のおばさまは愛想がなかった。
「あの、昨晩の件で……○○先生にお取次ぎ願いたいんですが」
「はぁ?」
患者じゃないことに少し――いやめちゃくちゃ露骨に――不信感を露わにした彼女はめんどくさそうに「先生! 客だよ!」と奥の部屋に声をかけた。
奥からのっそりと現れたのは小太りのおじいさんで、私を見て首を傾げる。アザラシに似てた。
「何用かね」
「すみません、警察に情報提供いただいた件なんですが……」
そう言った途端にアザラシ先生はのんびりした口調からは想像もできないような剣幕で目をむく。唇を震わせて、動揺を隠せない様子で「ここじゃなんだから」と私を診察室へ引きずり込んだ。受付の女性は怪しそうに診察室を覗いたが、先生に追い払われて方をすくめて扉を閉める。
「こっ……困るんだよ! ああいった奴の関係者に表からこられちゃ」
「え? あの……?」
「うちの名前は貸しただけだっ、検査も手続きもそっちの領分だろう⁉」
青ざめて取り乱す先生は、もはやアザラシというよりは栃狂ったドラえもんに近かった。これでもないあれでもない! ってパニクッて道具投げてる時のやつ。
そして叫んだ。
「闇医者なんぞに借りを作るんじゃなかった‼」
「え、あ、あの、よく意味が……」
「なんだって! あんたドクターTETSUの関係者じゃないのか⁉」
いや誰。ていうか今日日闇医者て。口軽そうだなこのおっさん。と思った気持ちがそのまま顔に出ていたのだろう。「とにかく、もううちには関係ない」とそのまま病院を追い出される。
なるほど、これはもうふりだしに戻るしかないのだろうか。
この時間になってやっと身体が本調子に戻ってきたので、目的地の途中デパ地下に寄っておもたせを買う。駅から目的地までは意外と道を覚えていて、すんなりとたどり着くことができた。まだ陽のあるうちに見る廃病院は、ガラスは割れていて蔦が絡まって、小さな前庭には育ちすぎたサボテンと背の高い雑草がエキゾチックな得体の知れなさをかもしだしていた。普通なら絶対近づかない。
「あのー……」
昨晩と同じように自動ドアを手動であけて、夕日が差し込む薄暗くて冷たい屋内に足を差し込む。一歩歩く度に、ホコリや小石やガラスの破片を踏みしめるハメになるので、自然と慎重な足取りになる。昨日は気づかなかったものたちだけれど、よく転ばずに走り抜けられたものだ。
手にはデパ地下の紙袋を下げていて、中身は焼き菓子とコーヒーの簡単なギフトが入っている。謝罪とお礼だ。経緯は何であれどうやら助けられたみたいだし、謎のツテでヤブ医者を経由したとはいえ警察への情報提供もしてくれているのだ。結構な手間をかけさせてしまったらしい。挨拶くらいはすべきだと思ったのだが。
「えーっと、ドクター、テツ、さん?」
撮り鉄みたいな名前だね。
夕方の日差しが宙を舞うホコリをちらちら光らせる中、昨夜自分が目覚めた部屋までたどり着く。引き戸は開けっ放しで、中を覗き込むと自分が目覚めたときのまま。落ちた毛布とひしゃげたブラインド。もぬけの殻だった。
「おい」
「ぎゃあっ」
突然背後から声がして、びっくりして前のめりに慌てる。バランスを崩した身体をこれまた後ろから回された腕が支えて、ホコリだらけの床に顔から倒れずに済んた。両手で紙袋を抱え込んでいたから重力に抗う術がなかったのだ。
振り向くと、人間の中でも比較的壁に似てるタイプの男が立っていた。昨夜と同じく、装甲みたいな前髪とトレンチコート。私が立ち直ったのを見て腕が外される。二、三歩後退りして間合いを取ると、周囲と比較できる分だけ男のデカさがより際立った。日本家屋だとちょっと暮らしづらいような規格感だ。
「てめぇ、昨日の……。のこのこ何しに来やがった」
「え、ええと……」
まぁのこのこですよね。のこのこ以外の表現が不適格ってくらいのこのこだと思う。日本語力満点だ。
「あの、昨日はお世話になりました……」
差し出した紙袋に多少警戒したようで、空気がピリつく。高○屋、お気に召しませんか。
「帰れよ、あんたみてェのが来るとこじゃねェ」
「す、すぐ帰ります……」
お邪魔しましたするために紙袋を押し付ける。このために来たので受け取ってもらわずにすごすごとは帰れない。物事には対価がある。借りは返すもの。なにかをしてもらったら「ありがとう」なんて小学生でもできること。そうせずにぬけぬけと安穏に暮らすのは居心地が悪い。さっきは気圧されて変なイントネーションだったので、改めて言い直す。場に慣れて動揺が収まってきたので、今度はまともな言葉を紡げた。
「昨日は助けていただいてありがとうございます」
下げた頭に舌打ちが降ってくる。助けたわけじゃねぇよ、と呟くみたいな小さい音が私のつむじにぽろりと落ちた。
頭を上げると、不快そうにひしゃげられた瞳とかち合う。瞳の色、そんな感じなんだ。相手の方が先に目を反らして、紙袋から箱を取り出し、残りを私に押し付ける。白い紙箱に入ったコーヒーだけが彼の手元に残った。
「じゃあな、二度と来んなよ」
酒とクスリにゃ気をつけな、と。背中を向けてあばよとばかりにひらりと手をあげる。遠ざかる背中に慌てて「待って」と声をかけた。意外と素直に立ち止まってこちらに視線を向けたので、二の句を告げずにまごついた。自分でも、どうして呼び止めたのか分からなかった。
けどそんな気まずさもすぐに消し飛んだ。
「―――後ろっ!」
もう日も落ちて薄闇に包まれた廊下、そのなかからぬるりと出てきた影。
叫んだ声に向き直った男が、振り下ろされる鉄パイプを蹴り飛ばす。
そのまま相手の男―――ドクターTETSUよりも幾分小柄だが、成人男性としては立派な体躯―――に踵落としを決める。
「んだよッ……」
流れるように別の男の顎に下から拳で殴りあげて、そのままこちらを見やる動作まで、決められた一連の振り付けみたいにぴたりとキマっていた。
「てめぇ、グルか⁉」
「ちがいまっ……!」
ふいに身体を後ろに引っ張られて、口を塞がれる。ぐっと首を絞められる感覚がした。今週の星占い、気絶運★★★★★かも。